今日も暑いですね。
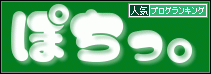
↑↑応援お願いします↑↑

↑↑応援お願いします↑↑
昨日、ある本が欲しくて書店に行ったのですが
お目当ての本がない。
帰宅後
アマゾンで二冊ポチった丸山です。
さて
今年に入り、丸山は体調を崩さず生活をしているわけですが
夏風邪などひいていませんか?
風邪をひいたり病気にならないようにするには
免疫力が大事なのはあなたも知っているはず。
それには健康でいるのが一番なわけで
植物はどのように自己管理をしているのでしょうか?
という事で今日はこんな話題を。
◆「植物が虫からどのように身を守るか」
植物は虫から自身を守るために毒を持っている。
アブラナ科の植物は
「からし油」
と言う物質で動物や昆虫による食害から身を守っています。
経験があると思いますが、
大根をすりおろした時に「辛い」と感じたことがあるはず。
まさにそれですね。
有名な所で言うと
お茶の
「タンニン」
でしょうか。
タンニンには
消化器官の粘膜に影響を与え、消化吸収に障害を出す
機能があります。
なぜお茶がこういうタンニンを持つようになったのか?
それは
お茶に付く害虫がお茶の葉を食害するから。
害虫:「うひゃー、この葉っぱウメー!!!みんな食べに来いよ♪」
むしゃむしゃ。
お茶:「このまま食べられていたままでは
葉っぱがなくなってしまうよぉ。」
「そうだ!!あいつらに一泡食わせてやろう」
害虫:「やっぱり、この葉っぱ最高だね♪」
「ん?あれ?ちょっとお腹が痛くなってきたよ?」
「おいおい、そんなわけ。。。お、お腹痛い」
「なにこれ?
この葉っぱいつからこんなようになったの?」
と実際にこういうやり取りがあったかは知りませんが
わかりやすく言うとこういう事ですね。
お茶が害虫から食害されないようにするために
消化吸収に障害を与える物質を出して防御するようになった。
んで、こういう物質を出すのには
パターンが2つあって
①元々持っている場合
と
②食害などされた時にだけ毒素をだす場合
がある。
①元々持っている場合
トマトのトマチンとか
タバコのニコチン。
トマトのトマチンは
~~~~~~~~~~~~~~
花(1100 mg/kg)
葉(975 mg/kg)
茎(896 mg/kg)
未熟果実(465 mg/kg)
熟した青い果実(48 mg/kg)
完熟果実(0.4 mg/kg)
含まれており未熟果実でも
34個を一挙に食べないと半致死量には達しない
~~~~~~~~~~~~~~
との事。
トマトの毒 トマチンより一部抜粋。
子孫を残したいトマトは
種が出来ていない時に食べられては困る。
だから完熟に向かうにつれてトマチンの含有量が少なくなっていっています。
完熟した物でも極微量含んでいて
元々持っているパターンですね。
次に
②食害などされた時にだけ毒素をだす場合
毒素をずっと作り続けるには植物にとって労力がかかる。
だから省エネ志向な植物は
葉などを傷付けられたときに毒素を生産する。
食害された時に防御していて
虫がつくと苦くなる野菜もある。
これだけ見ると、植物って凄いって感じる。
虫に食べられることないじゃんって思ったあなた。
そうですね。
ただ、虫もバカじゃない。
作物を栽培しているときに、必ずと言っていいほど遭遇する問題。
害虫です。
こうやって植物のみが害虫から身を守るようになった訳ではなく
それに対抗するべく耐性を持つ害虫が出てくるわけです。
また
その毒素を分解、解毒したりする。
んで、人間も毒を消すのがウマい。
通常、生で食べると
「辛い物」
や
「えぐ味」
のある物。
これを料理して解消するんですね。
玉ねぎは生だと辛いけれど、熱を加えると甘くなる。
上手く毒と付き合っているんですね。
散々「毒」と言う言葉を使い
野菜には「毒」があって食べると良くない物だ。
と判断してしまう人がいるかもしれない。
しかし、今は品種改良が進みその毒素が弱まっています。
原種に近いほどおいしいとは感じないはず。
こうやって品種改良が進み
人間にとっておいしいと感じる野菜が出来てきました。
それは同時に虫たちにとっても
好都合であり、虫たちにもおいしい野菜です。
しかもその食害する虫たちは栄養過多の野菜を好む。
同じ野菜でも栄養がたくさん含まれている方が
成長しやすい事を虫は知っています。
(ここで言う栄養過多の野菜は、虫にとっての物です。人間にとって栄養価が高いという意味ではないです。要するに肥料過多の野菜ですね。)
恐るべし害虫。
ただこの害虫にも植物とは別の敵がいる。
聞いたことあるかな?
「天敵」
と呼ばれる害虫を食べる野菜を栽培するうえで
人間にとって小さいけれど大きな味方。
草食系「害虫」
に対し
肉食系「天敵」
人間界と似ていて
肉食系「天敵」の方が成長も早く元気な場合が多い。
少し余談ですが
野菜がおいしくなり、害虫が多くなった。
ただその背景には農薬使用や、畑を耕すことで天敵が減った事も考えられる。
殺虫剤を使用したことで
その害虫や、他の害虫が増える事を「リサージェンス」という。
テストに出るから覚えておいてください。
要するに殺虫剤で「天敵」まで殺してしまったという事ですね。
話を戻します。
こうなると、さっきまで害虫恐るべしだったのが
天敵恐るべしになります。
もはや、自然界のハンターですね。
害虫:「よし、ここにはハンターがいないな。みんな今のうちにお腹いっぱい食べるんだ♪」
すると、かじった時に葉から臭いが発生する。
天敵:「ムムッ?どっかで奴らが無断飲食中だ。こりゃ取り締まらないといかん!!」
その臭いを嗅ぎつけ天敵がそこ急行する。
それにより食害の被害が少なくなる事も少なくない。
こういう事が実際植物界では起きています。
良く無農薬野菜を好む人がいますね。
ほとんどの植物は自分を守るために「毒」を持っています。
野菜だって例外じゃない。
品種改良が進み毒素が弱まり、それを補う様に農薬の散布をします。
農薬を散布しない分
植物は自分で自分を守るための毒素を生成します。
ここでは詳しく触れませんが、農薬と無農薬野菜が作り出す毒素。
無農薬だからって農薬かけた物より安全なんてことはないです。
どっちが安全とかそもそもないと思うし
何をもって安全とするのか?
という所は難しいですね。
という事でいかがでしたでしょうか?
あなたにとって何かの参考になると嬉しいです♪
メッセージはこちらから
随時募集中です。
読者登録はこちら
参考文献:野菜だより2013 3月 野菜作り最前線32 ここまで解った植物が虫から身を守るメカニズム