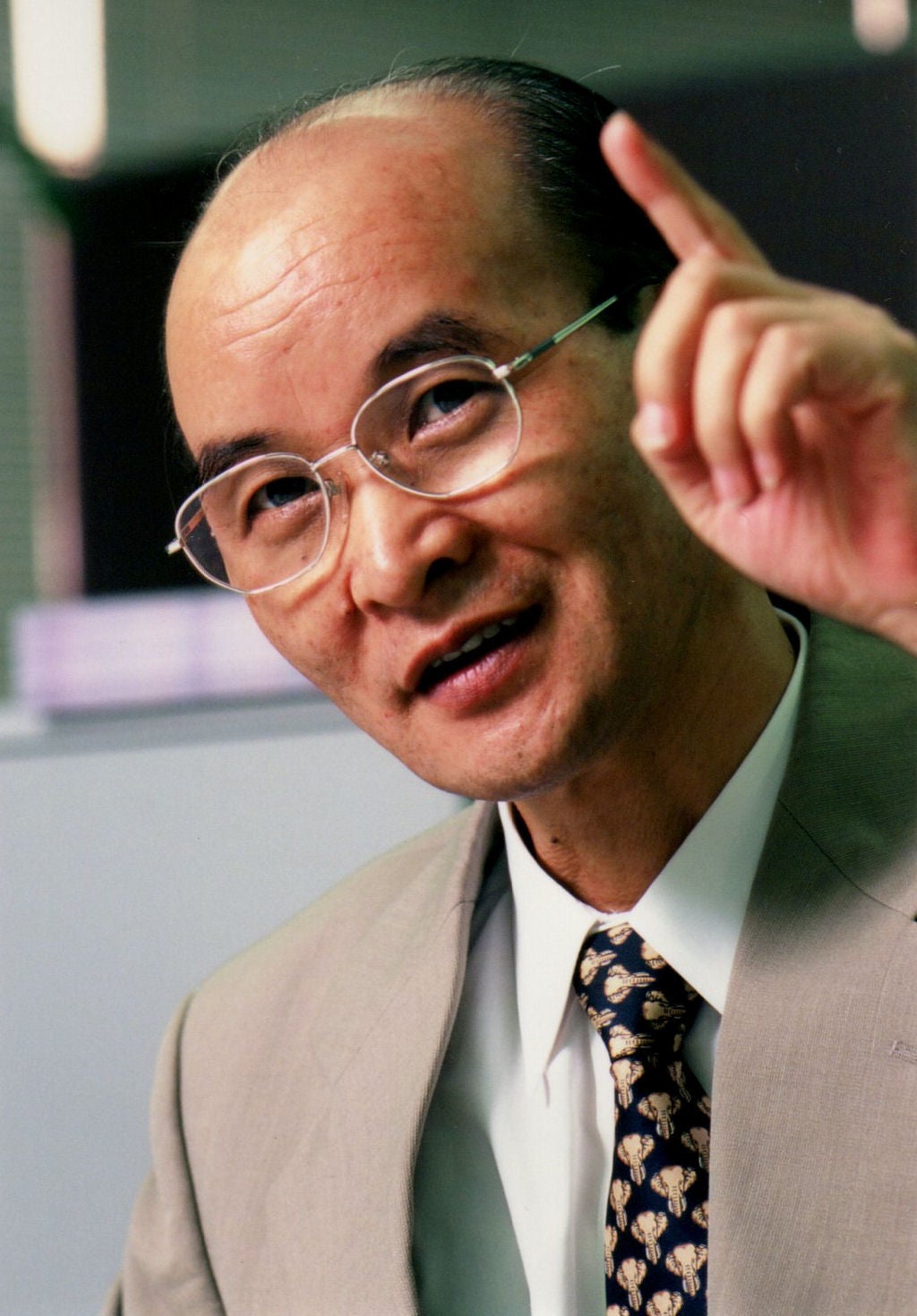■D・H・ロレンス文学の軌跡。――
母は偉大であり、死んでからも追いかけてくる。1
D・H・ロレンス
今朝は夢を見ていたらしい。
「母は偉大である!」というシーンで目がさめた。先日、母の肖像写真が出てきたのを機に、永久保存することを考えていた。北海道のじぶんの母はほんとうに偉大であったとおもう。
夢からさめてみても、依然として「母」がそこにいた。いくつかの深い海峡を渡るとき、じぶんはいつもイギリスを意識して渡った。
徳川幕府を支援したのはフランス、薩長を支援ししたのはイギリスで、明治の鉄道も郵便も海運も灯台も、連合王国英国の技術導入によって実現したものばかりだ。パクス・ブリタニカの幕開けだった。
当時のお雇い外国人2690人中、だんぜん1位はイギリス人の1127人だった。当時の日本は、東洋の英国たらんとしたのである。……ヨーコがまだぐうぐう眠っている。午前4時になって、ぼくは完全に目がさめた。
♪
ちょっとふるい話だけれど、D・H・ロレンスの新訳「ロレンス短編集」(井上義夫編訳、ちくま文庫、2010年)を読んでいて、そこに出てくる「ステンドグラスの破片(A Fragment of Stained Grass)」という小品に目がとまったときのことである。――田園風景と汚れた炭鉱町をモチーフにして書かれたその風景は、彼の小説のなかにも数多く登場してくる。その第1ページには、
「大きな炭坑の3村からはぐれ出た、迷い鳥をかき集めたような、いまでは人家もまばらになり、広大な森林地帯と古いシャーウッドの森や、牧畜と耕作に使われた丘、修道院の廃墟」などが描かれていて、その文章がたいへん美しく、ぼくは北海道のじぶんの生地をおもわず脳裏におもい浮かべた。
最初は「伝説」とか「ルビーのガラス」というタイトルだったらしいけれど、それを1911年に大幅に改稿し、「イングリッシュ・レヴュー」誌に掲載されたものという。しかしふたたび改稿し、1914年に短編集「プロシア士官」の1編として出版された。
フリーダ
ぼくにはどこをどう改稿したのか、その経緯は何もわからない。
しかし現在読めるこの短編は、すばらしいものだとおもう。おそらく「息子と恋人」や、「チャタレー夫人の恋人」を読んだことのある読者には、驚きの1編だろう。
きょうは、文章家としてのD・H・ロレンスについて、少し考えてみたい。
♪
20世紀のはじめごろ、――大まかにいって、そのころのロンドンでは芸術にたいする「過去派」と「未来派」との確執があった。その中心にいたのが詩人たちだった。詩の領域で過去派に背を向けて野心を大いにあらわしたのはエズラ・パウンドという詩人だった。
前代のもろもろの誤った空想を粉砕しようじゃないか。
To smash the false idealitiies of the last age.
お高くかまえた過去派にたいして、産業界のブルーカラーの人びとも乗り出し、あちこちでストライキを起こし、人びとの熱気や体温を熱くした。そのころ、炭鉱夫の息子だったディヴィッド・ハーバート・ロレンス(David Herbert Lawrence 1885-1930年)は、イギリスの文学をひっくり返してしまいそうな、鮮烈なデビューを果たしていた。過去派の人びとは、そういう彼の詩や小説をあらわに嫌悪した。
「女性のまえで、平気で肌着一枚になる男の話なんか、読みたくもない!」
特権階級の人びとは、彼の作品にケチをつけた。
ヴィクトリア時代に青春を送ったイングランドの人びとの多くは、彼の小説を嫌った。彼はイングランド中部のノッティンガム州の殺風景な炭鉱村に炭鉱夫の子として生まれたが、母親の献身的な愛情によって、過酷きわまる場所から抜け出すことができた。この母のおもい出は、生涯ロレンスのこころを温める力となった。
ノッティンガム高校で奨学金を受け、一時期、事務員になったこともあったらしいが、やがてノッティンガム大学に2年間在学し、教師になろうとして教員免許を取得した。彼はイングランドおよびウェルズを通して主席で合格し、1905年から1911年までクロイドンで小学校の教師をし、しだいに労働者階級の意識をもつようになり、ひろく人生を労働者という環境からながめるようになった。特権階級の、いわゆる「優越性」にたいしてひどい憤激をいだくようになる。この激憤は、終生ロレンスにつきまとい、彼の挑発的、挑戦的な態度は大きくふくらんでいった。――そうぼくはおもっている。
♪
きょうは、これまで一度も文章にしたことのないロレンスの話を書いてみたい。
D・H・ロレンスの小説にはじめて触れたのは、ぼくが大学生になってからだった。そのころ、マクミラン書房からだったとおもうが、「D・H・ロレンス全集」(全25巻?)が刊行され、ぼくはそのなかの「息子と恋人(Sons and Lovers)」を読んだ。その間、新潮社からは吉田健一訳が出て、河出書房からは三宅幾三郎・清野暢一郎訳が出て、ぼくは両方とも手に入れて読んだ。二度目に読んだとき、とてつもない感動をおぼえた。
そのころぼくは大学で、ロレンス研究で知られる西村孝次氏に学んでいたので、ロレンスについての講義を聴くことができた。教授から「詩を読みなさい」といわれた。ぼくはロレンスの詩を読んだことはなかった。たとえば、――
おまえは呼び声 おれは答える
おまえは希い おれは満たす
おまえは夜 おれは昼
ほかに何が要ろう? 完全ではないか
まったくじゅうぶんではないか
おまえとおれ
それ以上何が――?
なのにふしぎではないか ふたりがこんなに苦しむのは?
(D・H・ロレンス「ヘネフの近くで」より)
このような詩を読んで、ぼくはロレンスの諸作を読もうと決心した。
それから「死んだ男(The Man Who Died)」を福田恒存訳で読み、「三色すみれ」などのいくつかの詩集を読み、そしていくつかの短編を読みつつ、「虹」、「恋する女たち」、「チャタレー夫人の恋人」と読みすすみ、A・ハクスレーのまとめた「ロレンス書簡集」なども読んだ。
その冒頭にあるA・ハクスレーの「ロレンス論(The Olive Tree D.H.Lawrence)」は、かんたんな序文などではなかった。ボリュームたっぷりな名論文だった。
そして、彼の評論「Ends and Means Goals, Roads and Contemporary」や「Tragedy and the Whole Truth」なども併読し、その専門家である朱牟田夏雄氏や西村孝次氏、松村達雄氏の諸論を読むようになった。
それでもぼくには、D・H・ロレンスのほんとうの姿はわからなかった。
「あのわいせつな、発禁処分をうけたやつの小説だって? あんなもの、どこがいい?」とよく質問を受けたものである。
イギリスでも日本でも、彼の小説はよくないとして発禁書となった。しかも日本では、「チャタレー裁判」にまで発展した。
昭和32年(1957年)3月13日、――この日、伊藤整、小山久二郎のふたりは、高等裁判所大法廷で、「チャタレー夫人の恋人」の日本訳出版頒布に関し、それぞれ罰金10万円、罰金20万円の最終的有罪判決が下された。ここに出てくる小山久二郎というのは、これを出版した小山書店の社長である。
その後、日本文芸家協会は、「チャタレー問題対策委員会」を発足させ、広津和郎、青野季吉、石川達三、西村孝次、中村光夫、亀井勝一郎、高見順、中野重治、福田恒存、舟橋聖一などによる活動がはじまった。
そして1971年、「世界文学全集」(全45巻、新潮社)の1冊として出版されたとき、訳者の伊藤整は、「《チャタレー夫人の恋人》の性描写の特質」と題する小論を発表した。原文対応の精細な分析をおこない、わいせつを目的とした文芸でないことを論じた。
♪
1917年(昭和22年)の木下恵介監督作品の映画「不死鳥」に、田中絹代と佐田啓二のキスシーンが見られるそうだか、ぼくは未見だけれど、どうもあれはガラス越しのキスシーンだったのではないだろうかとおもっている。当時、映画館では男女別々の席に座らされたものである。そんな時代が戦後長くつづいた。
そういう時代に、「チャタレー夫人の恋人」が「わいせつ文書」に見られるというのも、むりからぬこととはいえ、日本ではこれを風俗ととらえ、思想とは考えなかったようだ。
あらためてD・H・ロレンスの作品を読むと、現在のポルノ作品とはまったく異なる次元で書かれていることは明白で、そういうことに目を奪われているかぎり、ロレンス文学の偉大さは何もわからない。
R・A・スコット=ジェイムズの評論「現代英文学の50年」(Fifty-Years of English Literature 1900-1950 英宝社、昭和35年)を読むと、「過去50年間にわたって世界を動乱させてきたさまざまな革命は、すべて一つの革命である。――つまりそれは人類の歴史のほんの一瞬にすぎない」(198ページ)と書かれ、ロレンスの出現は、「イギリス文学を覆いかくしてその性格を根本的な変えてしまうかと一時は思われた」と書かれている。
それほど鮮烈なデビューだったようだ。
♪
――さて、作品について話すまえに、ロレンス自身の物語について少し書いておきたい。
1912年の3月ごろ、つまりロレンスが27歳のころだが、ノッティンガム大学の言語学の教授だったアーネスト・ウィークリーは、妻フリーダとともにひとりの客人を昼食に招いた。
「彼は、若き天才だよ」と、教授はいった。
かつて学生だったロレンスは、ドイツの大学の講師の職に応募する件で教授宅を訪れたのである。ロレンスはノッティンガム大学の授業にはあきあきしていたが、ただひとり尊敬する教授がいた。それがアーネスト・ウィークリー教授だった。そこで、ロレンスは、妻フリーダを知る。
フリーダは貴族の出で、頭脳は明晰、ものいいは臆することなくしゃべる。それと知ったロレンスは、教授は尊敬しているが、彼女には偏見にも近いコンプレックスを抱いた。このときフリーダは一男二女の32歳の母であった。
昼食に入るまえ、フリーダは自分の部屋に彼を招じ入れた。少しおしゃべりすると、ロレンスは激しい口調で、女性呪詛を語りだした。彼女は吃驚(きっきょう)した。気をとりなおして、この「若き天才」のこころのなかに、いまも消えない女の傷痕を見てとると、おだやかに話しはじめた。
ロレンスは何を話したかというと、おざなりな社交辞令にうんざりしていて、貴族然とした女のものいいにむかっ腹を立てていたのだ。まるで母親に楯突くようなものだったかもしれない。
27歳といえば、彼はすでに詩人であり、小説「白孔雀」を出し、「侵入者」を出そうとしていたころのことである。さらに、「息子と恋人」としてやがて完成される自伝小説「ポール・モレル」の執筆と苦闘していたころだった。
フリーダはのちに書いている。
あのとき、「わたしたちはオイディプスの話をした。だが、ことばのなかを理解が躍動して流れた」と書いている。
オイディプス(息子)はそれと知らずに、あろうことかその実母を犯し、みずから破滅していく古代ギリシアの運命悲劇、その話に触れ、フリーダの感じた彼のテーマは、すでにこのときに感じ入ったものだったらしい。
これはのちにフロイドが「オイディプス・コンプレックス」と名づけたものであり、母への愛に固着した性的欲動に走る「息子と恋人」を描いたのは、至極とうぜんのような気がする。
しかし小説のテーマは、母との愛、そしてその愛による呪縛。そこからの遁走を夢見て自由になりたいと願う主人公を描いている。けっきょく母の愛の呪縛から抜け出ることはできなかった。そういう物語である。ロレンスの実像をそのままに描かれている。
すでに、2年まえにロレンスの母は死んでいた。
「あの娘は、男の魂をすすりとって、男のものは何ひとつ残しておこうとしない連中のひとりだよ」(「息子と恋人」)といわせているピューリタン的な、精神的純潔、そして肉体的結合を嫌う女の矛盾する物語のなかで、ロレンス自身の母との過去を利用している。ロレンスにとって「母」は偉大であり、「女」であり、逃げ出したいほどの相手であり、死んでからも追いかけてくる女だった。
それから3日後、
「あなたはイギリス中で一番すばらしい女性です」という、ひと言だけ記した手紙がフリーダの手元にとどく。2度目に会ったときのロレンスを、彼女はこんなふうに書いている。
「――だが、ロレンスはわたしのことを本当に理解していたのだ。最初から彼は鏡を見るようにわたしを見透かしていた。どんなに懸命になってわたしが陽気な装いを保とうとしていたか、それを彼は見ぬいていた」とフリーダは書いている。