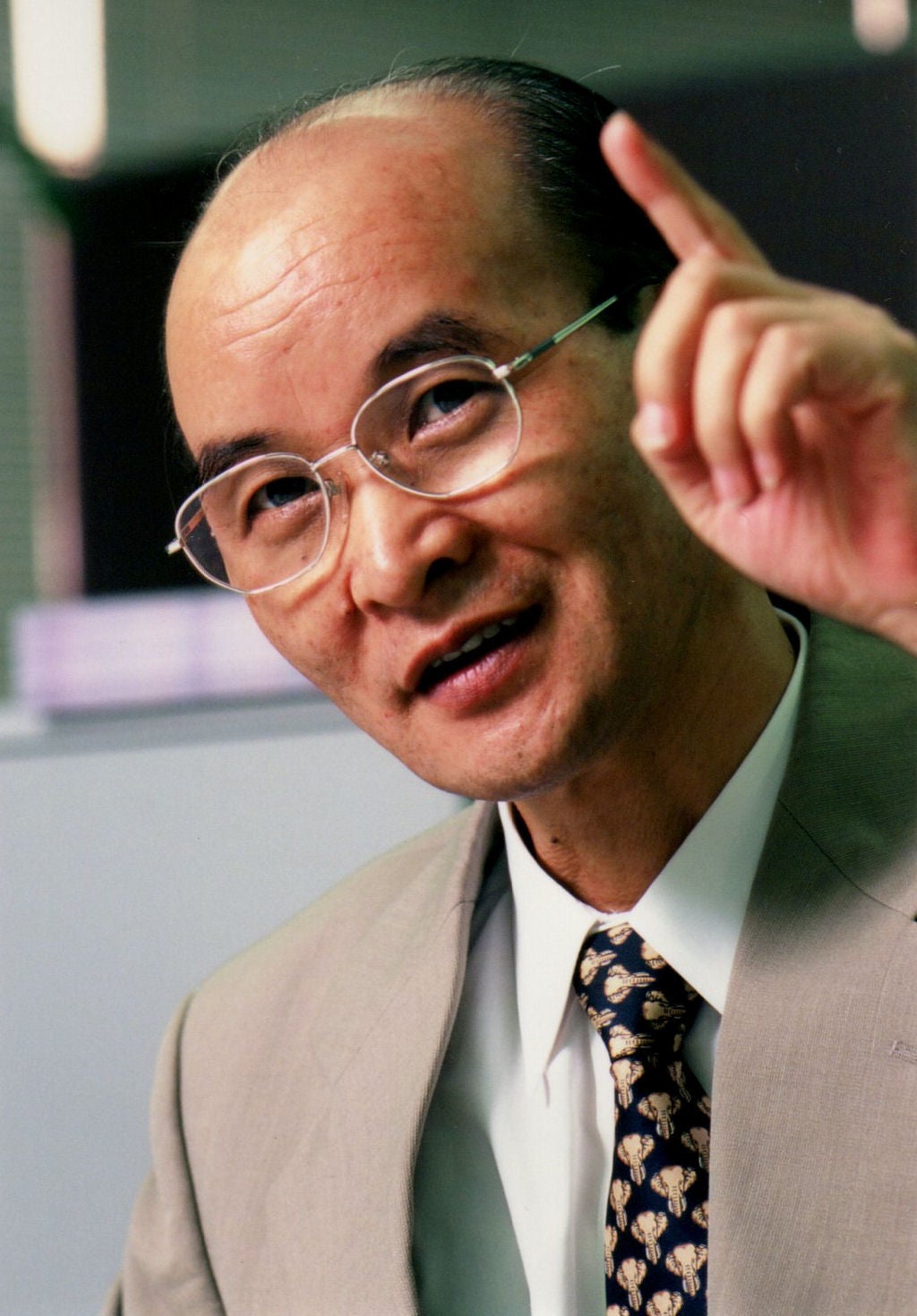Two nationsの英国で発達したことばは身分を表す
イギリスには「ふたつの国民(two nations)」という、古いことばがある。
え? ほんとなの?
と思われるかもしれないけれど、たしかにイギリスはふたつの国民で成り立っている。その話をしてみたい。
国民の90パーセントが中流意識をもっている日本では、ちょっと想像しにくいだろう。この「ふたつの国民(two nations)」ということばは、大英帝国時代の首相だったベンジャミン・ディズリーの文書のなかにあることばで、「何らの交渉も、親愛の情もなく、相互の習慣や思想や感情を知らないふたつの国民」(1845年)なのであると書き記したにはじまる。
イギリスは18世紀後半、産業革命が急ピッチですすんだため、世界の冠たる近代国家の仲間入りを果たし、ポルトガル、スペイン、オランダに次いで名乗りをあげた近代国家である。産業革命で、新興ブルジョアジーとプロレタリアートとのあいだの階級差が一気にひろがった。それ以来イギリスでは、ふたつの国民が別々に共存することになった。
21世紀になったいまでも、中流の人びとと、労働者階級の人びとが、依然として背を向け合って暮らしているのである。ところが、ふたつだけなら、まだわかりやすいのだが、中流階級といっても、その中身はだいたい3つに分かれている。
①上層中流階級、
②中層中流階級、
③下層中流階級、
の3つである。
社会の断面を3つに分けてみても、日本人には何のことかよくわからないかもしれない。けれども、イギリス人は、だれでもその話をしたがる。イギリスの政治家はまずその話を公言する。公言するのだけれど、これをなくそうとは、けっしていわない。
「ああ、そうなんですか」といってみても、日本人にはぜんぜんわからないのである。
学校の、同じミドル・クラスでも、いっぽうはアッパー・ミドル・クラスで、もういっぽうはロウアー・ミドル・クラスを対象とした学校なのである。
多くはワーキング・クラスから区別されている。イギリスは、「世界でもっとも階級に取り憑かれた国民」なのである。そう断言したのは「1984年」の作者ジョージ・オーウェルだった。
ことばの定義をもう少しいうと、「確立した(エスターブリッシュド)ミドル・クラス」と呼ばれている人びと。
「アッパー・ミドル・クラス」とは、「上流社会(polite society)においてアッパー・クラス(upper class)のすぐ下に位置する階級」と書かれている。「ロウアー・ミドル・クラス」は、ワーキング・クラスとおなじ階層に分類されている。――ディヴィッド・キャナダインの「英国上流階級の衰亡」(1990年)という本がくわしい。
ところが、アッパー・クラスの出身でなくても、一代でジェントルマンの階級に到達することは可能だった。
俗に「リスペクタブルrespectable」といわれる人びとは、なかなか日本語になりにくい語で、「尊敬に値する」とか、「礼儀正しい」とか「上品」という意味が込められている語で、そういうニュアンスの人たちも、ジェントルマン階級の一員とみなされた。そのように階級は自分みずからを「確立した(エスターブリッシュド)」存在とおもわれ、尊敬をあつめることができた。
♪
上流階級といっても、イギリスの貴族は国民の0・2パーセントしかいないのだから、タカが知れているとはいえ、この0・2パーセントが国を動かしているのである。――カズオ・イシグロ原作の映画「日の名残り」にもよくあらわれている。
この中流の下には、労働者階級が厳然として存在している。自分はその労働者階級に属していると考えている人は48パーセントもいる。自分は中流だと考えている人は、42パーセント。
つまりブルーカラーの意識を持っている人が、国民の半分弱もいるということである。ご存じのとおり、サッチャー元首相は、下層中流階級に属していた。
彼女の後継者であるジョン・メイジャー元首相は、サーカス芸人の息子だった。その彼が保守党の党首になり、首相にもなっている。2002年までカンタベリー大主教の地位にまでのぼりつめたジョージ・ケアリーもじつは、労働者階級の出である。
♪
いっぽう、労働党政権を率いるトニー・ブレア元首相は、中流階級に育ち、パブリック・スクールからオクスフォード大学を出た人で、組合活動の経験は一度もない。イギリスの政治家たちの歴代首相をながめても、ねじれ現象を起こしている。
イギリスという国は、いまも一等国として、意識の上では世界に君臨している。
そういう国ならではの、礼節に欠ける階級の話が、日常茶飯事に飛び出すのだからおもしろい。あいつらはアッパー・ミドルだとか、やつらはコクニー(cockney)だとかといって、平気で日常会話に登場している。
この階級意識が、互いに融合することは未来永劫けっしてないだろう。まるで、水と油のように自然に2分し合って、けっして溶け込まない。
アメリカにも階級意識というものはあることはあるけれど、ぼくの知るかぎり、彼らは口に出していわない。
中流階級以上と、労働者階級とのあいだには、大きな溝があり、このふたつの階級は、交わろうなんてまったく思っていない。あってもある調査では7パーセントしかないと出ている。上流階級の人間と知り合いになりたいという人が、7パーセントほどいるというわけである。
ところが、上流階級の人間は、だれひとりとして下の人間たちと付き合いたいとは思っていない。そればかりか嫌悪している。
日本ではちょっと考えられないような階級意識が、産業革命以来ずーっと支配し、イギリス国民を2分してきた。イギリス国民の支持政党もまた、升(ます)で測ったように、それぞれの国民の支持を得て2分し合っている。
保守党と労働党の二大政党。――日本でも近年それに近くなってはきたが、イギリスほどではない。イギリスの支持政党の違いは、学校教育の違いを生んできた。ふたつの国民の通う学校が、それぞれ違うのである。
20世紀への転換期は、前世紀の爛熟となれば「ベル・エポック」その退廃とみれば「世紀末」であるけれど、新しい兆候が明らかに見てとれる。夏目金之助(漱石)の場合、日記に「巴里(パリ)の繫華と堕落は驚くべきものなり」と記した5日後に「倫敦(ろんどん)」に到着した。1900年(明治33年)10月28日の夜のことだった。 その滞在は、世紀の変革をはさんだ2年間におよぶ。
1月23日の日記にはこう書かれている。
「昨夜六時半皇女死去す」と書き、そのまま英語でこう書かれていた。
All the town is mourning.The new century fas opened rather inauspiciously ……(新しい世紀は、いささか不吉に始まった)というのは、意味深長である。inauspiciouslyは、不吉で、縁起の悪い、幸先の良くない……という意味。
当時、イギリス経済全体を領導していたのは、綿業、鉄鋼、機械、石炭とともに、海運、保険、金融などである。
日清戦争に勝利した日本は、2億テールの賠償金をイングランド銀行に託してこれからの準備金とした。上海ではP&O社や香港上海銀行などが近代的なビル群を連ねたりした。
見方を変えると、イギリスの中央銀行にとっても日本の金は資産の一部をなした。たしかに近代日本の急迫はめざましく、当時は、戦艦薩摩をはじめとする主力艦の国産のための努力も実っていた。そして超弩級の戦艦への更新、世界の急速な建造競争のただなかにあって、「坂の上」の日本は英語と英国を同時に喜んで受け入れたのである。
日本人は戦って敗けたわけでもないのに、相手国の言語を素直に受け入れている。日本人は、どんな場合も、例外というものがない。好き好んで相手国に学ぶ謙虚さをもっていた。
♪
話を現代に戻そう。
イギリスの義務教育後の進学率は、1980年代でも30パーセント。さらに大学に行くのが、その約20パーセントという国だった。すでに国民の90パーセント以上が高校へ行き、大学進学率もその40パーセントに近づきつつあった日本とはまるで違っている。
学歴に冷淡だったイギリスも、ここ20年ほどで、大卒あたりまえのアメリカや日本に引きずられて、進学率が異常に高くなってきたが日本にはおよばない。
♪
そうはいっても、国民の大多数がふたつの国民に分かれているのが現状である。そのふたつの国民を見分けるのはかんたんで、彼らの読む新聞が違っている。
ちょっと小さいタブロイド版は、労働者が読む新聞と相場が決まっている。日本の場合でいえば、これらの新聞を「大衆紙」といっている。「タイムズ」とか「ガーディアン」のことを「高級紙」といっている。
タブロイド版の多くは、ヌードと犯罪、ゴシップが専門の新聞で、日本でいえば、スポーツ紙レベルということになるだろう。日本でも、かつてはそうだった。読売新聞は、かつて「読売」と呼ばれ、大衆紙としてスタートした。
大衆紙の「サン」の発行部数はおよそ350万部、いっぽう高級紙の「タイムズ」は67万部、「ガーディアン」は40万部(いずれも2002年)である。ここに労働者人口の多さがあらわれている。
♪
日本は、階級なき社会だとよくいわれている。
その証拠に、サラリーマンたちは、朝は日本経済新聞を読み、帰りの電車のなかでは東スポを読んでいるのである。高級紙も大衆紙も読んでいるというわけである。そもそも日本には階級などというものがないのだから、何を読んでもいいわけである。しかし、イギリスの上流階級の人びとは、大衆紙をけっして読まない。むしろ嫌っている。
このふたつの国民は、しゃべることばまで違う。
聞くに堪えないコクニーことばは、住む場所によっても違い、わが国の世代感格差以上にはびこっている。英語には話しことばと、書きことばがある。
日本にもあるけれど、そんなものじゃない。これが英語か? とおもえるほど、解読不可能な言語がまかりとおっている。イギリスへ行くと、クイーンズ・イングリッシュが聴けるとおもったら大間違い。クイーンズ・イングリッシュはロンドンの街を歩いていても、けっして聞くことのできない言語である。
こういう話がある(狩野良規「スクリーンの中に英国が見える」国書刊行会、2005年発行)。
「イギリスの地方へ行って、タクシーの運ちゃんの英語がわかったなんて嘘っぱちもいいところだ」と。当のイギリス人がいうには、
「アメリカ人の発音はどんな方言でもわかる。日本語は、これまで理解できなかったのは奄美大島のお婆ちゃんの日本語だけだ。しかし、イギリスでは隣村に行くと、もう英語がわからない」という。
イギリス人のしゃべる英語が、これまた理解に苦しむことが多い。
多いどころの話じゃない。すべてがそうだ!
まあ、語学は男女の情意投合、とはいかないが、人の情意は知とは違って、気持ちの投合となると、ことばを越えたものが存在する。単なる理屈ではなくなる。
ときどき「ここは、英語を話すイギリスだろ?」とおもいたくなる。トマト(tomato)はここでもトマトというのだが、たいがいの人は「トメイト」と発音するだろう。そういう英語は彼らには通じないのだ。
ゲート(gate)は「ガイト」と発音し、ケーキ(cake)は「カイク」といい、テイク(take)は「ターク」といい、テープ(tape)は「タイプ」という。頭のなかがこんがらかって、自分でも何を話しているのかわからなくなる。これはまた若くて違った世代のことばだ。
それくらい英語は複雑な言語である。ロンドンの旧市街を2ブロックほど歩くと、もうしゃべることばが違うのである。コートのことをトップ・コートといったり、グレート・コートといったり、オーバー・コートといったりする。映画「マイ・フェア・レディ」に登場するヒギンズ教授の論はおもしろい。
自転車のことを「bike」というか、「cycle」というか。
たとえば、ナプキンのことをtable napkinではなくserviette、トイレをlavatoryではなくてtoilet、居間のことをlounge、乗馬をridingと呼び、わざわざriding on horsebackといい、デザートをsweet、ジャムをpreserveと呼んだりしていて、これらはすべてアッパー・クラスでないことを証明している。
♪
階級に取り憑かれた国イギリスでは、ことば遣いをはじめ、あらゆるものに階級があらわれる。
そういえば、1997年8月31日にウェールズ公妃ダイアナ、プリンセス・オブ・ウェールズ(1961年-1997年)がパリで事故死したときの英国国民の哀しみぶりは、国際的にテレビでも報じられて話題になった。「上唇を動かさないstiff upper lip」、つまり何があっても感情をけっして人に見せないイギリス人は、何事も動じないというのが英国人の伝統的な態度だった。
ところが、ダイアナ妃の死が、いままでの無表情のはずの英国人の気持ちを変え、報道テレビカメラの前で声をあげて泣くシーンが大きく写しだされ、英国人が「感情の吐露」をすることに驚きをもって迎えられた。
これは、めずらしいものだった。これを視聴者参加型の「リアリティ・テレビ」(Reality TV)と呼ばれたりし、英国人の階級意識が変化しつつあることを印象づけた。
サッチャーはいきなり政治の話に切り替えたとき、のちにサッチャーの後継者となるメージャー院内幹事はこういった。
「租税を控除することと減税することの違いを、一般大衆が理解しているわけではありません」と。このことばに、サッチャーはすばらしいメージャーの着眼点にこころからの賛意を抱いていた。そこに英国人として、紳士の主人公「ロウアー・ミドル・クラス」たらんとする涙ぐましい努力を見て取ったサッチャーは、メージャーを首相に指名したのは当然だった。