- HUNTER×HUNTER 28 (ジャンプコミックス)/冨樫 義博
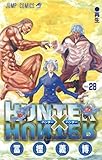
- ¥420
- Amazon.co.jp
- HUNTER×HUNTER 29 (ジャンプコミックス)/冨樫 義博
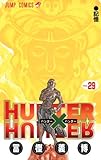
- ¥420
- Amazon.co.jp
いやはや、なんとも、凄絶な展開である。
二ヶ月連続刊行なんて、当日まで信じていなかったけど、それどころか来週から連載も再開するらしい。いったい作者になにが起こったのか・・・。プロなんだから当たり前といえばそうなんだけど、逆に心配である。
僕なんかは、ちょっと前に27巻までを一気に読んだのでまだましだろうけど、ふつうに新刊を追うかたちで読んできたひとでは、たぶん設定とか状況とか、キャラの能力とか、よくわからなくなっているということもじゅうぶんあるんではないだろうか。
作品の表情が作者に帰属するものと考えて読むことは、読者の読み幅みたいなものを制限し、作品が本来もっている価値の大半を損なってしまうが、ここまでくるとついつい作者の天才について考えてしまう。なんというか、こういってはなにかもしれないが、てすさびという感じがするのだ。これは内田樹が『街場のメディア論』で紹介していたはなしだけど、シャーロック・ホームズを書いていたコナン・ドイルは、あんな伝説的名探偵を創出しながら、心霊主義の伝道こそがじぶんに課せられた使命であると信じ、すべての印税をこれに投じていたというし、ニュートンではそれは錬金術だった。そっちのほうが「天職」なのであって、執筆や物理学はいやいやしていたのだ。なんかこのマンガの作者を見ていると(といってもマンガ以外「見る」場所はないので、たんなる想像なんだけど)、このはなしを思い出さずにいられない。
はっきりいって、僕には、まだこの作品を分析するだけの器がない。
僕のばあい、批評は、つねに内的な感情のうごきをよすがにして書かれるもの。だから、その意味で、プロのものとはぜんぜんちがうのだけど(なんの感興もなく読み終えた小説を批評することも不可能ではないだろうけど、たぶんすごくつまらないものになる)、ともかく、この作品を読むときに僕の体内で起こっているなにか爆発みたいなものは、圧倒的なもので、僕の理性が縁取る器から溢れていくような感情の波が、いったい物語のなにを原因にしてもたらされているのか、ぜんぜんつかめないのだ。
いずれにしても、連載が再開されるなら読みたいし、ここまでのぶんをぜんぶ読み返しておいたほうがいいかもしれないなぁ。
今回は同時にワンピース63巻とバクマンも出た。
- ONE PIECE 63 (ジャンプコミックス)/尾田 栄一郎
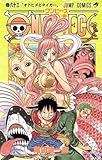
- ¥420
- Amazon.co.jp
- バクマン。 14 (ジャンプコミックス)/小畑 健
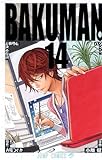
- ¥420
- Amazon.co.jp
どの段階からかわからないが、ワンピースは、ぜんたいの文字量・・・というか絵の細かさも含めると情報量が増加し、読み終えるのにけっこう体力をつかう作品となっていった。それはバクマンもおなじことだ。
で、どちらも、ぱっと開くと、あまりの情報量にうはぁっとなって、ちょっとあとでいいやとなるのだけど、読み始めてみるとやっぱりおもしろいのである。
ワンピースの情報量が増えていったのは、まあしかたないことというか、必然だろう。あれだけキャラが増えて、しかもその造形のどれもが見えないところまで徹底的につくりこまれているのだ。すべてのキャラクターの背後に、彼ら固有の物語が流れている。ここまでポリフォニックなマンガは現在ほかに見られないし、むしろあれだけの並列する物語を余裕をもってひとつの流れのなかにおさめていくのは、ちょっととんでもない技術だとおもう。
というわけで、情報量が増えたことは、キャラ(物語)が増えていったことと一致するわけだけど、ではどうしてキャラがそのように増えていったのかというと、それは、まあくちにしてみれば当然なんだけど、ルフィの海賊としての才能に通じていくのだ。頂上決戦のときに、ミホークだったか誰かが、ルフィの、近くにあるもののぜんぶを瞬時に味方につけていくちからを指摘していたけど、まさにあれなんです。誰もがルフィを求め、また誰もをルフィは求める。そういう構造にあるのだから、物語がここまで分厚くなるのは必然なのです。
バクマンには、ひさしぶりに悪役というか、七峰透という、敵らしい敵が出て来た。が、いかにも現実にいそうな種類の作家であって、なるほどなーという感じだ。
このひとの登場は、「作者とはなにか」という問いにまっすぐにつながっていく。
テクストというものはテクスチャー、織り上げられるものなのであって、たとえば、僕は最初のことばを父や母から学んだし、文体は村上春樹や田中小実昌から学んだし(ぜんぜん似てないとおもうけど)、それを動的に展開していく思考法みたいなものを、竹田青嗣や内田樹やフロイトから学んだ。この「学んだ」を、ぜんぶ「盗んだ」にかえてもまったく同じこと。原理として、僕らはつねに「だれかがしゃべっていたことば」をしゃべっているのであるし、その意味で、「作者」というものは存在しないのである。理屈としてはそうだろう。バルトのテクスト論は、すぐに作品を作者につなげ、作者の思考の結果としてとらえ、彼の意識・無意識を暴いていくという、狭い範囲の分析から批評を解き放った。この方法ぬきで現在の、それじたいで読むことのできる、また価値を帯びる批評はありえなかった。
七峰透の作品は、いってみればテクスト論をうしろだてに、自覚的に「作者」を殺すという手法で書かれたものだ。それでいて現実的な著作権は彼がとるというのがなんともずるがしこいところなのだが、それはともかく、登場する作家の多くはこれに違和感を示す。特に、久しぶりに登場した中井さんのリアクションは明確で、「いやこれは違うだろ・・・」と、そのちがいがどこに返っていくものか説明できないものの、絶望的な表情でつぶやくのである。ここのところが、いかにも漫画家サイドから描かれた漫画という感じだ。
- 街場のメディア論 (光文社新書)/内田 樹

- ¥777
- Amazon.co.jp