■『雨天炎天―ギリシャ・トルコ辺境紀行―』村上春樹 新潮文庫
- 雨天炎天―ギリシャ・トルコ辺境紀行 (新潮文庫)/村上 春樹
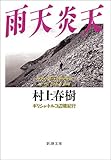
- ¥380
- Amazon.co.jp
「『女』と名のつくものはたとえ動物であろうと入れない、ギリシャ正教の聖地アトス。険しい山道にも、厳しい天候にも、粗食にも負けず、アトスの山中を修道院から修道院へひたすら歩くギリシャ編。一転、若葉マークの四駆を駆って、ボスフェラス海峡を抜け、兵隊と羊と埃がいっぱいのトルコ一周の旅へ――。雨に降られ太陽に焙られ埃にまみれつつ、タフでハードな冒険の旅は続く!」裏表紙から
写真の松村映三が同行した、村上春樹の紀行文。とはいえ、文中の「こんな写真を撮った」という描写通りに写真が挿入されているわけではない。
村上春樹はこれ以外にもいくつか海外旅行記や滞在記を書いているのだけど、どれもたいへんにおもしろい。講談社文庫の『遠い太鼓』などはとても長いのだけど、けっこう短い期間にするする読めてしまったように記憶している。それというのは、もちろん村上春樹の魅力的な語り口があるからでしょう。このひとはわりに冗談がすきなひとというイメージがありますが、決して意地悪なものではない、夏目漱石にも似た誠実なユーモア・センスが、異文化交流のもたらす滑稽さを大真面目に描出し、こころをあたためてくれるのだとおもう。
- 遠い太鼓 (講談社文庫)/村上 春樹

- ¥840
- Amazon.co.jp
- やがて哀しき外国語 (講談社文庫)/村上 春樹

- ¥540
- Amazon.co.jp
『ノルウェイの森』にはこういう場面がある。主人公のワタナベが、寮でお世話になっている天才型永沢さんとその恋人のハツミさんと食事をしているところだ。
「俺とワタナベの似ているところはね、自分のことを他人に理解してほしいと思っていないところなんだ」と永沢さんが言った。「そこが他の連中と違っているところなんだ。他の奴らはみんな自分のことをまわりの人間にわかってほしいと思ってあくせくしてる。でも俺はそうじゃないし、ワタナベもそうじゃない。理解してもらわなくったってかまわないと思っているのさ。自分は自分で、他人は他人だって」
ワタナベはそれに対し次のように反論する。
「僕はそれほど強い人間じゃありませんよ。誰にも理解されなくていいと思っているわけじゃない。理解しあいたいと思う相手だっています。ただそれ以外の人々にはある程度理解されなくても、まあこれは仕方ないだろうと思っているだけです。あきらめてるんです(略)」下巻127-128
- ノルウェイの森 上 (講談社文庫)/村上 春樹

- ¥540
- Amazon.co.jp
- ノルウェイの森 下 (講談社文庫)/村上 春樹

- ¥540
- Amazon.co.jp
僕は外国に出たことがないし、仕事以外で外国人とはなしたこともほとんどないのでなんともわからないが、ことばの通じない、地理も風俗もくわしくないある土地に暮らしてみるというのはどういう動機で、どういう感覚なんだろうとおもう。もちろん、鈍感な僕だって、知り合いがひとりもいない場所に逃げたいとおもうことはある。だけどそれはたんに「どっかに一億円くらい落ちてないかな~」ぐらいの希望であって、深い意味はない。村上春樹は英語がつかえるし、かんたんな現地語も修得して、さらにガイド・ブックなんかも読んで、しっかり準備をしているのだけど(こういうところがいかにもこのひとらしいよなー)、もちろん国内を旅行するのとはわけがちがう。いかに英語がぺらぺらであっても、アメリカやイギリスはどこまでも外国であり、こちらがそれ以外のことばで思考している以上、それはどこまでも「異国」であるはず。僕らは原理的に他者の記憶を体験することはできないが、少なくとも同国人で、同じ言語で思考している(らしい)ひとびとの気持ちを経験的に想像することはべつにむずかしくない。外国に行き、そして獲得されるこの「異国感」ということは、おそらく意図的にこの「経験的推察」を除くことなんではないかとおもう。なんだかさびしいはなしのようだが、これは「私」という単位に還ることなんではないかと僕はおもう。誰もじぶんのことを知らない土地に行きたいという感覚は、たぶん僕たちをとらえる「構造」を振り払って、素っ裸になりたいという衝動からくるんではないでしょうか。村上春樹は臨床心理学の河合隼雄との対談で次のように語っている。
「ぼくは、小説家になるというのは非常に個人的な行為だと思っていたんですよ。みんな自分の好きなものを書いて、それを持っていって売って、おカネをもらって生活する。誰とも付き合わなくていい。ところが、そうじゃないのですね。この世界もまた、日本の社会の縮図なんですね。(略)」
「そういう日本的な土壌の中で小説を書くことが、ぼくはものすごく辛くなったんです。現実的に、いろいろな雑用とかややこしいことが多すぎたこともありますが、集中して仕事をするということがだんだんむずかしくなってきて、とにかく外国に出て小説を書きたいと思って、この間までアメリカにいたわけですが、申し上げたように、やはり全く違う土壌の中に二年、三年といると、考え方、ものの見方がだんだん少しずつ変わってくるのですね(略)」
「日本語でものを書くというのは、結局、思考システムとしては日本語なんです。日本語自体は日本で生み出されたものだから、日本というものと分離不可能なんですね。そしてどう転んでも、やはりぼくは英語で小説は、書けないそれが実感としてひしひしとわかってきた、ということですね」
『村上春樹、河合隼雄に会いにいく』47頁ー48頁
- 村上春樹、河合隼雄に会いにいく (新潮文庫)/河合 隼雄

- ¥460
- Amazon.co.jp
ちょっと逆説的になるけど、ここで村上春樹は、言い方を変えれば、「じぶんが日本語で小説を書いているのだ」ということを再発見するために、外国に出たということにもなる。日本語をつかわないことでじぶんが日本語人だということを確認したわけです。これはとっても興味深い。というのは、逆にいえば、日本にいて、日本語をつかっているうちは、じぶんが日本語人であることに気づけないということなのだから。鋭敏すぎる感覚をもった村上春樹には、日本と日本語の構造的なからまりがたえられず、しかし同時にどこまでも日本人であるという矛盾を抱えていて、そのことがこのひとに外国へのじしんの投げかけをさせて、自己を再規定するのかもしれない。