- ■『いまを生きる/DEAD POETS SOCIETY』
- 監督:ピーター・ウィアー
- 主演:ロビン・ウィリアムズ
- いまを生きる [DVD]
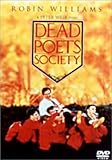
- ¥1,099
- Amazon.co.jp
ヘルマン・ヘッセを読んでいたら猛烈に見たくなったので、レンタルしてきた。
いわゆるお涙ものには僕は強いので、べつに泣いたりとかはないのだけど、やっぱこれはすごいなとおもった。
この『いまを生きる』やヘッセの『車輪の下』、それからエーリッヒ・ケストナーの『飛ぶ教室』のような種類の物語はギムナジウムと呼ばれます。ウィキペディアによると語源は古代ギリシア語のギュムナシオンで、ボクシングなどのジムと由来は同じだそう。エリート志望の子供たちが全寮制の学校に寝泊りして鍛錬のような学習の日々をおくる、そういったシチュエーションの物語を、そう呼ぶわけです。
- 車輪の下で (光文社古典新訳文庫)/ヘッセ

- ¥600
- Amazon.co.jp
- 飛ぶ教室 (光文社古典新訳文庫)/ケストナー

- ¥500
- Amazon.co.jp
こういった設定が物語をつくりやすいのだということは、たぶんあるとおもう。特にヘッセのように実際繊細な少年時代に体験しているばあいは、少年期のどのような思い出もそうであるように、重い意味をもつはずで、こちらの行動や衝動を強権的に抑制する「状況」は、そのうえ少年達の葛藤を生みやすいのだとおもう。
そのような状況に現れる、ロビン・ウィリアムズ演じるキーティングのような型破りな教師は、そりゃ子供たちには刺激的だし、不安定に揺れる青春時代にこんなひとに出会えば影響を受けるのは必然なのである。しかし、この物語が見事なのは、それでも、カルぺ・ディエム=seize the day=今を生きよという魅力的なスローガンの重要を認めながらも、結果としてはキーティングが敗北をするというところだ。
新潮文庫の『いまを生きる』には川本三郎の見事な解説が付されていて、ここにも書かれてあることだが、キーティングは明らかにニールの自殺に責任があるし、性急すぎたのである。キーティングの教えに開眼し、同調したニールは、厳格な父親に隠れてお芝居にうちこみ、主役を獲得する。しかし閉幕とともに父親に連れ去られたニールは、陸軍学校に転校させられることとなり、絶望から彼は拳銃で自殺してしまうのだ。キーティングに同調し、この教師がむかし開催していた「死せる詩人たちの会」を復活させたトッドら他のメンバーたちは、会のこともばれて、学校側からキーティング追放の書類に署名を迫られる。「責任」をキーティングにおしつけ、贖罪の山羊にしてしまおうというわけである。そして、そのことは…責任がキーティングにあるということを完全に否定することができないということが、このおはなしのむずかしいところである。教育には、カリキュラムには意味があったのである。いい大学に入って医者や弁護士になることはとてもすばらしいことなのである。しかし同様にして、そのような抑圧された環境で育ってきたおぼっちゃまたちには特に、じぶんの言葉を獲得し、いま生きているという官能的な実感をその手でつかみとるという生のナマな感触もまた、美しいのである。キーティングは体制のアンチテーゼとして登場した、いわば革命家である。だから、トッドたちには当然魅力的に見えるのだ。この革命に同調するということは、つまりじぶんがおかれている「状況」を全否定することにほかならない。この結末はほとんど必然だったといってもいいのだ。なぜなら、彼らの存在はどこまでもこの「状況」に含まれていることが前提条件だから。キーティングに責任があるというのは、そういう意味だ。理想を追究するあまり、彼はほとんど状況を省みなかった。プリチャードの著した詩の「概論」を破くエピソードが示すように、彼は体制を否定することで、みずからの理想を強調して呈示してみせた。体制のなかで、体制を否定してみせたのだ。破滅は必至だった。
しかし、それでもなおこの物語が美しいのは、ふたたび体制に閉じ込められながらも、少年達が明らかに大切ななにかを獲得し、成長したのだというあたたかな実感があるからだ。キーティングが去っていく場面…。厳格な校長の前で、キーティングの命によりびりびり破いた「概論」を朗読するという、体制の復権をあらわすような局面で、トッドは机のうえにあがって、去り行く「船長」に最大級の敬意を示してみせる。校長の目前でこれをやるというのが以前ならどれだけ勇気のいることだったか。
このキーティングの敗北は、このように考えさせられるのだ。だからこの作品は、青春映画でありながら、子供にモノを教える大人たちこそ観るべき映画だというふうにもいえるとおもう。
