■『「空気」の研究』山本七平 文春文庫
- 「空気」の研究 (文春文庫 (306‐3))/山本 七平
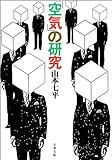
- ¥460
- Amazon.co.jp
「昭和期以前の人びとには『その場の空気に左右される』ことを『恥』と考える一面があった。しかし、現代の日本では“空気”はある種の“絶対権威”のように驚くべき力をふるっている。あらゆる論理や主張を超えて、人びとを拘束するこの怪物の正体を解明し、日本人に独特の伝統的発想、心的秩序、体制を探った名著」裏表紙より
奥付によれば文庫初版は1983年、単行本は昭和52年ということで、いまから三十年も前に書かれた、名著として名高い本書ですが、これが現在でも補足も修正もなく、まるきり新刊のように通用し、読者にショッキングな気付きを与えるということが、まずショッキングである。「そんなの当たり前じゃん」というふうにすらなっていないということなのだから。さきに結論を書いてしまうと、筆者はこの気付き…再把握こそが最優先であるとしている。
「(略)…われわれがもし本当に『進歩』を考えるなら、この点の再把握を出発点とすべきであろう。
(略)。
それだけが、それからの脱却の道である。人は、何かを把握したとき、今まで自己を拘束していたものを逆に拘束し得て、すでに別の位置へと一歩進んでいるのである。人が『空気』を本当に把握し得たとき、その人は空気の拘束から脱却している」あとがきより
もちろん僕たちは、じぶんたちの息づくこの国のこの空間に「空気」という権威的な非存在が居座って、僕たちの言動や心的作用まで支配していることを、知っている。「KY」などという流行語が生まれるくらいであるのだから。だがそれがどんな機構であって、どんなところからどのようにして生まれ出てくるかはわからない。つまり、「空気」について僕らはなんにも知らないのだ。ということは、じぶんたちの状態がいかなるものであるか、地球は丸いのかそれとも平らなのかをわかっていないも同然である。そしてそのこと(「空気」の正体をわかっていないこと)を事実として伝え、論理的にこれこれこうだと説明するのはじつに困難である。なぜなら、「空気」の支配する日本においては特に、「論理的説得」で「心的態度を変え」ることは「不可能と言ってよい」からだ(P216)。空気そのものが空気の看破を妨げるのだ。
「空気」はどのようにして生まれてくるか。筆者は、空間を満たし、我々を拘束する「空気」は、「水」を差されることによって破壊され、雲散霧消するという。「水」とはつまるところ「現実」であり、「通常性」である。しかしこれですらも、じつは「空気」を生み出す温床であって、筆者はこれを日本的な「情況倫理」であると規定し、変形された「日本的儒教」=「父と子の倫理」であるとした。これらのことばの意味はすべて本書を読んでもらうとして(特に孔子の変形に端を発する「父と子の倫理」は必読)、なにしろ「空気」そのものはつねに「水」を差すことで破壊可能なのだが、「水」とは「空気」醸成のもとであり、抜け出たかに見えて、僕らはじつはただ次の空気へと移動するだけだというのだ。
どちらも僕らを規定するものながら、「空気」はえたいのしれないものであるが「情況」は論理的に説明可能だ。しかし情況倫理は「行為」と「個人」が欠落しているという。たとえば、ある情況では許された盗みが、ある情況では許されないばあいがある。悪いのは「盗み」であって、情況次第で変わってしまうということは本来ないはず。また同時に、同じ「情況」でも人によって行動が異なるということも、多く忘れられているという。
「(略)これは自己の意志の否定であり、従って自己の行為への責任の否定である。そのため、この考え方をする者は、同じ情況に置かれても、それへの対応は個人個人でみな違う、その違いは、各個人の自らの意志に基づく決断であることを、絶対に認めようとせず、人間は一定の情況に対して、平等かつ等質に反応するものと規定してしまう」P112
そして、ある絶対者の創出した情況は「空気」を生み出す。
だから、このことの、外側から考えられる解決策というのは、原理的に存在しない。解決不可能なのである。「空気」の外側から「現実」を持ち出して「水」を差しても、結局はそれじたい情況が生んだものであって、情況は「父と子の倫理」のもとに、絶対者として我々を均質に規定し、また「空気」を生成してしまうのだ。こうした動きは僕らの意識の深いところに根付いているため、ほとんど無意識に、本能みたいに行われる。だから筆者は、総体として、事態がどのようなことなのかということの再把握を訴えるのだ。
ちょっとした人間関係でも、「空気」を読まずに好きに生きていくというのは、たいへんにむずかしい。おれはそんなのかんけいない、嫌われようとなんだろうと知ったことかといえるひとはいいが、現実には困難だ。しかしもし僕らが、真に自由を獲得し、創造的に生きようとおもったら、空気に規定されるばかりではいけないのだ。…「現実」が許さないのだと「水」を差されるだろうか?
個人的な実感としては、「KY」ということばの出現が示すように、「空気を読まなければならない空気」といったような強権的な空気には、逆説的みたいだが、違和感を覚えているひとも多いとおもう。というのは、わざわざ空気の読めていないことを指摘し、確認しあうという行為は、もちろん空気を読み損ねてしまう恐怖からきており、ということはすなわちそれは、じぶんが空気を読めていないのではないかという不安感のあらわれだとおもえるからだ。もちろんそれは、それだけ「空気」を尊重していることになるのだが、いっぽうで限界がきてるんじゃないか。
なんにしてもすばらしい論考でした。まだまだ理解しきれていないところも多いですが、これはほんとに再読の価値があると最初に読んでいる時点でおもったし、この文章も書くか迷ったほどだった。日本人論としてこれほど推薦したい本は他にない気がします。僕はたんじゅんな男なので、いい本を読むたびに「これは今年いちばんだ!ぜったいブログでごり押ししよう」とおもうのだけど、これはほんとのほんき。全日本人必読。 このひとの他の日本人論も読んでみたいです。
↓本書の副読本として。
- 「関係の空気」 「場の空気」 (講談社現代新書)/冷泉 彰彦

- ¥756
- Amazon.co.jp
■関連記事
『「関係の空気」「場の空気」』冷泉彰彦
http://ameblo.jp/tsucchini/entry-10054498183.html
※本稿で取り上げられていたテネシー州における「進化論裁判」は、以下の書籍がくわしいです。欧米の歴史的怪奇事件がじつにおもしろおかしく書かれていて、ミステリ・ファンには百科事典的な役割を果たすとおもいます(ちなみに牧逸馬とは、本名長谷川海太郎、長谷川四郎のお兄さんであります)。
- 牧逸馬の世界怪奇実話 (光文社文庫)

- ¥880
- Amazon.co.jp