■『津軽』太宰治 新潮文庫
- 津軽 (新潮文庫)/太宰 治

- ¥420
- Amazon.co.jp
「太宰文学のうちには、旧家に生れた者の暗い宿命がある。古沼のような“家”からどうして脱出するか。さらに自分自身からいかにして逃亡するか。しかしこうした運命を凝視し懐かしく回想するような刹那が、一度彼に訪れた。それは昭和19年、津軽風土記の執筆を依頼され3週間にわたって津軽を旅行したときで、このとき生れた本書は、全作品のなかで特異な位置を占める佳品となった」裏表紙より
太宰治の書くものには二種類ある…。きわめて随筆に近い、暗く息苦しい自責に満ちた私小説的な性格のものと、小説家…“おはなし”のつくりてとしての、類のない、輝かしい才能を全開にしたもの。太宰の自殺後に書かれた坂口安吾の「不良少年とキリスト」(角川文庫版『堕落論』所収)によれば、太宰は「M.C=マイ・コメジアン」を自称していたようで、もしこれが後者の物語作家としての太宰をあらわすのなら、同文中で安吾のいう「フツカヨイ的」というのは前者だろうか。
- 堕落論 新装版 (角川文庫 さ 2-2)/坂口 安吾

- ¥460
- Amazon.co.jp
…というふうにかんたんに分類したいところだけど、これを読んでなんだか混乱してしまった。太宰独特の自虐的ユーモアというのは、太宰文学最大の魅力であり、このひとのすばらしいぶぶんはなんであれすべてこのことに収斂していくんじゃないかとすらおもう。太宰治の自己否定って、逆説的に強烈な自意識過剰からきているとおもうのだけど、あたまのいいひとの宿命といっていいのか、きりがない感じがある。どこまでも素直にというか、単純になりきれず深みにはまっていくようなところがあるのだ。そしてそういったことにも、太宰のようなひとはすぐに自覚的に目覚めてしまい、おもっただけならべつにどうってことないのに、いちいち文章にして公開し、自責的にじぶんをおとしめることで回復して、“小説”を書き…ということをずっとくりかえしているようなイメージがあります。つまり、小説家として構築するフィクションとしての物語世界と、じぶんはほんとうのところこうなのだという告白的な物語が、太宰治という作家の両極端にあって、揺り戻しじゃないけど、反復してお互いを準備しあい、バランスをとっている感じがするのです。そしてこの両端をつなぐ一本があの乾燥した自虐的なユーモア感覚であり、さらにこれを覆うように自責的苦悩があらわれ、逆向きに揺れ戻っていく…。つまり、告白体から小説家として回復する手段というのが、太宰では内容をいちど括弧でくくって客視するユーモアだとおもうわけです。
本書は功成り名遂げた筆者が久しぶりに津軽へ帰郷した際の「旅の印象記」だ。何年ぶりかで太宰を読んだので確信をもって言えるわけではないのだけど、このひとの書いたもののなかではけっこう毛色の変わった作品だとおもう。なんだろう…、いつものように自虐的なユーモアに満ちてはいるのだけど、じつに落ち着いているのだ。もちろんそれは、故郷そのものの風土や、家族親戚、古い友人知人たちがもたらしたこころの平安であるにはちがいないでしょう。もしこの作品が他の小説にはない落ち着きをもっているとすれば、そういった故郷的なものの不在がこれまでの太宰の書いてきたことの原動力だったのかもしれない。故郷をたずね、古い友人と酒を飲み、いろいろ思い返してみるということは、過去がげんに存在していたということを確認しあう行為であり、それは自身の成り立ちをくわしく見直すということにほかならない。そういう意味で、この旅行は一種の自己分析であって、方法的客視とでもいえばいいか、作家としてのその反復から抜け出て、落ち着きとともに広い観察を果たした、珍しい作品ということになるのかもしれない。
僕個人としては、“小説家”の太宰治が書いた作品が好きだ。教科書にのるような有名な作品もいいが、僕のいちばんのオススメは『お伽草紙』です。まあいってしまえば昔話のパロディなのだけど、ほんとうに才能にあふれた、とんでもない作家なのだということがよくわかる。
収録内容の充実という意味もこめて、太宰入門としてオススメなのは新潮文庫の『走れメロス』ですかね。
- お伽草紙 (新潮文庫)/太宰 治
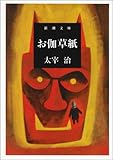
- ¥540
- Amazon.co.jp
- 走れメロス (新潮文庫)/太宰 治

- ¥420
- Amazon.co.jp