◆報告書は参考になるところが満載
338ページにもおよぶ、
スルガ銀行の第三者委員会の報告書について、
お読みなった方もいるでしょうか。
報道やネット記事では、
スルガ銀行内の「パワハラ」「不祥事」ばかりが、
報じられています。
もちろん一つの企業が、
利益を追い求めるばかりに暴走し、
不正に関与および主導していく様子は、
虚しさすら感じます。
また、パワハラと理不尽な指示ばかりだった、
昔のサラリーマン時代の我が事を見ているようで、
ハラハラしてきます。
しかし、それ以外にもこの報告書からは、
学ぶべきところがたくさんあります。
たとえば、この報告書は、
ここまで明かしてもいいのかというほど、
スルガ銀行の内部を公開しています。
人事評価制度はどうなっていたのか?
内部の監査体制はどうなっていたのか?
コンプライアンス体制はどうなっていたのか?
などなど、他の銀行だけでなく、
他の企業が参考になる社外秘が満載です。

◆どんな不動産投資家が破綻しているのか?
そして、
私たち不動産投資家にとっても、
さまざまな気付きがあります。
その中でも、P.143から記載されている、
【「出口から見た気づき」の会議】には、
特に重要な気づきがあります。
この会議開催の目的といきさつは、
次のように記されています。
~ 報告書より一部抜粋 ~
審査部に属す融資管理部は、延滞債権等の管理(督促、法的措置対応等)等を行っており、融資審査を「入口」とすれば、延滞事案の回収等を行う「出口」を見る部署であった。そのため、日常的な業務を通じて、多くの延滞事案に共通する問題点が見えてくることが期待される。
この点に着目した岡野副社長が、融資管理部長と営業企画部長を交えて、「出口から見た気づき」という会議を定例的に開催していた。
~ ここまで ~
融資を実行したのにも関わらず、
延滞(および破綻)してしまったものには、
共通する問題点があるのではないか?
共通する問題点をあぶり出すことができれば、
延滞(および破綻)を減らすことができるのはないか?
と考えて開催された会議だったのです。
これは私たち不動産投資家にとっても、
とても興味深いところです。
それでは、どんな案件が、
延滞(および破綻)しているのでしょうか?
延滞(および破綻)者に共通する問題とは、
なんでしょうか?
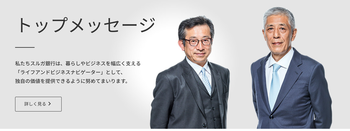
◆デフォルト(返済不能)の共通点
スルガ銀行の第三者委員会の報告書によると、
デフォルト(返済不能)の共通点として、
次のような特徴が報告されています。
1.破綻案件の特徴
・融資実行後1年以内の差し押さえが散見
・デフォルトに至った案件のほぼ全てが架空や偽造
・オーナーの意向では解約できない契約や保証額の随時変更が、
保証会社の一存では変更できるような契約が散見
※保証会社 ≒ 販売会社 or 仲介業者
2.破綻オーナーの特徴
・購入物件も見ずに購入するケースが多い(当事者意識の欠如)
・購入当初からの収支見込が甘い
・賃貸経営のノウハウがない
・キャッシュフローを流用している
・当初から返済余力が僅少
3.破綻物件の特徴
・近隣物件に比較し2割程度高い
・売買価格の妥当性が検証されていない
・販売価格と担保評価額の妥当性が検証されていない
・高値掴みしている
・レントロールがおかしい
4.破綻までの経緯の特徴
・不動産取得税未納での差し押さえ
・入居者チェンジ ⇒ 収支悪化 ⇒ 破綻という構図
・空室や賃料が低下した時には、
即収支がマイナスになる ⇒ 破綻
・不動産を取得さえすれば、永続的に不労所得を得られると勘違い
・修繕費発生に伴う破綻と、空室発生に伴う破綻が多い
・取組時(≒ 所有権が移った時)から家賃金額が大幅に減少
(スルガ銀行では不良債権が急増)
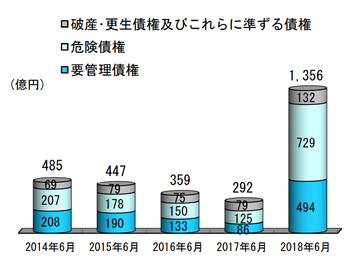
こうした破綻した人の情報というのは、
私たちのところにはほとんど入ってこないので、
とても勉強になります。
しかし、スルガ銀行は、残念ながら、
この【「出口から見た気づき」の会議】の内容が、
活かされることはありませんでした。
そして、かぼちゃの馬車を含むシェアハウス投資物件や、
1棟アパートや1棟マンションへの融資に盲進し、
1兆円を超えるであろうと囁かれるほどの、
不良債権を抱えることとなりました。
私たち不動産投資家は、
ここから何を学べるでしょうか?
スルガ銀行の第三者委員会の報告書を読むことで、
多くの気づきがあると感じた次第です。