こんばんは、年始の挨拶の次が実質的な「ブログ始め」だと思ってますが、マンガの続きを公開することはままなりませんでした。
さらに数日かかるような気がします。
年末年始・・・何やってたんだ!?・・・休んでました。
昨年のメイキングの紹介以来、引き続き広島県産業奨励館を描いております。
この絵を描くためには、まずは往年の写真資料だけを見て描きたかったと思っていました。
そして、実際ここまで往年の写真や復元模型の写真などだけを見て描いています。
そうして描いている限り、この絵は心地よい風景ですし、描いている僕の気持ちも穏やかです。
言うまでもなく、広島県産業奨励館は現在は原爆ドームと呼ばれる遺構として保存されています。
往年の写真だけではわからないところは、被爆後の写真を見て描くこともありますけど、できればやりたくないと思っていました(やや過去形)。
描いてて、まったく穏やかではない気持ちになってきます。
ただし・・・広島県産業奨励館について往年の写真や、少々の文章の資料を拝読するうちに、被爆前の広島県産業奨励館の魅力を強く感じるようになってきています。
実は僕は近代建築が好きなんです。
この建物はチェコの建築家、ヤン・レツルの設計により大正4年(1915年)に作られました。
崩れてしまった今となっては面影を感じるのは難しいのですが「恰幅のよい堂々たる威容」を誇っていたのではないかと感じられます。
真上から見ると真四角ではなくて正面側が広がった台形(というか扇形?)をしています。
これも建物を見た人に、よりダイナミックな「パース感」を感じさせたと思います。
現在ではドーム部分が特に注目されますが、外壁は直線(縦方向)と曲面(横方向)の組み合わせによって構成されており、威厳がありつつも優雅なシルエットだったのではないかと思います。
外壁の装飾は鮮明な資料がなかなかなくて苦労したところですが、セセッション様式と呼ばれるものだそうで、想像よりもずっと細かかったです。
そして、この建物の白眉なところは川辺に正面を向けて「川のある景色との調和」を図っている点だと言われます。
・・・こんな風に広島県産業奨励館を知りながら描いていきますと、被爆後の状態、すなわち原爆ドームの写真の見方も少し変わってきます。
幽霊のようなおどろおどろしい瓦礫・・・というだけではなく、往年の風雅な姿の面影を所々に感じたり、あるいは想像してみようという気にもなります。
この記事には若干ながら原爆ドームの写真(撮影者は僕です)を掲載しましたが、この姿しか知らないという方におかれましては、よろしければ上記のような観点でご覧頂ければ・・・とも思います。
今回、絵にしているセセッション様式の装飾も残っているところがあります。
1階部分の外壁から横幅がわかります。堂々たる恰幅の良いシルエットが想像できませんか?
余談ですが原爆ドーム付近から撮ったと思われる「元安橋」です。
平成に入って掛け替えられたため橋桁の雰囲気は変わってしまったと思われますが、戦前の金属供出前の欄干のデザインはこれに近いものです。
川と一体となった広がりのある町並みを想像します。
<お知らせ>
(1)BOOTHで通信販売をしています!
扱っているのは、只今ブログで掲載誌ている「ヨシノとミコト」の第1部と第2部を収録した同人誌「墜ちたテンシと太陽の物語(1)」です。
(2)Webマンガを公開中です!
BOOTHで取り扱っている「墜ちたテンシと太陽の物語(1)」も含めた過去作品をアメブロ系のサービス「マンガにしてみた」にて公開中です。
こちらは無料で閲覧できます。
もし、冊子として欲しい!ということになりましたら、ぜひBOOTHの通信販売をご利用下さいませ!
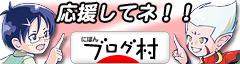
にほんブログ村
ランキングに参加しています、ぜひクリックをお願いします!






