ずばり、新刊は予定を拡張して「ヨシノ編」の第一部を全て収録。A4二つ折り5枚重ね(表紙込み)で本文16ページのトリュフ・ラボ史上最大規模のコピー誌を・・・やれたらイイネ!っと思ってます。
そうなると、結構充実した頒布物になるでしょう。
問題は・・・第一部の原稿がまだ上がってないことです(4コマをあと2本!!)
※なお、さすがにコストがかかるので、申し訳ないのですが一冊100円の予価を考えております。
さて、今回のブログ記事の本題はそのことじゃなくてイベントレポートです。
去る4月16日に東京都千代田区の明治大学で「おざわゆき、こうの史代トークイベント『はだしのゲン』をたのしむ」が行われました。
僕は拝聴させて頂きました。
↑明治大学リバティータワー
会場はこの建物の15階の大学の普通の講義室でした
※このイベントは主催者から写真OK!、ツイートOK!とアナウンスされているのですが、この記事の写真には著作権、肖像権、来場者や僕自身のプライバシーに十分配慮して画像を加工したところがあります。ご了承ください。
こうの史代さん、おざわゆきさんは共に漫画家です。
ご存知の方には説明する必要もないのですが、
こうの史代さんは「夕凪の街、桜の国」、また今秋にはアニメ映画が公開予定の「この世界の片隅で」という、それぞれ太平洋戦争時に関わりのある広島と呉を舞台にした作品を執筆されています。
また、おざわゆきさんはお父様のシベリア抑留の体験談を元に「凍りの掌」、お母様の名古屋空襲の体験談を元に「あとかたの街」という作品を執筆されてます。
(ちなみに僕は全て読了済みです(^^))
トークイベントはタイトルが"「はだしのゲン」をたのしむ"という、ちょっと驚きのテーマでした。
また、こうのさんとおざわさんがそれぞれの作品について語る内容もありました。
本当に良いお話だったのですが、ブログではエッセンス的に2~3点の観点に絞ってご紹介します。
(1)はだしのゲンは実はマンガとして面白い
このトークイベントのメインテーマなんですが、眼から鱗でした。
はだしのゲンをご存じの方は多いと思いますが、全部通して読んだ人は、あまり多くないみたいですね。
僕も2巻(一番怖いところ)まで読んでギブアップしてしまった一人です。
でも、実は6巻以降は良い青春モノのマンガとして面白い。
ゲンの性格がまっすぐ過ぎて「とんでもないこと」をしばしばやる、そこにツッコミと笑いがあるんだそうです。
イベントではいくつかのシーンがスクリーンで紹介されましたが、なるほど、面白いです。
そして、はだしのゲンが、今日まで長きに渡って支持されている理由の一つに、作品のユーモアがあるのではないか?というお話でした。
はだしのゲンには、あまりにも悲惨なことがたくさん描かれていますが、それだけだと読者は参ってしまったかもしれない。読者層である子供に受け入れられるように、匠みに「面白さ」も盛り込んだ結果、長く受け入れられ、そして原爆の悲惨さを伝える作品の筆頭になったということです。
↑OSがXPじゃないか!?・・・というツッコミは野暮としまして(^^;)
プロジェクターで話題になっている作品のページを表示してくれるので
とてもわかり易かったです。
(2)戦争で怖いのは爆弾より人間関係かもしれない
戦争では当然、攻撃されて自身や肉親の命が奪われる、身体や財産を損なう恐怖があるのですが、もっと怖いのは「人間関係」ではないか?ということが話題になりました。
具体的には「はだしのゲン」ではゲンの家族が「非国民」として迫害にあっているところです。被爆後の陰惨な描写はありませんが、描かれていることは爆弾よりももっと恐ろしいことではないか?という指摘でした。
おざわゆきさんの作品(あとかたの街)でも主人公の父親に「男の子供」がいないため、肩身の狭い思いをするなど、ギスギスした人間関係が描かれています。
人間関係に起因する戦争の恐ろしさ・・・僕も意識はしていたのですが、認識のユルさを思い知った感じがします。
(3)戦争漫画を描くモチベーション
イベントの最後で質問コーナーが設けられまして、「どのような動機(使命感)やモチベーションで描かれたのか?」という質問がありました。
それに対する、こうの史代さんの回答が大変印象的でしたので最後に要約をご紹介します。
「実は戦争漫画は描きたいと思ってなかったし、描いてて辛かったが義務感(あるいは使命感)があった。
それは手塚マンガから続く『戦争』をテーマにした作品を作るという伝統の継承である。
この中(聴衆)でマンガを描く方がいたら、ぜひ戦争を題材にした作品に挑戦してみてください。いろいろ『変わりますよ』」
このご回答は僕にとってはとても励みになりました。
イベントレポートは以上です。
最後にお断りさせていただきたいことがあります。
この記事は僕の記憶とメモを元に執筆しました。
解釈の間違いや記憶違いがあり、誤ったことを記してしまっている可能性があります。
それらはどうかご容赦頂きたいということ、また、間違いにお気づきになりましたら、ご面倒でなければコメント欄などでご指摘頂ければありがたいです。
ここまでお読み頂きありがとうございました。
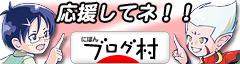
にほんブログ村
ランキングに参加しています、ぜひクリックをお願いします!!


