今回はデンマーク特有の言葉「ヒュッゲ / hygge」に
インスピレーションを受けて
「幸せって?」
を探ってみたいと思います。
北欧エッセイ第3回目。
後半スタートです。
by sen
【北欧エッセイ】バックナンバー
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
ヒュッゲの心、豊かな時間と人間関係
何はともあれキャンドルに火を
前編でご紹介したベストセラー『ヒュッゲ365日「シンプルな幸せ」の作り方』によると、デンマーク人が「ヒュッゲだなあ」と感じるにはそれなりの条件があるそうです。いくつかある中で、ここでは上位の2つを取り上げてみたいと思います。
まずは、キャンドルと照明。
デンマーク人のキャンドル好きは有名で、1人あたりの年間消費量は約6キロだそうです。そもそもヨーロッパ人は蛍光灯をほとんど使用せず、少し暗くても温かみのある照明を好みます。これに輪をかけて照明にこだわるのがデンマーク人。ルイス・ポールセンやヴェルナー・パントンなどのデザイナーの名前を聞いた方も多いと思います。
キャンドルや白熱灯(近頃は白熱灯のような明かりのLEDが主流)を好む文化は北欧の冬と関係がありそうです。夏場は夜の11時ぐらいまで辺りが明るく、朝は4時ごろから空が白むのでほとんど照明を必要としません。なので、あたたかくやわらかい明かりへのこだわりは、ともすると気分が沈みがちな暗く長い冬に発揮されます。ほっこりゆったり過ごすための工夫なのでしょう。
さらに、ろうそくの炎には 1/f ゆらぎの効果があることで知られています。これは人間の心拍や小川のせせらぎなどと同じで、いわゆるリラックス効果や癒し効果があります。ゆらゆら揺れるろうそくの炎を何気なしに眺めているだけで心が落ち着いてくるのはそのためです。
蛍光灯では決して醸し出せない、ゆったりとした時間の流れを感じられる空間がヒュッゲへの第一歩なのです。
ヒュッゲとホットドリンクの関係
そして、キャンドルと同じぐらい欠かせないアイテムがホットドリンクです。
コーヒー、紅茶、ココア、ホットワインなど、その時の気分やゲストの雰囲気で飲みものは変わってくるでしょうが、一般的にデンマーク人はコーヒが大好きです。
どれぐらい好きかというと、この事実には皆さんも驚かれることでしょう。
デンマーク人のコーヒー消費量は世界4位。さらに面白いことに、コーヒーの消費量の世界トップ10の中に北欧諸国がもれなく入っています。2018年1月のworldatlas.comの記事によると、1位はフィンランド、2位はノルウェー、3位はアイスランドで4位がデンマーク。スウェーデンは6位だそうです。
これほど上位に北欧の国々が入っていると、照明同様、北欧の気候が関係しているのかなと考えたくもなります。寒くて暗くて長い冬だからこそ、キャンドルを灯したゆったりした空間で、ホットドリンクを片手にのんびり過ごす。これは一つの時間の楽しみ方と言えそうです。
試しにインスタグラムで「#hygge」で検索してみると、コーヒーの画像がたくさんアップされています。ホットドリンクの中でも特にコーヒーはただ単に美味しい飲みものというばかりではなく、ライフスタイルを演出する大きな役割を担っています。
イッタラ(iitala)のキャンドルホルダーBallo
廃盤のため今では蚤の市やヴィンテージショップでしか出会えません。
火を灯すと下に光の輪ができます。
いつの時代も人と人を繋いできたコーヒー
代表的なホットドリンクといえばコーヒー、紅茶、ココア。
どれも、もともとヨーロッパにあったものではありません。貿易が盛んに行われた大航海時代にもたらされたものでした。コーヒーと紅茶はオリエント(東洋)から、ココアはメキシコからもたらされ、刺激が強く希少であったことから最初は薬として薬局で売られていました。
薬としてではなく飲料としてこれらのエキゾチックな飲みものが受け入れられようになったのは、フランス王室で流行したことがきっかけでした。その後、各国の王室へと広まりました。ココアはほかのふたつに比べて高価だっため上流階級に限定されたようですが、紅茶とコーヒーは徐々に大衆化しヨーロッパ全土に浸透していきました。
とはいえ、今のように家庭で日常的に飲まれるということはなく、人々はコーヒーハウスに足を運びました。例えばパリに最初のコーヒーハウスが現れたのは1643年のことで、1716年には約300軒に増え、一方、同じ頃のロンドンには約2000軒もあったそうで、コーヒーハウスの目覚ましい発展がうかがい知れますね。
コーヒーハウスがどんな場所だったかというと、壁は鏡張りで天井からはクリスタルのシャンデリアが垂れ下がり、大理石のテーブルが置かれていました。コーヒー、紅茶、ココアのほかにレモネードやシャーベットなどが出され、さまざまな人たちが交流する社交の場としてたいへん人気がありました。のちに隆盛したカフェからフランス革命が始まったといわれる背景はここにあります。
しかし、この時代は女性と男性が平等ではなかった時代です。女性がコーヒーハウスに出入りすることは望ましいとはされていませんでした。コーヒーハウスに女性の姿が見られるようになったのは19世紀に入ってから。その代わり、女性たちはサロンを開きコーヒーや紅茶でおもてなしをするという独自の文化を築いていきました。コーヒーハウスが大衆的であるならば、サロンは限定的で私的な社交の場でした。
このように歴史的に見ると、ホットドリンクが東洋と西洋を結び、さらに人と人を結んできたことがよく分かります。人の集まるところにはホットドリンクがあり、ホットドリンクのあるところには人がいる。
人と人のふれあいを大事にするヒュッゲの精神にホットドリンクが欠かせないのも納得いくというものです。
キャンドルが日常的な存在でなくても
気が向いた時にそっと火を灯してみてください。
ヒュッゲな時間をより豊かにするカップの選び方
ヨーロッパ人がコーヒーなどの新しい飲みものを生活に取り入れるにあたり工夫を凝らしたのがカップやポットなどの食器です。最初の頃はビールや水用に使っていた金属製のマグで飲んでいましたが、次第に、熱伝導率が低くクリーニングのしやすい陶磁器が好まれるようになりました。貿易が盛んになり中国や日本から陶磁器が大量に入ってくるようになったことも大きかったようです。日本の柿右衛門や伊万里焼の人気は当時から高かったそうです。
日本や中国からもたされた茶碗は持ち手のないボウル型でした。私たちが普段から煎茶や抹茶をいただく時の湯のみや茶碗を思い出してください。それを改良して持ち手をつけたり、形を変えていったのがヨーロッパ人です。コーヒーカップは口の狭いスラッとした形になりましり、ティーカップは飲み口の広く浅いタイプへと変容をとげました。
人と人の交流の中にある飲みものだからこそ、食器にも多大な配慮がされたのでしょう。ティーセットやコーヒーセットにさまざまな趣向が凝らされてきた過程を見ると、もっと美味しく飲むには、もっと和やかな場を作るためには、という精神的な豊かさを求める人間の心の動きが見えてくるようです。これは現代を生きる私たちも受け継いでいきたい心配りですね。
ゲフレ(Gefle)社のアグネッタ(Agneta)は小ぶりで可愛いシリーズ。
ヴィンテージ感たっぷりのデザインです。
古いものが好きな人はアンティークやヴィンテージのカップで飲みながら、カップが語り始める物語に耳を澄ませるのもいいでしょう。ひと目惚れした現代作家のカップだったり、旅行先で見つけたカップだったら、その時の高揚感が加わってさらに楽しいコーヒータイムになるでしょう。友人や家族からもらったり受け継いだカップだったら、その人のことを思い出したり、記念となるような出来事を思い出すことで、心はもっと温かくなるでしょう。
ホットドリンクが人と人を繫ぐならば、カップは人ともの、そして過去や想いまでをも繫いでくれる貴重な存在です。ですから、カップを選ぶ時は何気なく選ぶのではなく、意識的に選びたいと思います。
もっと言えば、1客だけでなく、最低2客は揃えたいとも思います。お客さんや家族と同じカップで飲めたなら、共有するものが増えるぶん、繋がりをより感じることができるでしょう。こうして選んだカップで飲むと、居心地のよい空間はさらに居心地がよくなり、美味しいコーヒーはより深い味わいとなるでしょう。また、相手の気持ちを和らげ、より良い関係を築くきっかけにもなるかもしれません。
たとえ、お客さんのいないひとりの時間だったとしても、もてなす相手は自分です。自分とのより良い関係を作ることだって、少し意識をするだけで簡単にできると思うのです。
こう考えると、幸せな人生とは幸せだと思える時間がどれだけ多いか、ということなのではないかと気づきます。そして、幸せな時間とは与えられるものではなく、自ら意識して作り出すものなのだということに気づきます。「ヒュッゲ」という言葉が教えてくれるのは、幸せな時間を持つことは難しいことではなくて、ちょっとした心構えで今すぐにでも作り出せるということ。自分とのふれあい、他人とのふれあいを大事にすることが、幸せな時間というキャンドルに火を灯すための最初に取るべき行動なのかもしれません。
丹下 翆 / Sen Tange
参照資料
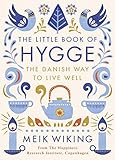 |
The Little Book of Hygge: The Danish Way to Liv...
1,163円
Amazon |
Top 10 Coffee Consuming Nations
https://www.worldatlas.com/articles/top-10-coffee-consuming-nations.html
"Kaffe, Te og Chokolade", Flora Danica og det Danske Hof (1990)
丹下 翆 / Sen Tange プロフィール
2003年に渡欧し、その間ドイツ、スイス、デンマークに暮らしました。現在はデンマーク在住5年目。第3外国語になるデンマーク語を勉強しながら、日本語、英語、ドイツ語ももっと磨かなくては〜と思っているところです。ようやくデンマークの生活を楽しみつつある今日この頃、北欧エッセイをスタートしました。津田塾大学卒、ドイツマインツ大学博士課程中退の文筆活動が大好きなフリーランスライター&翻訳者。2016年11月からぺんみん倶楽部のヴィンテージ雑貨買い付け&北欧文化研究を担当しつつ、素敵な生き方を探っています。




