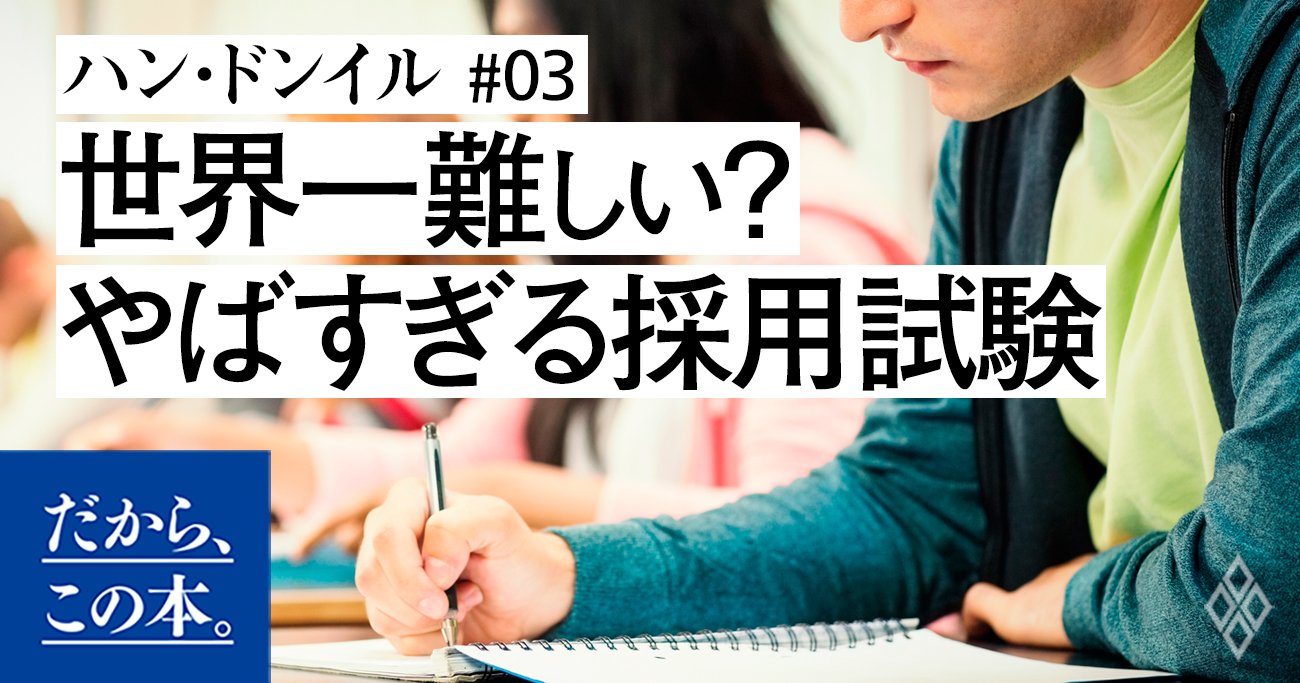HMVの著者紹介をコピペしておく: 韓国人初、東アジア初のロタ・ロマーナ(バチカン裁判所)の弁護士。ロタ・ロマーナが設立されて以来、700年の歴史上、930番目に宣誓した弁護人。2001年にローマに留学し、法王庁立ラテラノ大学で2003年に教会法学修士号を最優秀で修了、2004年には同大学院で教会法学博士号をを最優秀で取得。韓国とローマを行き来しながらイタリア法務法人で働き、その傍ら、西江大学でラテン語の講義を担当した。彼のラテン語講義は、他校の学生や教授、一般人まで聴講に訪れ、最高の名講義と評価され、教室は超満員であった。
こういう天才の本、字も大きく、本村先生が監訳されている。しかも35万部というベストセラー、読むしかないでしょう。「学問とは、その知の窓から人間と人生を見つめること」、ラテン語の勉強は叡智にふれる営み、ラテン語は叡智の貯蔵庫。「人は教えている間に、学ぶ Homines, dum docent, discunt」= 啐啄同時。
大学生はまだ無知な子供であり、彼らを相手に平易に話すこの先生の講義を聴いた気分であった。古代ローマについての部分は少し物足りない。また、この教授もやはり、反日教育の洗脳を受けていることをしみじみと感じた。残念である。
Lectio I : 胸に秘めた偉大なる幼稚さ Magna puerilitas quae est in me.
『いまを生きる』という映画の中のせりふ「Carpe diem」。キケロがアントニウスに言った言葉: Non tam praeclarum est scire Latine quam turpe nescire. (純粋なラテン語がてせきることがすばらしいというよりは、できないことがみっともないのである。) ラテン語の勉強は頭脳を活性化させ、思考体系を広げてくれる。学びには終わりがない。イタリアではmaturità という高校卒業資格に合格し、diploma (卒業証書)をもらわなければ大学に進学できない。大学の卒業は容易ではない。
Lectio II : 最初の授業は休講します Prima Schola alba est.
学問とは「人間と世界を見つめる枠組み」をつくる作業。頭の中に本棚をつくる作業。自分の人生をどう生きるかという省察が講義の最終目的である。Nolite timere! (恐れるな) 古代ローマの教育制度: 小学校 ludus parvorum puerorum / 中学校 Litterarum ludus / 高校 ingenuarum litterarum ludus。5世紀〜カトリック教会の公教育: 初等教育 schola parochialis / 司教座附属学校(神学校) Schola episcopalis o cathedralis: schola minor e schola maior / 修道院が経営する学校 schola monachialia / 貴族や宮廷人の子弟のための学校 Schola palatina。
休講となったらやるべきことは"陽炎"を見つめること。
Lectio III : ラテン語の品格 De Elegantiis Linguae Latinae.
否定の副詞 no non などは「夜に流れる水の曖昧さ」印欧祖語の水 na から生じた。エジプトの象形文字も否定は水。ラテン語は印欧語族の影響を受けている。
母親という言葉は、ほぼすべての言語に ma という音が入っている。M の音価から「人間の生命と関わる人」という母という言葉が派生した。
イタリア語の哲学 filosofia はピュタゴラスに由来し、そのピュタゴラスも、プラトンやストア派の思想もやはりインドの思想に影響を受けた。
ラテン語はルター登場以降衰退したが、ロレンツォ・ヴァッラは『ラテン語の典雅 Elegantiarum libri sex (i sei libri sull'"eleganza" della lingua latina)』を上梓した[コンスタンティヌス帝の寄進状の方が有名かも]。自分の考えを表現するとは、他人の考えを理解するということ。ラテン語は相手についての尊重や配慮、公平性をもち、それを使う人たちの思想と態度・行動の拠り所となった。なので、正しいコミュニケーションに適した言語である。
Lectio IV : 私たちは学校のためではなく、人生のために学ぶ Non Scholae sed viate discimus.
言語は勉強できない。たゆまぬ習慣により身につけるもの。だがラテン語を聞く機会は少ない。ラテン語の発音には二つある: ローマ式(スコラ発音、教会発音 pronuntiatio scholae o Latinitas scholastica)と、古典式(エラスムスの文献『正しいラテン語およびギリシア語の発音に関する問答』に準拠す)。英・米・独系学者は古典式、伊・西系学者はローマ式に発音する傾向がある。勉強して知識人になっても、その知識を人のために使えなければ知性のある人とは言えない。
Lectio V : 長所と短所 Defectus et meritum.
それぞれの語源: de + 動詞facio (不足している)/ 動詞 mereo(価値がある)。どんな人間にも神に見返りを要求する資格はないということも meritum。
捨てる勇気 Postquam nave flumen transiit, navis relinquenda est in flumine.
人生とは絶えず、自分の中の meritum と defectus を自問し、選択して捨てること。
Lectio VI : ひとりひとりの"スムマ・クム・ラウデ" Summa cum laude pro se quisque.
Summa cum laude とは西欧の大学の卒業証書で最優秀を表すラテン語。次が Magna cum laude、Cum laude、Beneとあり、すべての評価が肯定的で、可能性を否定ぜす、枠を残しておく絶対評価である。
ヨーロッパ言語は、冠詞の登場により、名詞の性と数を示すことができるようになり、前置詞とともに使うことで、名詞の格変化をさせなくてもよくなった。
ラファエッロの天使[智天使ケルビム]像で有名な「システィーナの聖母」にある緑の緞帳は、シナゴーグの Torah(モーセ五書)を保管する場所にかけられているもので、それが開き、神秘つまり神が顕現したことを示す[このような絵解きは初耳だ! 右は聖女バルバラ]。
Lectio VII : 私は勉強する労働者です Ego sum operarius studens.
中世の三学四科: 文法学、論理学、修辞学、算術、幾何学、音楽、天文学。命題をつくり、論理を介してそれにアプローチして問題解決へ至るという、一種の自己表現の訓練である。自分のもつ可能性に目を向け、より上を目指すことが謙虚な姿勢。
ラテン語の"習慣"は habitus、動詞は habeo、その語源は修道衣。
自分にできることとできないことを区別するのが大切。Non efficitur ut nunc student multum, sed postea ad effectum veniet. (懸命に勉強した結果が今現れずとも、いつかは現れる) 「自分を哀れむことを知らない人間ほど哀れなものはない」(アウグスティヌス)=自らを知り、ねぎらうことで人は成熟する。
Lectio VIII : カエサルのものはカエサルに、神のものは神に返しなさい Quae sunt Caesarius Caesari et quae sunt Dei Dio.
キリスト教の話は西欧文化をひもとくために欠かせぬ手がかりである。聖パウロがローマの信徒に宛てた手紙の話。神への信仰と神の恵みにより、人が罪から離れて義と認められる。この信仰はユダヤ教とキリスト教の障壁をなくす神学の原理である、と述べた。キリスト教は「すべての人は同一の道徳的地位をもつ」とし、すべての人が平等であるとした(ユダヤ教の伝統をキリスト教が継承した点)。この『ローマ書』における終末論: イエスの中で未来が実現されるとする。
『ローマ書』13章「クリスチャンと権威」: 人はみな権威に従うべき。おおよそ存在している権威はかべて神によって立てられたものだから。[今では?である。]
Reddite igitur quae sunt Caesaris Caesari et quae sunt Dei Deo.(ヨハネ以外の全福音書に書かれている、パリサイ人とヘロデ党員の納税の可否に対するイエスの言葉で、古くからある政教一致を破壊する要素をはらんでいる。政教分離、"二重の忠誠"の始まりである。クリスチャンは、地上と天上、二つの都市に属す市民である。)
Lectio IX : たとえ神がいなくとも Etsi Deus non daretur.
キケロは、人間の"批判的に思考できる能力"に価値を認めていた。人間と神の最初の結びつきは理性によるそれである。
国際法を打ち立てた法学者グローティウスは、Etsi Deus non daretur という前提を提示し、神の存在を排除し、人間の純粋理性による法、哲学、倫理を述べた。『戦争と平和の法』で、神の意志と人間の意志を区別したのは、4〜5世紀のアレクサンドリアにおける学者ヒュパティアであった。
時代を追い、権利に関する問題は、信教の自由、良心の問題であると自覚するようになったが、イスラム教の国々は、イスラム教を国是として、政教一致体制である。
聖書は弟子たちによる授業ノートのようなものだと言える。
Lectio X : 与えよ、さらば与えられん Do ut des.
前91年、古代ローマにて同盟市戦争が起き、イタリアの同盟市は自治都市 Munipicia civium Romanorum となり、市民にローマ市民権 cīvis rōmānus が与えられた。相互主義。
今日の国際社会では、プーチンやトランプなど、自国以外には何が起きてもかまわないと考える傾向が生まれ、西欧の極右政党はグローバル政策の失敗を宣言し、反移民政策やEU脱退を唱える傾向にあり、相互主義の伝統は揺らいでいる。[この著者の日本による朝鮮植民地化が Do ut des でなかったという考え方には同意できない。日本は朝鮮の近代化に必要な様々なインフラを建設し、教育を広め、福利衛生の観念を植え付けたはずだ。やはり韓国の教育が悪いのだろう。]
Lectio XI : 時間は最も優れた裁判官である Tempus est optimus iudex.
hic et nunc(今、ここで)。
beatitudo(態度や心のもちように応じて幸せになれる)。む
Lectio XII : すべての動物は性交後にゆううつになる Post coitum omne animal triste est.
このフレーズは意味というよりも単語と文法の説明のためのもの。
情熱的に望んだ瞬間が一気に過ぎ去ると、人間は虚無感を覚えるものである。そして、成し遂げた後でこそ、自分の望みはもっと別のものだったとわかる。
Lectio XIII : あなたが元気なら、よかったです。私は元気です Si vales, bene est, ego valeo.
『されど夢見る権利』という著者の著作を読んだ子たちのいる少年院から講演に招かれた。講師からのメッセージ: So vales, bene est; ego valeo. (生徒たちが元気ならば私も元気だ)。これは手紙の書き出しの文句。S.V.B.E.E.V.と略した。ローマ人のあいさつは Salve!/ Ave! 複数だと Salvete! アヴェ・マリアは「ごきげんよう、マリア」。さようならは Vale、複数にはValete. 手紙の挨拶文は、Salutem dicit. (S.D.) 手紙の末尾には、Vale/ cura ut valeas. (お元気でさようなら)。
ローマ人は手紙を受け取って読んだ時点にあわせて時制、時間副詞を用いた。
hoide 今日 → eo die あの日
heri 昨日 → pridie 前日に
cras 明日 → postridie, postero die 翌日に
nunc 今 → tum その時に
adhuc 今まで → ad id tempus そのときまで
古代ローマ時代の郵便制度は執政官の監督下にあった軍事事項。運ぶ馬を交替する場所を statio と言った。ローマからパリまで要2日。一般人は飛脚 cursor tabellarius を使ったが高額であった。
Lectio XIV : 今日は私へ、明日はあなたへ Hodie mihi, Cras tibi.
古代ローマの葬儀: 葬儀業者 pollinctor 。死者の口にコインを入れる。埋葬は郊外の共同墓地に。その石碑にある言葉: Hodie mihi, Cras tibi. (他人の死を通して、自らの死を考えよ、という意味)。人間は死後、他者に記憶されて存在する。
Si vis vitam, para mortem.(生を欲さば、死への備えをせよ)
Lectio XV : 今日を楽しみなさい Carpe diem.
再び、映画『いまを生きる』の話。アイビーリーグは、ハーバード、イェールなど、北米東部のエリート大学の総称。Carpe diem はホラティウスが書いた農業詩の中にある言葉: 明日ではなく、今日のうちに摘め。
Lectio XVI : ローマ人の悪口 Improperia Romanorum.
筆者は、ローマの S. Anselmo 教会の図書館によく通っていた。Stultus es! (馬鹿野郎)、 stupido の語源。ラテン語のわるくちいろいろ:
Sane ineptus es! (おまえは本当にバカだ)
Abi pedicatum! (くたばれ)
Mentula es! (FUCK)
Sane coleus es! (ふざけるな!)
Sacer esto! (呪ってやる); sacer は神聖な、呪われた、という二つの意味がある。Tempus fugit, amor manet. (時が去ろうとも、愛は残る)
Lectio XVII : ローマ人の年齢 Aetates Romanorum.
ラテン語はフラットな言語体系。
infans (話のできない乳幼児)、parvulus (小児)、puer (少年)、puella (少女)、adulescens (思春期の青少年)、iuvenis (若者: 20〜45歳)、vir (成人男性: 60歳未満)、 senex (高齢者)。ローマ法では男子14歳、女子12歳で結婚できたが、成人は25歳以上であった。そのため、イタリア人には年齢に対する寛大さがある。
Lectio XVIII : ローマ人の食事 Cibi Romanorum.
朝食 ientaculum / 昼食 prandium / 夕食 mensae primae + mesae secundae (デザート)。De gustibus non est dispuntandum (好みは人それぞれ)。前菜 Apicium。
キリスト教徒は金曜日(主の受難日)に魚を食べる。甘味には蜂蜜を使っていた。ワインは水で割りも蜂蜜を混ぜていた。生活に不可欠で、奴隷にも1日1リットルが支給された。ローマ人の宴: サンダル soleae に履き替え、syntesis を着て、奴隷 nomenclator(名簿係)、structor(プランナー)、carptor(給仕係) が取り仕切った。共和世紀以降はコの字型に並べた長椅子に寝そべって食べた。liquo (濾過する)。道化師(scurra)、cinaedus (同性愛の小姓; これは違法で起訴された: 婚姻により人口を増やすことが不可欠と考えられていたため)。
Lectio XIX : ローマ人の遊び Ludi Romanorum.
あら、『ベン・ハー』が2016年版としてリメイクされていたなんて知らなかったわ。日本では興業なしでブルーレイだけ発売されたとのこと。
ローマ時代のコイン投げゲームは capita et navia (頭と船)といった。
サイコロ賭博には形状により、talus、tessera、pyrgrus、fritillus、ボードゲームのludus calculorumがあり、駒には latrunculus、milites、bellator、などがあった。
子供たちの遊びには、aedificare casas、adiungere mures plostello、equitare in harundine longa、輪回しなどがあった。
salutatio という宗教的な踊りもあった。
剣闘競技は葬儀のための催しであった。Mitte! (攻撃しろ)、 iugula! Pollice verso (首刎)、sponsio という賭けもあった。
戦車競争は、赤、緑、白、青の4チームが競争した。
球技には、pila, paganicus, trigon, harenaria, harpastum, aluta, などがあった。
公共浴場について。
Lectio XX : 物事は、知っているものしか見えない Tantum videmus quantum scimus.
ムッソリーニがローマの道路建設により都市改造をした話。
Largo Torre Argentina の話。Curia Pompeiaにおけるカエサルの暗殺の話: Caesar eam videt! Caesar, cape eam! Et tu, Brute? / Veni, vidi, vici.
Tantum cidemus quantum scimus. (我々は自分が知っているものしか目に入らない)
[この先生は古代ローマの考古学にはあまり通暁していないようだ。]
Lectio XXI : 私は欲望する。ゆえに存在する。Desidero ergo sum.
17世紀の哲学者スピノザの言葉: Desidero ergo sum. 著作『エチカ』にて、欲望とは天地万物すべてに共通する本質に過ぎない、とした。人間の精神と肉体は、自然の法則(potentia、potestas )に従うものだと述べた。Desidero sed satisfacio.
デカルトは『方法序説』にて Cogito, ergo sum. (我思う、ゆえに我あり Je pense donc je suis. ) と言った。
Lectio XXII : 韓国人ですか? Coreanus esne?
イタリアのMITO国際音楽祭で、韓国の「正楽(チョンアク)」が演奏された。
Cujas es (estis)? / Cuius gentis (populi, civitatis) estis? (どこの国の人か?)
Ego sum Coreanus/ Sinicus / Hispanus. o Nps sumus Coreani/ Italii/ Germani/ Anglii/ Japonius.
孔子 Confucius/ 孟子 Mentius はイエズス会のマテオ・リッチによる造語。
国家という概念は近代になってうまれたもの。
Lectio XXIII : しかし、今日も明日も、またその次の日も、私は進んで行かねばならない Vermtamen oportet me hodie et cras et sequenti die ambulare.
malus (りんごの木、悪い) / malum(りんご、悪).
男性形、女性形、中世形は malus mala malum (悪なのは旧約聖書から?)
十戒の六条「姦淫するべからず neque moechaberis」から sex (六)→ secus (性)
姦通 adulterium、売春・不倫 fornicatio
hic (指示形容詞 これ) の性別格変化
studere 専念する、努力する、没頭する。
新約聖書、ルカによる福音書にある一文: Vermtamen oportet me hodie et cras et sequenti die ambulare.
Lectio XXIV : 真理に服従せよ Obedire Veritati!
パウロは、現世の権威は神から与えられたものなので、キリスト教徒は国家に服従する義務があるとした。中世には、世俗の学問により、諸問題を解決しようと大学が生まれた。教養科目 artes liberales (人文学) / 真の学問 scientia.
中世の大学は veritas (真理)、sapientia (知恵)、lux (光)などをモットーとした。
veritas の形容詞は verus。真理に服従せよ Obedire Veritati! このobedire は動詞の原型ではなく、命令法・能動態である。
真理という言葉を考えるには宗教とともに考えるべき。大自然は、誤った存在ではなく、異なる存在としてすべてのものを受け入れる。宗教は個々の小さな庭。
Lectio XXV : みな傷つけられ、最後は殺される Vulnerant imnes, ultima necat.
この文は、フランスのピレネー・アトランティック県にある Urrugne の教会の日時計に刻まれている。[永遠なものはない、すべてが壊れていき、やがて死ぬ。つまり生きているうちにやるべきことをなさねばならない」という意味ではないか?]。 著者の解釈はしかし、「傷つくことにより、自分の短所に気づかされ。自分をより深くしることができる」。傷に関する単語いろいろ: vulnusculm, stgma, ciatrices, combustum, trauma, transpunctio, hulcus, plaga, turpedo, ulceratio, vulneratio, vulnus (この二つは精神的な傷: 名誉毀損による心の傷).
Lectio XXVI : 愛しなさい、そしてあなたが望むことを行いなさい Dilige et fac quod vis. (アウグスティヌスの『ペルシア人のためのヨハネの手紙』より)
砂漠では信仰が深まる。砂漠の荒々しさが人間を浄化するから。心臓に持病をもつ著者はタクラマカン砂漠を訪ね、歩いて倒れ、病院に搬送され、ローマで再び学問を続ける決心をした。カエサルの言葉: alea jacta est! (賽は投げられた)
Lectio XXVII : これもまた過ぎゆく Hoc quoque transibit.
絶望と諦めという感情を筆者は最も嫌っている。 Nolite ergo esse solliciti in crastinum crastinus enim dies sollicitus erit sibi ipse sufficit diei malitia sua. (明日のことまで思い悩むな、明日のことは明日自らが思い悩む、その日の苦労はその日だけで十分だ)。今日の絶望や怒りを先送りにしてみなさい。
Lectio XXVIII: 命ある限り、希望はある Dum vita est, spes est.
著者は、日本による植民地時代についてまた語っている。[日本政府はもう少しましな植民地政策をできなかったものだろうか? どんなに未開であった彼の地に、日本の持ち出しでインフラを整備し、庶民に教育の機会を整えたかもしれないが、人間は自由を欲する動物なのだ。韓国人の恨みは激しく根深い。]
Dum spiro, spero. (息をしているうちは、私は希望をもつ)。
Dum vivimus, speramus. (生きている限り、私は望む)。
Letum non omnia finit. (死がすべてのことを終わらせるわけではない)。
Salvete, miei socii (こんにちは、わが仲間よ)
Vos autem nolite vocari rabbi unus enim est magister vester omnes autem vos fratres estis. (しかしあなた方は先生と呼ばれてはいけない。あなた方の先生はただ一人しかなく、あなたがたは皆兄弟なのだから)。
学問の前で人間がもつべき態度は謙虚さのみ。