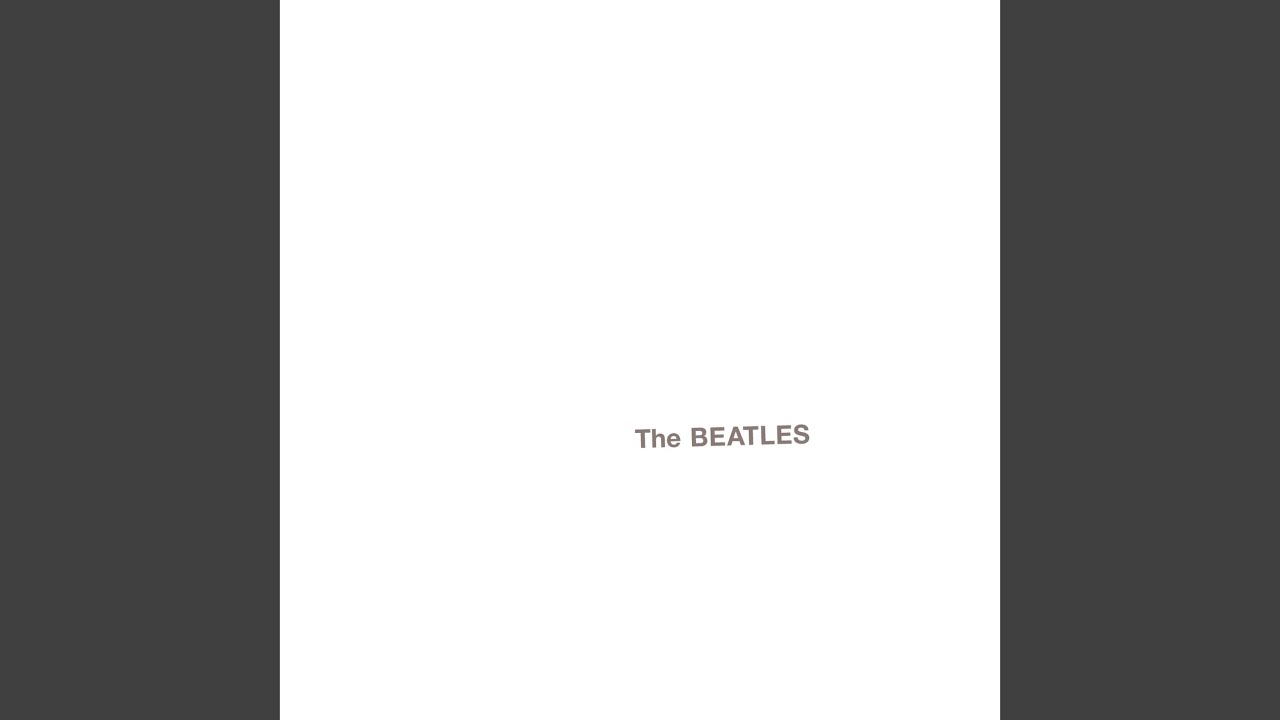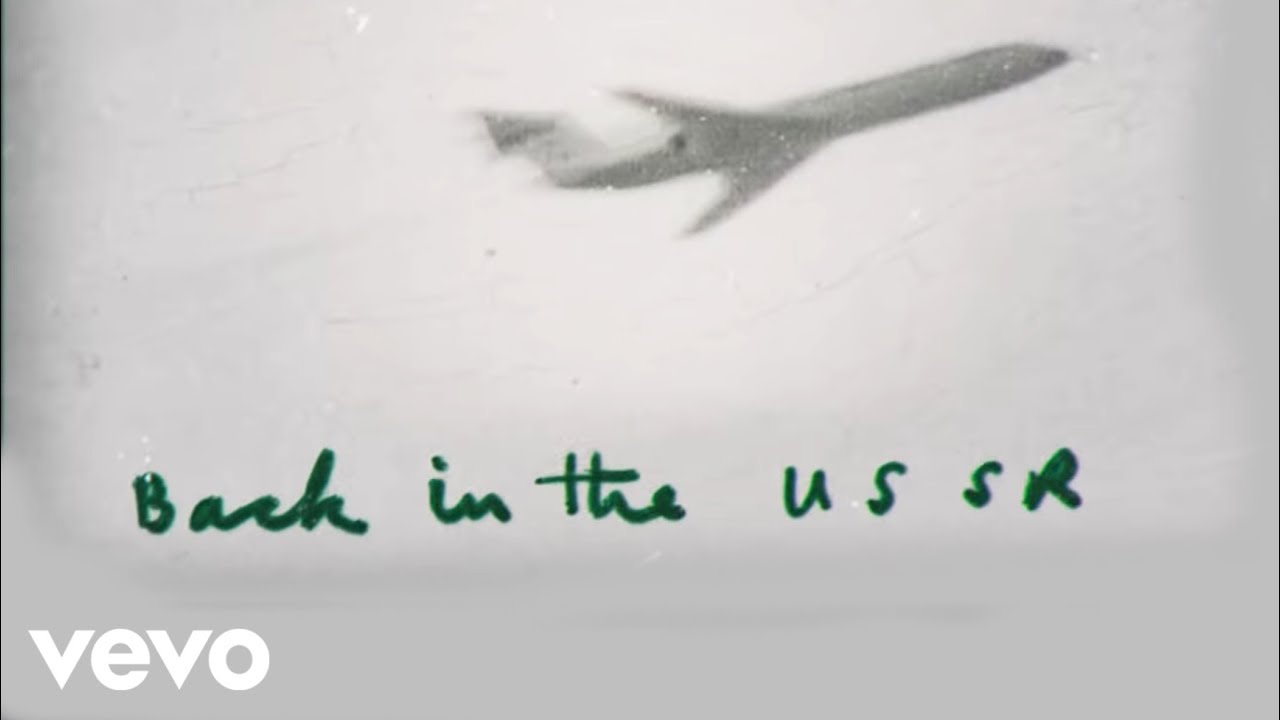●●●●●●●●●●●●●●
★59位
【Martha My Dear】
<THE BEATLES(WHITE ALBUM)>1968.11/22=2:28=
正にポールらしさ全開で、ポールの天才性を感じさせる、ポップス職人が真骨頂を発揮した名曲である。
そして、この世の中で、ポール・マッカートニーという人しか書けない曲でしょう。
恐らく、ポールの弾くピアノ曲で1番難しい曲である。
そう、この曲は、ポールのピアノの練習中に思い付いた曲でもあるのだ。
この時代、著しい成長ぶりを見せたピアノの腕のポールだが、両手弾きの難しい技術があるので練習しているうちに生まれたらしい。
なので、今でも必ずしも、いつも完璧に弾ける訳ではないので、ポールのソロ公演でも2022年の今でもライブ演奏したことはない。
但し、今でもピアノの練習になるからと、本番前のリハーサルでは弾くことがあるようだ。実際、日本公演(武道館)のリハでも弾いていたのだ。
「WHITE ALBUM」に収録されている曲ですが、ポール以外の他のメンバーは録音に参加していません。
ポールは、ピアノ、リッケンバッカー4001S、フェンダー・エスクワイア、ドラムス、ハンド・クラップと、ブラスとストリングス以外は全部、自分で演奏しています。
もはやワンマンレコーディングで、マルチプレイヤーの域に達してしまっていますが、こういうことも、メンバーの絆を削いでいく要因ともなるのですから難しいものですね。
ブラスとストリングスアレンジは、ジョージ・マーティン。
曲のタイトルにある「マーサ」とは、当時、ポールが飼っていたシープドッグの名前です(その名前はポールの"音楽の女神"にちなんで名づけられたとも言われています)。
飼い犬マーサを歌いつつも、気持ちがすれ違う当時のポールの恋人ジェーン・アッシャーとのダブルミーイングなのかも知れませんね。
構成は意外と複雑で、イントロの出だしは4分の3拍子で、それから4分の2拍子になって、4分の4拍子になっていく。
でも、不自然な感じが全然しない。さすがだよね、曲作りが上手い。
コードも複雑である。書き出すと、相当な文字数になるので省略するが、まあ、面白い。
Drもポールが叩いているというのが定説だが、フィルの入れ方がリンゴそのものなので、リンゴ説も未だに可能性が残っている。
どちらも存命なのだから、確認して欲しいものである(もう覚えてないか?^^;)。
録音は、1969年の10月4日に、たったの1テイクで完成させてしまった。
しかも、その日のうちに、オーケストラパートまで録音完了しているのだから、その集中度が凄いとしか…。
良く5日に、ギターとベースをオーバーダブして完成。7日には、ミックスまで終えている。
今は、オーケストラををミックスしていないデモを聴くことが出来るが、これがまた素晴らしい。
ポールのピアノが全面的に聴ける音源だからだ。
↓↓<デモ音源>↓↓
https://www.youtube.com/watch?v=d7ZuEE44KhQ
●●●●●●●●●●●●●●