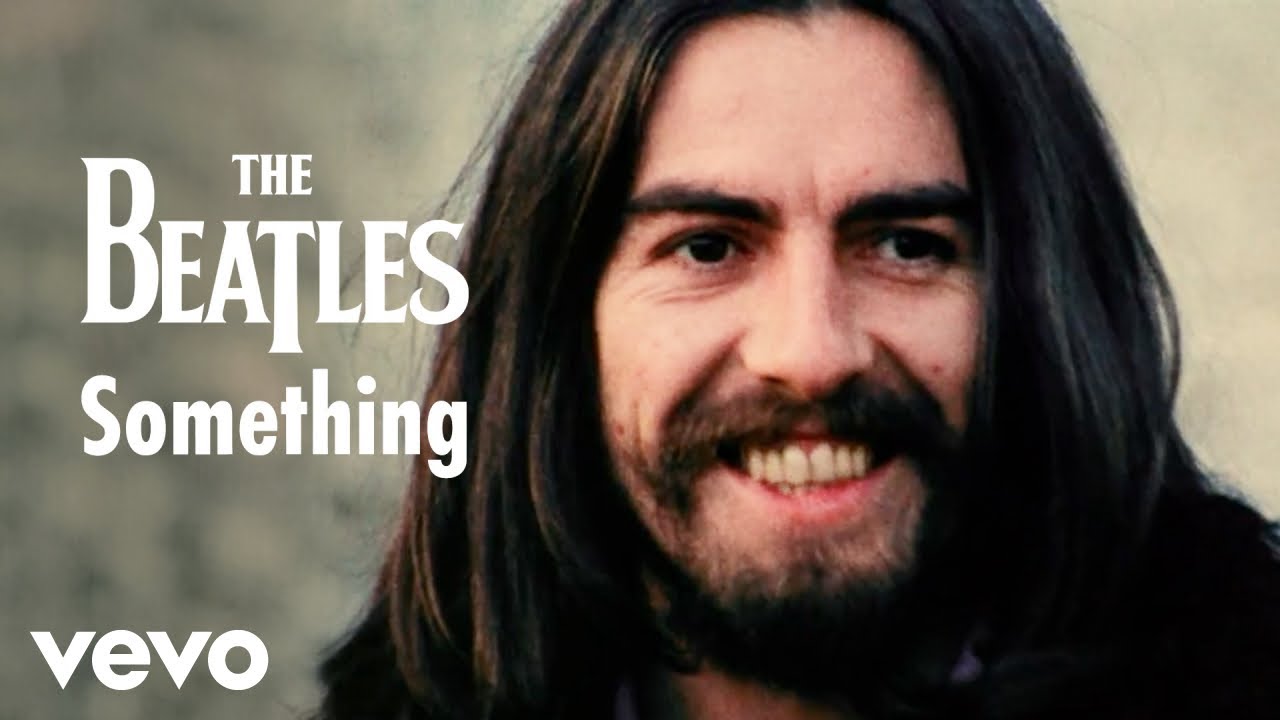●●●●●●●●●●●●●●
★29位
【Come Together】
<ABBEY ROAD>1969.9/26=4:17=
ジョンのBEATLES時代の最後の大きな大きな輝きである。
世界最高峰のイントロでしょう。
ジョンの"Shoot me"、ポールの不穏なリフ崩れのフレーズ、リンゴのタムロール…。
ジョンの、この曲の歌メロとリズムに対する単語の選び方も冴えている。
BEATLES(特にジョンとポール)が作詞家として他のアーチストと何が違うと思うのは、歌という観点で、音に対する言葉の選び方や使い方のセンスにおいて抜群だということ。特に、ジョンという人の言葉のグルーブ感は図抜けている。
1956年のチャック・ベリーの曲“You Can't Catch Me”を、尊敬と軽い気持ちで拝借した(と思われる)ブルーズ曲です。
flat-topの言い回しのあたりは、レコーディング前にポールからチャックの曲に似ていると指摘を受けたようですが、ジョンは構わずオリジナルとして発表しました。
「ちょっと似てしまったかもしれないが、これ程度のものなら良くあることで、少し変えなければなと言い、結果、オリジナリティが勝っているから」と判断したのでしょう。
元はチャックの曲同様に速い曲だったが、ポールの提案で、スローなリズムで、押し寄せるような圧倒的な曲調にしようということになる。
チャック・ベリー本人はこの件に関して何もコメントしてませんが、著作権者であるモーリス・レビーが訴えようとしたのですね。でも、交換条件で話は簡単についてしまったのであります。
ジョンは“無理やり裁判所に連れて行かれたんだよ”なんていう、らしいジョークをかましていますけどね。ジョージの“例の曲”の件もありましたからね…。
ジョン自身は、潜在意識的にリスペクトも含めて、いつか超えたいと目標にしていたチャック・ベリーをようやく超えられたという思いはあったのかも知れないですね。俺はもっと先に行くよという意味でね。
この曲に関しては、他の3人が全員、素晴らしいプレイを聴かせてくれている。久々にまとまりのある最高の演奏とも言える。
まず、ジョージのギターのフレーズは、音としては音数が少なくシンプルですが、その中に詰まったアイディアと情念を感じますね。良い仕事してますよ。
次は、リンゴの最小限の音数のグルーブ感が心地良く、そこに例のリフのようなフレーズが繰り替えされる。
さして、極め付けは、曲自体のイメージを支配しているポールのベースプレイ。ただの8分弾きや、弾いてない箇所もあるくらいなのに、このリンゴのフレーズと連動したコンビネーションは最高としか言いようがない。最強のリズム隊なんだと高々に宣言する名演。
更に、ジョン自身が、フェンダーのローズピアノを間奏で弾いていて、これが実に効果を挙げているが、実はこれはポールの考えたフレーズをジョンが弾いてしまっていたのだ。ちょっと、これで問題が起こった…。
ここでは、それはともかく、結果的に全員の演奏とこの曲だけが持つ独特な雰囲気に、後年、ジョン自身がこの曲を“ファンキーでブルージー、この曲は買いだね”と自画自賛したのも頷ける。
そして、意外と気付かれていない「低音コーラスの妙」。
曲のイメージ合わせた、通常は上のコーラスパートを歌うことがほとんどだったポールが、常にジョンより下を歌うという新しい試みで、解散間際の最後の最後まで新しいことにチャレンジしていたことの驚きと同時に、嬉しさを感じざるを得ないのです。これはポールの発案かなあ?だとしたらポールはやっぱり凄いな。
曲のイメージに合ったアイディアもまたビートルズの魅力。
細かく解説すると、ジョンがシングルトラックで歌ってきて、最初のヴァースはポールのコーラスが入らず、2回目のヴァースでポールのコーラスが入って来ます。サビではジョンのダブルトラック。
歌詞については、かの“I Am The Walrus”とは違った意味での奇奇怪怪な内容で、いろんな解釈をしてみたが、未だに結論に至っていない。そもそも結論(意味)はないのだと思う。
Come Together“一緒に行こうぜ”は、メンバーの事、ドラッグやSexの“イク”の意味とあったりで、すでに解釈が分からない。
後になってしまったが、良くこの曲のキーはマイナーで、イントロ最初のコードをDm7と書かれたコード譜を見掛けるが、キーはDメジャーで、最初のコードはD7(#9)でいきなりテンション爆発の曲なのです。
(コードについては諸説あります)
ジョンが後年、“Come Togetherは自分がBEATLES時代で書いた曲で1番好きな曲”と発言したこともあります。
張り詰めた空気感と洗練の極地に至るサウンドが織りなす、最強のビートルズ流ロックンロール。
何だかんだと御託を並べても、単純に、有無を言わさぬカッコ良さなんだよ、この曲は!
●●●●●●●●●●●●●●