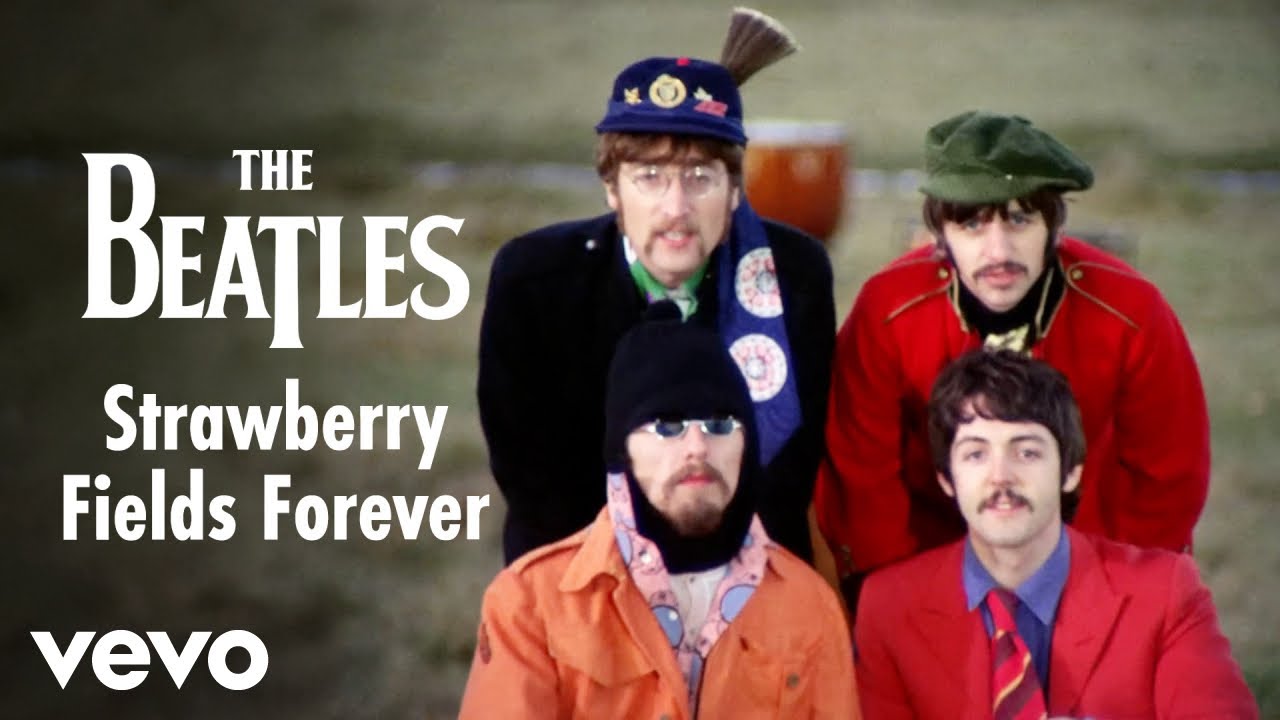●●●●●●●●●●●●●●
★1位
【A Day In The Life】
<SGT. PEPPER'S LONELY HEARTS CLUB BAND>1967.6/1==
BEATLESが残した最高傑作にて、音楽史上における最高傑作である!!
一大叙事詩である。
ジョンは、この曲をポールと一緒に作っている時がBEATLESで一番楽しかったとも語っているのですが、それがすべてですよ!
こんな名曲を作っている時なんて、至上の喜びでしょう。
レノン/マッカートニーの頂点でもあり、BEATLESの総力でもあり、ジョージ・マーティンやジェフ・エメリックまでも含めたBEATLESファミリーの総決算でもあった。
オーケストラを演奏というだけではなく、演出というコンセプトで用いてしまったことは極めて独創的で、かつ前衛的である。
間奏部分とエンディング部分の、重厚極まりないオーケストラサウンドが次第に高揚していく様は、緊張感と恍惚感を聞き手側に与え、最後のピアノ3台(奏者は4人)による強烈なコード音の圧倒的な迫力と、何処までも続くような余韻は、正に、SGT. PEPPER'S~というアルバムの最後に相応しい音世界で示されるのである。
まずは、ジョンの持って来た曲からスタートした。
しかし、パートはバース部とサビしかなかったので、中間部を空けておくことになった。
そこに、逆にミドルしか出来上がっていなかったポールの未完の曲を繋げて1つの楽曲となった。
そこで、注目なのは、この2つの曲は曲調も違うし、キーもすらも違うにも関わらず繋げようと思ったことだ。もっといえば、拍も変だし、ギターとピアノのコードが違う(凄い!)
全く違う曲を2つを何故、この曲たちを繋ぎ合わせようとしたのだろうか?その発想自体が凄く、そして、その強引な接合にストーリーをもたらす発想が恐ろしい。しかし、これが完璧なのだ。
ここがまずBEATLESマジックだろう。
まず、ジョンのパートだが、ジョンの書いたメロディ(歌詞も)が余りにも素晴らしく秀逸だが、流石にそれを歌うジョンの歌がまずもって良い。淡々と歌っているのだけど、その浮遊感が素晴らしいのだ。適度なリバーブ感が透明感を増し、独特な感じにしている。これは、チーフ・エンジニアのジェフ・エメリックがテープエコーを使った成果も凄く出ている。さすがエメリックである。但し、これは誰の歌声でもその効果が出る訳ではなく、ジョンのあの声質があってこそ生きるものだということは書いておきたい。
ジョンの歌うパートの最後に出てくる短いフレーズではあるが、この曲のサビともいえる要中の要である「I'd love to turn you on」のメロディと歌詞はポールが書いたが、ジョンは歌詞もメロディも絶賛している。
この部分の儚く弱々しくジョンのVoがストリングスの洪水の中に消えていく様は、1億回聴いても鳥肌が立つ。
続くポールの歌うミドルのパートは、それまでのジョンが夢の中であったかのように目覚まし時計が鳴り響き(これは偶然の産物でもあるが)、ある男の1日の始まりを歌う。この繋ぎが上手いなあ。
淡々と歌うポールのVoは、ジョンとVoとは敢えて対照的過ぎるくらいに意識して、朝の1人の男の歌を現実的に歌っていて、ジョンの部分とクロスオーバーするこの対比感がこの曲に与えている効果は計り知れないのだ。このポールのVoは大好きだ。
なのに、それは突如舞い上がり、足は地から離れ、またジョンの「浮遊感」な世界に落ちていく。このスキャット風に歌うジョンのVoは史上最高とも思えるほどのアート感がある。ジョンの声って本当に唯一無二の素晴らしさだと思わせてくれる。
(この部分は、ポールの特徴であるコード進行「C→G→D→A→Eと5度から5度へと進行していく」から、ポールが作ったという意見もあります。Anthology 2 Versionではこの部分は空いているので、それを踏まえても、この部分はポールが作ったと見るべきでしょう。ただ、ポールやジョンは、この部分までは細かく言及していないので、あくまで推測ではありますが)
そして、再び最初のパートに戻り、最後は、さっきよりも強烈なストリングスの波にかき消されていく。遠くで謎のカウントが聞こえ、ドラムはずっと忙しく転がり回り、そして限界の限界までストリングスが高揚していく。
40人(4回音を重ね事実上160人という構成に)が参加したオーケストラの部分は、スコアから録音まで膨大な経緯があるので、ここでは割愛するが、肝心な部分だけは書いておこう。
スコアを書いたのはジョージ・マーティンだが、このオーケストラのパートでのポールの貢献も大きい。
ポールは、上昇していくクレッシェンドの部分について、“他の部分はちゃんと譜面にすべきだけど、あの15小節だけは、一言、『最低音からはじめて、最高音で終わってくれ』と指示を与えるだけでいいんじゃないか、と僕が提案したんだ”と語っている。
それを受けたマーティンが、最初の小節にそれぞれの楽器が出せる最低音を、そして最後の24小節目には、Eメジャーのコードに一番近いところで、それぞれの楽器が出せる最高音を大まかな形でスコアに書いた。
しかし、問題もあった。弦楽器なら弦に指をスライドさせられるので問題ないが、クラリネットやオーボエのようなキーのある管楽器などでは、どうしてもキーからキーへと指を動かさなければならない。そこで彼らには、唇を上手く使って、出来るだけ多く変化つけてくれとマーティンは頼んで指示を出したのだ。
最高音量に達するまでの音量の上昇についての細かいテクニックははもちろんエメリックの手腕によるものだ。
そして、いよいよ、あのポピュラー音楽史上に残る最後のピアノの大音響である。
3台のピアノ(グランドピアノ、アップライトピアノ、エレピ)とハーモニウムがスタジオに運ばれた。
ポール、ジョン、リンゴ、そしてマル・エヴァンズの4人(ジョージはこの時、スタジオに居なかったのだ)は3台のピアノの前に腰かけ、同時にEのメジャー・コードを叩いた。ぴったり同じ瞬間に鍵盤を叩くのは難しく、ポールが指示を出しながら、綺麗に音を揃えるために何度もやり直していて、成功したのは9テイク目だった。最後が一番上手く合った。それを3回オーバーダビングし、9台のピアノを12人で演奏したような効果を出したのだ。
加えて、ジョージ・マーティンの弾くハーモニウムを加えたオーバーダブを3回繰り返して4トラック全てを埋めた。
更に、この音を持続させるために、振動が消えるにつれ音量を上げていき、40秒以上残響が残るようにした。なお、音量を上げ切ったことにより、暖房機の音や、椅子などがきしむような音や譜面と思われる紙をめくるような音なども僅かに聞こえるのだ。
なお、1967年のアメリカ盤を除くLP盤において、本作の後に15キロヘルツの高周波の音と、逆回転させた笑い声と話し声が収録されている。
加えて、ジョンは「犬の為にも何かサウンドを入れよう!」と言い出して、人の耳には聞こえないが、15KHzの犬笛の音も入っている。これら部分は「エディット・フォー・LP・エンド」と呼ばれる。
演奏面で言えば、リンゴのDrプレイがまた素晴らし過ぎるのだ。
楽曲の良さを異次元まで持っていっていったのが、このリンゴのオーバーダブしたDrプレイである。やや不安定な音像の下で、小気味よく転がっていくDrがかなり素敵だ。浮遊感と自らのドライブ感の狭間でこの2つを繋ぎ合わせてもいる。
だから、リンゴのドラマーとしての才能・凄さは、ここにあるということが良く分かるのだ。
エンジニアのジェフ・エメリックは、低音に拘り、タムもまるでオーケストラのティンパニのように聞こえるくらいのサウンドになっているのがまた凄い。
この曲は、ドラッグ描写がいくつもあるということで英国のいくつかのラジオ局ではでは放送禁止処分を受けた。
以前にも出てきたポールの歌詞で「Turn you on」や、「had a smokeから~の I went into a dream」や、ジョンの「He blew his mind」など、数か所も出てくるのです。
過去の歌詞の経験から、取り締まる当局も見逃さなかったのは、以前は分からなかったこういう隠語をドラッグカルチャーとして学んでいた結果なのでした。
クラシックとポップのミュージシャンの垣根を取っ払ってしまいたいというジョンのイメージがあり、ポールの発想と提案でクラシック演奏者全員に仮装させようということになった。良く了承したなあ、クラシック畑の方々達は。でも、概ねは楽しんでやっているのです。ギャラが増えたこともあったでしょうが(笑)。
オーケストラ奏者に仮装用のコスチュームの小物が(それからプラスチックの乳首も)配られるとムードが和らいだ。ブライアン・ジョーンズ、キース・リチャーズ、ドノヴァン、ミック・ジャガー、マリアンヌ・フェイスフルなどもレコーディングに参加した。
当時は、4トラックのレコーダーが最新機器で、この複雑な音楽を録音するのは不可能であった。そこで、ジョージ・マーティンがエンジニアのケン・タウンゼントに「4トラックのレコーダーを2台同時に同期させる事は可能か?」という打診をし、ケンは片方のレコーダーから信号を取り出して、もう片方のレコーダーに直に配線を繋ぐことでこれをクリアした。もちろん、これもBEATLESにおける世界初の出来事である。
これでBEATLESの4トラックマスターを聞きながら、4トラックのオーケストラの録音が可能になった。
今では無限にチャンネルが使える時代になったが、この当時、良くこれだけのことが出来たものである。音楽に注いだ情熱の賜物である。
才能と情熱との絶頂期であった彼等BEATLESが生み出した奇跡の楽曲なのである。
だから、何万回聴いても、必ず心して聴くことにしている。
この曲が、その後のミュージシャン(特にプログレッシブロック)に与えた影響は計り知れず、音楽の概念を変えてしまった1曲といって良いだろう。
そのように、ポピュラー音楽やロックの世界では革命を起こしたこの曲だが、クラシック界での評価が気になるだろうが、かのクラシックの巨匠バーンスタインが、この曲を大絶賛したのである。
最後にもう1度言おう。
A Day In The LifeはBEATLESの最高傑作であり、音楽史上の最高傑作でもあるのだ。
そして、音楽の金字塔である。
●●●●●●●●●●●●●●