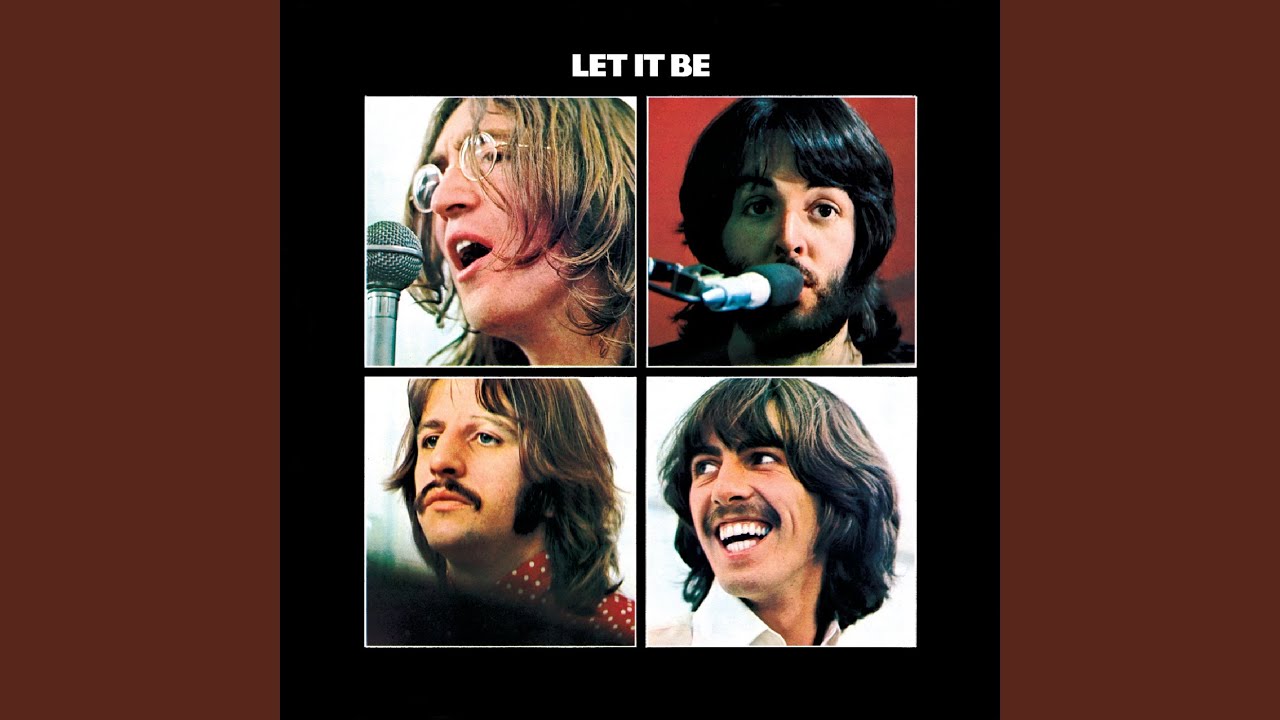●●●●●●●●●●●●●●
★9位
【I Am The Walrus】
<Single & MAGICAL MYSTERY TOUR>1967.11/27=4:34=
レノンワールドは、音のファンタジーである!
間違いなく世界中でジョン・レノンという人間にしか絶対に書くことが出来ない曲であり、とてつもなく個性的であり前衛的であり完成度が高い曲であり、狂気とシニカルさが同居した名曲中の名曲。
ジョン自身も100年後も通用するサウンドと自らが言ったが、すでに半世紀以上の月日が経ったが、まったくもって色褪せていない。200年後も通用するサウンドと楽曲だと思う。
メロディ、サウンド、歌詞に至る全編に行き渡ったナンセンスさは、非常に薄暗く退廃的な倦怠感に満ちている。
圧巻なのは突然変な効果音が挿入されてから曲全体が浮かび上がってミドルエイトへ向かう展開。ボーカルの効果はきつくなり、ストリングスがより前面に出てきて(しかしなんて退廃的なストリングスだろう)、そしてエンディングで次第に壊れていく。無意味な効果音が飛び交い、変なコーラスや、ラジオから流れる『リア王』が混沌を作り出していく。
圧倒的な混乱具合が陰惨さに繋がっている。そういう点で僕はこの曲とM8が対極的なものに感じる。
コード進行も異様である。
まあ、一応、音楽に絶対的な理論がある訳ではないので、ハチャメチャということではない。ただ、進行がジョンの独特な感性のみで作られているのだ。
イントロからして謎進行ですね。キーは一応「B」であると思われますが、すでに歌に入る前に「A」に転調してからの進行です。で、そのままAメロのキーが「A」なので、そのまま進行する。
(イントロのコード進行は、B→/B→A→G/F→E→E7→D→D7である)
Aメロ~サビも循環的なコード進行とは程遠いながらも、まだ音楽的ですが、問題はエンディングですね。
もはや無調性と捉えるべきという進行で。
特筆すべきは、ジョージ・マーティンが考え譜面を書いたバイオリンとチェロとホルンの絶妙なアレンジだろう。それらがこの曲のアレンジの要であると言って良いだろう。
フィルターがかった感じのようなジョンのVoだが、これは、またまたジョンがジェフ・エメリックに“月から聞こえてくるような声が欲しい”という無理難題を言って作った声である。
至るところに入るコーラスらしくないコーラスもこの曲を特徴づけている。エンディングの合唱団風の意味のないコーラスに至るまで、とても普通では考えもつかないフレーズを散りばめている。
演奏面では、やはりジョンが大活躍で、エレピとメロトロンまで弾いている。
曲が曲だけに、リズム隊はタイトにプレイしている。ポールも要所で速いフレーズが出てくるが基本は8ビートである。
プレイに対して悩んでいたリンゴに、ポールはベースを弾くのをやめてリンゴの側でタンバリンを叩いてリズムイメージを伝えた。これに励まされたリンゴは良いプレイをこの曲では聴かせている。リンゴは後々までこのポールのこの時のさり気ない励ましをBEATLES時代の1番の励ましで嬉しかったと回顧している。
歌詞についてだが、観念的な歌詞はジョン曰く、
“歌詞の1行目はある週末にアシッドでトリップしているときに書いた。2行目はその次の週末のアシッドトリップで、そしてヨーコに出会って全部埋まった。Walrus(セイウチ)は『セイウチと大工』からきている。『不思議の国のアリス』のね”と語っている。
しかし、それにしても無意味で本当にナンセンスな歌詞という意味では、BEATLESで1番だろう。しかし、文学的でもある。
あと、エロティックで危ない表現もあり、ジョージ・マーティンはこの歌詞を嫌っていたらしい。少女の下着を下ろせや、その少女を“Boy”と表現したり…この歌詞の世界観は異常というか…本当に意味不明である。
それを読んで不思議がってる我々を笑っているジョンもいるような気がするが…まあ、すべてはドラッグトリップと、ジョンの持ってる陰湿な部分をさらけ出してるところが交差しているのだろう。
個人的には、「Yellow matter custard dripping from a dead dog's eye (黄色い膿みたいなカスタード、死んだ犬の目から滴り落ちる)」がいつもヤバいなあと思っている。
ちなみに、ポールは、「“Sitting on a cornflake”なんて、かなり混乱した状態の歌詞だよね」と後に語っている。
エンディングがサイケの最たるもので、わざわざプロのコーラス隊を呼んで奇声を上げさせたり、ラジオで流れてきた「リア王」のセリフを取り込んだりと、これでもかという怒濤のエンディング。
特筆なのは、歌のリズムです。この部分は何と宮城県民謡である「斎太郎節(さいたらぶし)」をモチーフにしているのです。確かに「エンヤートット」というリズムなのが分かります。
ジョンはこの民謡と、1966年の日本公演の来日時に聴いたのです。
メンバー4人の中でも、特に日本文化への関心が高かったジョンは、ホテルで民謡のレコードを聴き込んでいたのだそうで、その中でもお気に入りだったのが、この「斎太郎節」だったのです。
余談だが、歌詞に出てくる「Egg Man」は、不思議な国のアリスにも登場するが、実はアニマルズのエリック・バードンが「エッグ」と呼ばれていたのだ。ジョンも参加した乱交パーティで、セックス中に女性の体の上で卵を割ることが性癖だったエリックを見ていたジョンが“行け!やれ!エッグマン”と叫んでいたという話が伝わっている。この頃のジョンは、生活も乱れ、相当にイッてしまっていたのだろうね。じゃなきゃ、こんな異端な名曲は生まれない。
録音もミックスも複雑な経路を辿ったために、この曲は公式音源で、モノで2種類、ステレオで6種類のVer.もあるのである。
●●●●●●●●●●●●●●