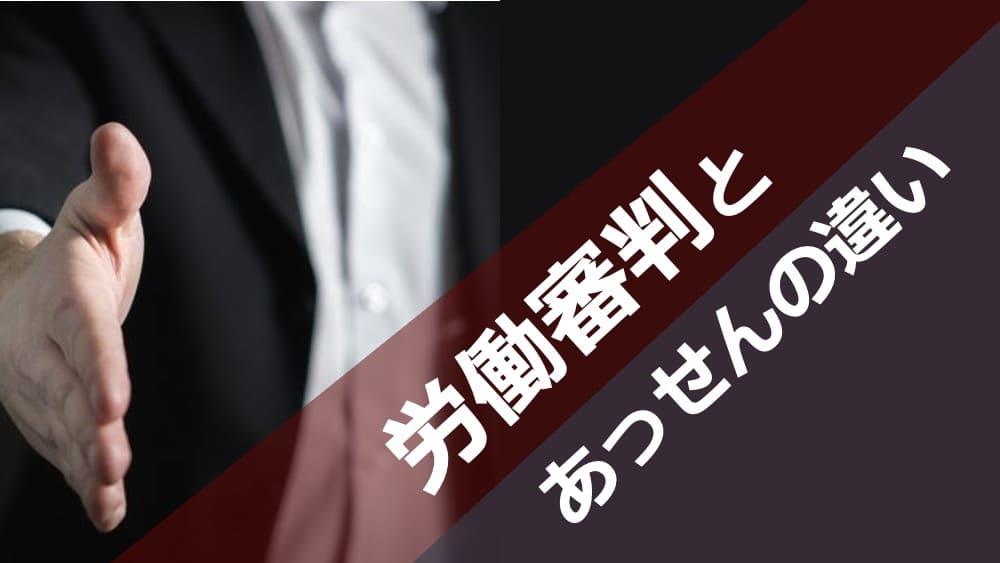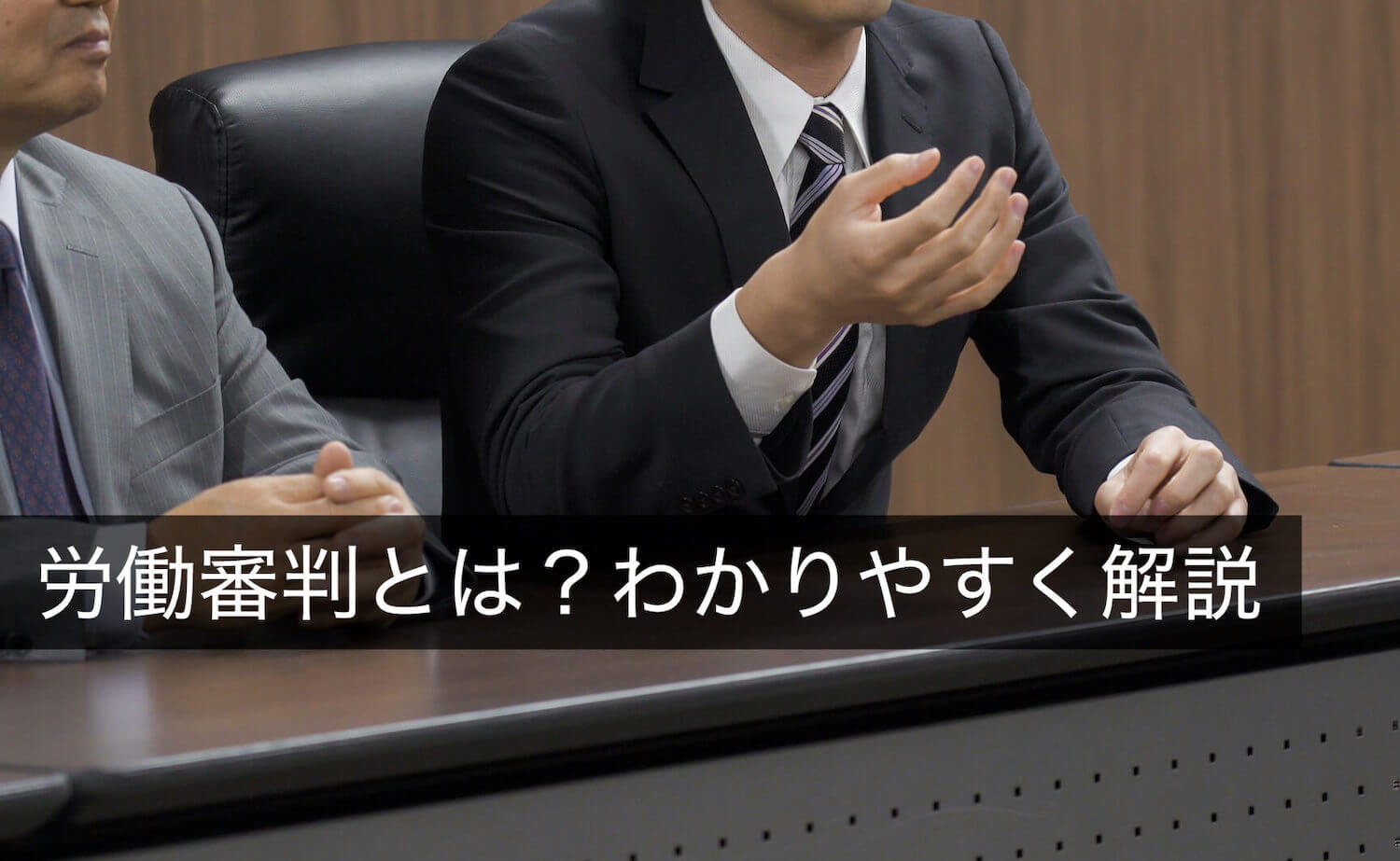労働審判のすすめ-03R
<労働者側の立場での労働審判準備>
下記のサイトの解説は非常に分かり易い
ので、まずは熟読してみてください。
労働審判のすすめ-02
<労働審判での準備:予備知識編>
1)労働審判で最も重要な点を確認
①予告なし、解雇事由不明な中
突然の解雇通告を受けた場合
などの「不当解雇」か?
②残業代・夜勤手当・通常賃金
等の「賃金の未払い」か?
③その他の事由(パワハラその他
の事由)か?
上記のどれに相当するのかの確認
2)ここでは、①と⓶のケースで労働
審判にするのかを、まず明確にし
ます。
筆者の事例では、①です。同僚の
方の場合は、①と⓶の両方が当て
はまる場合です。
3)その理由により、請求すべき金額
が変わることに注意が必要です。
「予告手当が未払い」のケースも
あります。
4)確認事項
①雇用契約書の有無
②解雇通知書の有無
③解雇理由の明示の有無
④証拠資料の有無
⑤労働審判に至った理由
まずは、上記の内容を確認しましょう。
解雇の「不自由」はなぜ起こるのか
「おまえはクビだ!」の一言で解雇されて
しまった主人公が、明日からの生活に思い
悩む中で、物語は始まりを迎える。
ドラマや映画で、よく見かける出来事です。
しかし現実の世界では、その次にやってく
るのは辞めさせた従業員が依頼した弁護士
からの内容証明郵便であり、行く先にただ
煩わしいトラブルが待っているのみです。
もしかすると、今まで何人か解雇したこと
があるけれども、文句を言ってきた者は一
人もいないので、トラブルを恐れて解雇を
控えるのは、経営者としての覚悟が足りな
いとお考えの方もいらっしゃるかもしれま
せん。たしかに、解雇された従業員のうち、
会社に対して弁護士に依頼してまで反撃を
加えようとする人は、昔は少なかったかも
しれません。
しかし、今や誰もが瞬時に大量の情報に接
することができる時代です。少しでも解雇
に納得がいかないと思えば、インターネッ
トを使ってほんの数分検索するだけで、労
働者側の立場から、解雇の効力を争って会
社と対決することを請け負う弁護士の情報
は、山のように出てきます。
そしてそこでは必ず、
「解雇は簡単にできないので勝算がある」
という論調の説明がなされています。
どうしてそのような強気なことがいえるか
というと、我が国では雇い主と従業員との
関係についての法律の体系が、「労働者を
保護する」という価値観で出来上がってい
るからです。どこでどのように働くかにつ
いては、雇い主と従業員との間で取り交わ
される雇用契約によってその内容が定まり
ます。
解雇するということは雇い主側から、辞め
るということは従業員側から、それぞれ契
約を一方的に破棄することを意味します。
一度結んだ契約は、そう簡単に破棄するこ
とはできないことは当たり前なので、解雇
が簡単にできないこともまた当たり前だと
いうことになります。このことは法律上、
「解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、
社会通念上相当であると認められない場合、
その権利を濫用したとして、無効とする」
という定めとして端的に表れています
(労働契約法16条)。
そうすると、従業員が辞めるということも、
契約の一方的な破棄なので、簡単にはでき
ないのではないかという疑問が当然に出て
きます。しかし法律は、期間の定めなしに
雇った従業員は、雇い主が承諾しなくとも、
申し入れから2週間経てば辞めることがで
きると定めており(民法627条1項)、
期間の定めをおいた場合でも、やむを得な
い事由があれば、すぐ辞めることができる
と定めています(民法628条)。
従業員が辞めるというのは自由なのに、
会社から辞めてくれということは制限され
るというのは、不公平ではないかと思われ
ることでしょう。しかし我が国では、憲法
によって、誰にも公共の福祉に反しない限
りで、「職業選択の自由」が保障されてい
ます(憲法22条)。今の仕事を辞めて、
他の仕事に就きたいというのも、自分の意
思に反して退職させられないことも、どち
らも我が国の重要な価値観として定まって
いるので、法律の世界では、こと解雇につ
いていう限り、簡単にはできない制度とす
ることこそが、むしろ当然と理解されてい
るのです。
========================
労働審判のすすめ-01
労働審判とは..
労働審判とは、労働問題を解決するための
一つの有力な方法です。
通常、労働問題が発生した場合、
例えば、残業代未払い、不当解雇が発生した
場合は、「労働基準監督署」に出向き相談し
その労働問題の「申告」を行います。
しかし、地域により或いは担当者によっては
現実には、まともに取り合ってくれない労働
基準監督署があります。そのケースは多いよ
うです。(筆者の経験した範囲では)
「申告」を労働基準監督署(以後、労基と略)
すると、労基は通常、その会社の調査をしま
す。しかし、それでも会社側はその労働者側
の申告を認めないため、そのまま労働者側が
泣き寝入りするケースも多いようです。
しかし、その場合にでも、「あっせん」という
制度があり、労基にその「あっせん」の手続き
をすれば、労働者側が雇用者側(企業)との
交渉が可能です。しかし、この制度は強制力を
持たないため、雇用者側から無視される場合も
多いのが現実です。
そこで、別な制度を使うことが可能です。それ
が「労働審判」です。しかし、この制度を素人
が何の知識もなく行うのは、正直難易度が高い
です。そこで、弁護士に依頼する方法も考えら
れます。通常は、その方がおすすめです。
しかし、弁護士に相談した場合、着手金とかで
それなりの費用がかかります。
そこで、このブログの案内は、あまり予算のな
い人を対象に、自分で全てを労働審判をするや
り方を案内します。