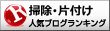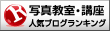今日は、東日本震災から11年。
テレビでも特集が組まれていますね。
地震、津波のみならず、ここ10年、20年、豪雨や浸水の被害も増えています。
今日という日に改めて、震災と暮らしについて考えてみたいと思います・・
・・・50代の家事と暮らし、デジタル化で残す写真整理、網野千代美です。
■一口に備蓄と言ってもどのくらい持てばいいの?
最近は備蓄に関する情報も豊富です。
特に、私が手元に置いて参考にしているのが↓こちら
■防災ブック「東京防災」
無料配布ですが、内容が充実したしっかりした冊子というより「書籍」で
東京在住でなくてももちろん役立つ情報がたくさんです。
ネットから無料でダウンロードもできますので、
ぜひ!ダウンロードしていただきたい。
↓ダウンロードページはこちら。
こちらにも、もちろん備蓄の適量は記載がありますが・・。
何人家族?大人は何人?ペットは?シニアは・・?と
家族の状況はそれぞれ異なるもの。
↓そこで!条件を入力しながら備蓄の適正量を知る「備蓄ナビ」にチャレンジ。
■わが家に圧倒的に足りないのは?
一覧をみて気づいたのは
- 消耗品(トイレットペーパーやラップ、電池など)は十分
- 食料品は圧倒的に足りていない
ということ。
たとえば必要な備蓄品リストは↓こんな感じ。
- 水: 63 L
- レトルトご飯: 63 食
- レトルト食品: 21 個
- 缶詰(さばの味噌煮、野菜など): 21 缶
- 栄養補助食品: 21 箱
- 野菜ジュース: 21 本
いやいや、こんなにないです・・
実際には↓↓こんな感じ
- 水: 24L
- レトルトご飯: 6 食
- レトルト食品: 6 個
- 缶詰(さばの味噌煮、野菜など): 6 缶
- 栄養補助食品: 0箱
- 野菜ジュース: 12 本
■適正量を知ったうえでさらに調整
適正量を知ったうえで、さらに
- 自分の住んでいる地域
- 収納スペース
- 消費のサイクル
などを洗い出して、最終的な備蓄量を決められるといいですよね・・。
ちなみにわが家の備蓄は、
キッチンの食品保存引き出しの中に一緒に入っています。
少し少な目かな・・というのは実は気になっていて、
コロナをきっかけに、多少見直しました。
11年目、気持ちを新たにもう少し増やしてみることを検討しています。
ちなみに、防災食ってやはり「長期保存対応」みたいな味のものもあるのですが・・
↓こちらの、カン入りバンはなかなかおいしかったと思います。
※でも水のまないと食べられないのよね・・
今日はここまで。
***********************
写真をGoogleフォトだけに保存している人、要注意!
こちらも参考にしてください。
たくさんのアクセスありがとうございます!
ポチしてね。
**********************************************
全国どこからでもお問合せくださいね!