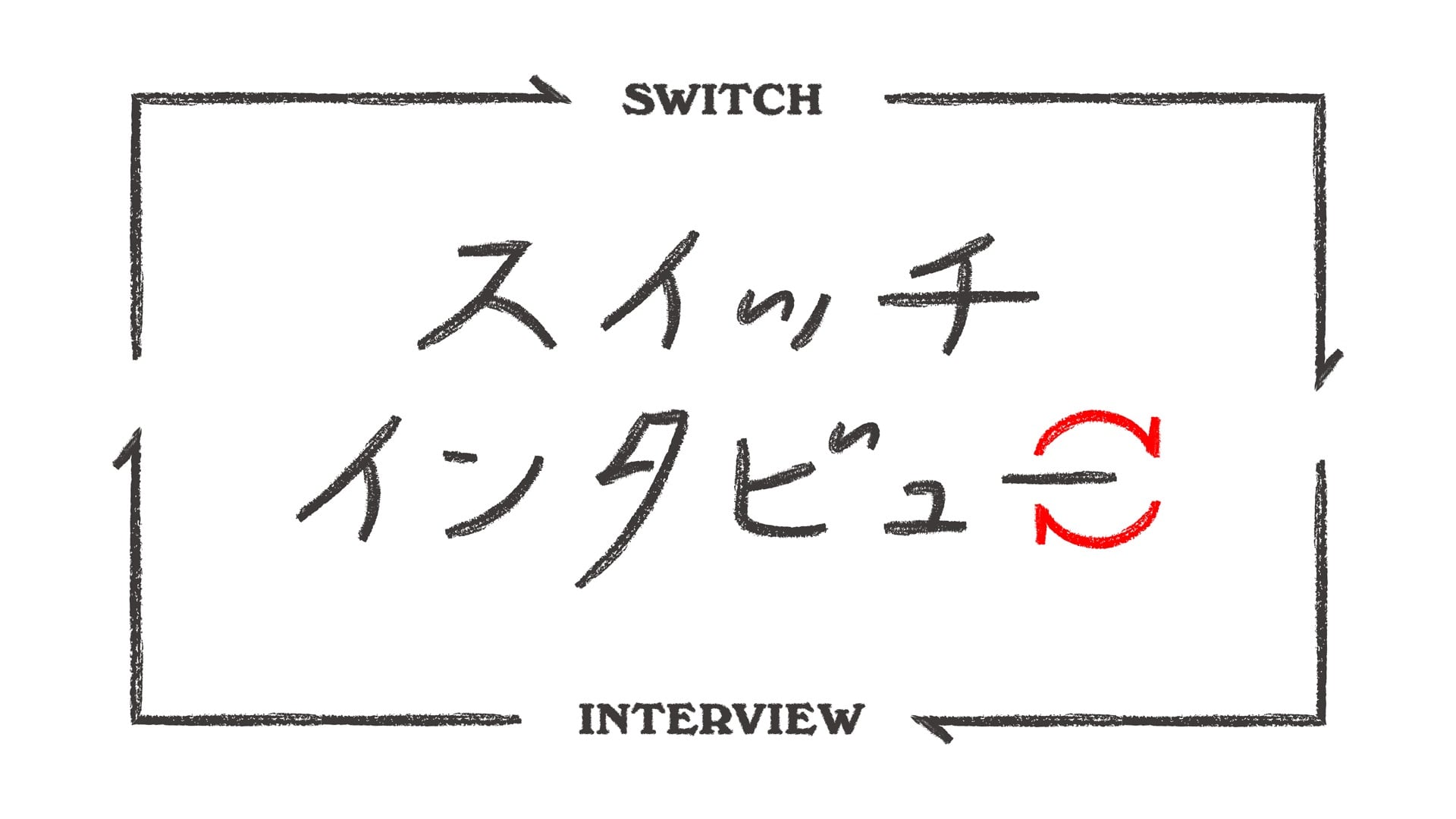今回は言葉について書こうと思います。
Q:4歳と14歳で、生きようと思った。に込められた意味とは。
Q:言葉との向き合い方、最近の傾向とは。
きっかけは「SWITCHインタビュー 達人達」というEテレの番組の芦田愛菜さんと糸井重里さんの対談です。
 SWITCHインタビュー 達人達(たち) - NHK
SWITCHインタビュー 達人達(たち) - NHK糸井重里が対談相手に希望したのは、年の差56の女優・芦田愛菜。人気子役から着実に成長を遂げている芦田が、言葉のプロフェッショナル・糸井と語り合う。
考えさせられたエピソードとして、火垂るの墓のポスターにあるキャッチコピー「4歳と14歳で、生きようと思った」と文章に対してのエピソードトークです
芦田さんはこのキャッチコピーが好きだということをおっしゃっていて。名前でも境遇でもなく、年齢ということで語りかけるところが面白いと言っていた。
対して糸井さんは「4歳というのは1人では生きることができない。14歳は4歳を生かすだけの力がない。つまりそんな二人だけで生きようと思ったということはよほどの状況なんだな」ということが伝わるように意図したとのことでした。
これを聞いて、全然何気ないと思っていたポスターのフレーズ1つが、こんなにも読者を考えさせるものであったこと、こんな思いが込められていたことを初めて知り、感動しました。
糸井さんは続けて、ただしこのようなキャッチコピーは現在ではじれったくて嫌だということであまり好まれなくなってきた、ということであった。今の世の中は、具体的に具体的にということが求められてきており、他のインタビューなどでも具体的には?という問いがすごく多いらしい。
でも、本当に言いたいのは伝えきれない気持ちなんだと糸井さんはいう。
「海を見て簡単に海だって伝えたくないと思ったときに言葉が生まれる」
「言葉じゃない言葉」「言葉にならないところの言葉」
糸井さんは言葉に思いを込めることの難しさや言葉から思いを汲み取ることの難しさを伝えようとしたトークだったと思います。
このことについて、以前読んだ「Q わたしの思考探究」という本(NHKの番組を書籍化したもの)の中で、ピースの又吉さんと言語学者の町田さんの対話の一節を思い出しました。
(又吉さんが出会った面白い便器というものを他者に伝えたい状況で)
町田 何千、何万とある便器の中で、その壊れた便器を正確に表そうとするなら、そのためだけの単語を作らなきゃいけないんです。たとえば「俺はこれを、ベヤキと呼びたい」と。
又吉 なるほど。
町田 でも「ベヤキ、ベヤキがあったでー」と相手に言っても、分からないわけですよ。
又吉 伝わらないですよね。自分ひとりで作った単語ですもんね。
町田 だからこそですね、言葉というのはある程度のまとまりに対して名前を与えて、それをみんなが共通に理解しよう、というものなんですね。だから絶対に言葉というのは、曖昧じゃないといけないんですよ。
又吉 そうか、曖昧じゃないとダメなんですね。
町田 言葉は曖昧であるからこそ、私たちみんなが自由に使えるわけなんですね。曖昧性というものから逃れられない、それが言葉の制約なんです。
糸井さんの言っていた「言葉じゃない言葉」というのは、この言葉の曖昧性というものと似ているのかなと見ていて感じました。だから、言葉の発信者も受信者も言葉の曖昧さというものを意識しながらも、その曖昧なものをすり合わせていく作業、それが私は言葉を味わうということなのかなあと思います。そうすると、現在ではこの言葉を味わうということをなおざりにしてしまっているのではないかなと思いました。
その一つとして、以前ブログにも書きましたが、再掲します。
(文章のごく一部にだけ反応する人達は、)その反応も、「正しいか、間違ってるか」「成り立つか、成り立たないか」という極端な反応が多く見受けられます。
そうなってしまう原因は、おそらく、
「この文章を読んで、作者がどう思ったのかを下記から選びなさい。」「この文章は何を伝えようとしているのか、下記から選びなさい。」
という問題にあるような気がします。
言葉の曖昧さということを考えずに、この文章はこういうことを考えている。ということを判断することが味わうと言うことを忘れさせているのかなと。
また糸井さんは、言葉を裏地にするということで、逆の思考もあるということを言っています。例えば、結婚する際に親に挨拶するときに、「娘を幸せにしてくれるか」という問いかけに対して、すぐに「はい」ということがパターンですよね。そのときに、「うーん」と悩んでしまったり「幸せって何ですか」といったりとかというものは求められていません。はいって言葉にしてから、どんなことが幸せなんだろうとか考え出す。つまり言葉から思考を進めるということもあるということを言っています。
「出した言葉とホントの気持ちのズレを大切にする。」だそうです。
例えば、私がこうやってブログを書いているのもそうです。本当にわかっているか定かではないですが、私は今はこう考えているとか、私はこれを見て聞いてこう思ったとか言葉にしてみる。そこから、曖昧性を担保にこの言葉にはこんな意味もあるのではないかとかってさらに考えていくことができる。それも言葉の良さなんだなと思います。
だから、現時点ではこう考えているけど、100%正しいとは限らない。具体的に具体的にしていってわかったという気になって、判断して終わりではなく、言葉にすることで思考を進めるスキマを空けておくことが言葉の曖昧性を知っている糸井さんのメッセージなのかなと思いました。
だから、同じ本を定期的に、何度も何度も読んで考えていく。できたらこれまでの自分の考えと対比させて深まりや含みをもたせておく、そんな教育できないかなと思っています。「”今は”こう考えている」といった立場。
こういった言葉の曖昧さや多様性について考えていく一つとして、植松さんが最近書いてある読書することが大きいのかなと思います。
私もこれを機に、大学の頃に読んで感動した「思考の整理学」を読み直してみようと思いました。それについては、別の機会でかけたらなと思います。
また、番組「スイッチ」にはスタッフが書いた編集後記のようなブログがあります。
その中でこんなことを書いています。
こんなお二人が語りあったのは「ことば」のことでした。自分の中に「気持ち」はあるのに、それをどんな言葉にしても100%伝えることができない、という体験、皆さんもお持ちでしょうし、芦田愛菜さんも持っていて、それを糸井さんに伝えました。そこで糸井さんが語ったのは、「言いたいのに言えない、そんなときに言葉は生まれる」ということ、そして「言いたいのに言えない、その思いを忘れないこと」ということでした。なんと力強いメッセージでしょうか。「言いたいのに言えない」体験は、悩ましいだけではなく、いつか自分の心と身体を温めてくれる体験なんだと、私は解釈しました。たぶん聞く人によって、それぞれの解釈が出てくると思います。
この「いつか自分のことを心を身を温めてくれる存在である」と解釈しているところ、これが言葉を味わうこと、そして心が豊かになっていくことなのかなあと思いました。
言葉って本当にいいもんですね。
今後の課題:思考の整理学についてのレビュー
編集後記:言葉の奥深さについてブログを書き出してからさらに感じています。中学の国語の成績が2だったことを未だに覚えていることから結構引きずっているんだと思いますが、言葉とどう向き合っていくかは大切な視点なので今後も考えて発表していけたらと思います。
参考文献
 |
Q わたしの思考探究(1)
90,512円
Amazon |
 |
Q わたしの思考探究(2)
56,919円
Amazon |
 |
思考の整理学 (ちくま文庫)
562円
Amazon |