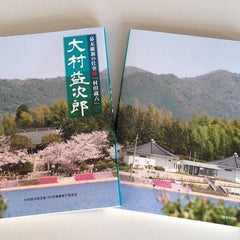藤村孝益は、村田蔵六(大村益次郎)の実父。
書簡紹介します。
内田伸先生の『大村益次郎文書』に載っていますが、だれも内容がわからないから放置されています。
この世に、私しか大村益次郎研究家はいないので、解説します。
○安政五年二月三日 藤村孝益より (『文書』185)
弥御安康の由、珍重に存候。
此方向も無別条罷過由候間、御安意可被下候。
昨年は書面も怠り、亦差越候も不埒に及候て、御案被成候段、渡辺よりも承知致候。
今年よりは、毎時差出し可申候。
其方よりも、御送り可被下候。
宮市駅迄相届き候得は、夫よりの賃銭は此方より相調可申候。
昨年御送の請取、別紙の通り御引合可被下候。
先は時気御保養専一に存候。頓首。
二月三日
尚々、拙者儀も追々気分宜敷候故、一両年は御気遣有之間敷候。
尚また扶持方御送り被下候故、別て安楽に罷過候間、萬々御気に被懸間敷候。 已上。
孝益
蔵六様
尚また送り金の儀は不埒無之様撫育仕、組立追々可申進候。已上。
{解説}
文中の「渡辺」は、おそらく渡辺源左衛門。鋳銭司の人。
「宮市」は、現防府市。交通の要衝地で、ここまでは江戸からの書簡は届いても、僻地の鋳銭司までは別料金がかかるので、三田尻~鋳銭司の郵送料はこちらが出します。と言っているのです。