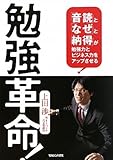こんばんは。学習アドバイザーの佐藤正治です(^^)
先日、弟が1歳になる息子を連れて遊びに来ました。
それにしても赤ん坊の反応というのはおもしろいですね。
ちょうど離乳食を与えているところなのですが、
好き嫌いが非常にはっきりしています。
嫌いなものは口を閉じて食べようとしません。
隙を見て口を開けたところに流し込んでも、はき出してしまいます。
それに対して大好きなミルクの時はまるで違います。
ほ乳瓶を渡すと、それこそ息もつかずに飲み干してしまいます。
これを見ると本当に人間というのは気持ちいいことには一生懸命に
なるけれども、嫌なことは逆にしないことに一生懸命になるものだと
思えます。
当たり前のように思えますが、このことは重要です。
「勉強が大好き!」という子は少ないと思います。
(私としては勉強することの面白さを少しでも味わって欲しいと
思うのですが(^_^;)
好きでもないことを無理にすることは苦痛でしかありません。
人間は苦痛から逃れようとする生き物ですから、
好きでもないことを続けるのは非常に難しいのです。
では、どうすれば続けることができるのか?
はい、そうです。好きになれば続けられます(^^)
「だから、勉強が好きになれないから苦労しているんじゃないか!」
という怒りの声が聞こえて来そうですが、
実は好きになる方法があるのです。
その一つが「脳を騙す」事です。
どういうことかというと好きなことと嫌いなことを頭の中で結びつけてしまうのです。
このことは数多くのスポーツ選手のイメトレの指導をされている
西田文郎さんのセミナーで知りました。
西田さんはお酒が大好きなのだそうで、仕事の後、帰りの電車で
一杯お酒を飲むのが何よりの楽しみなのだそうです。
その時、「仕事のおかげでこんなにおいしいお酒を飲むことができる」
と感謝しながらお酒を楽しむのだそうです。
これを繰り返すうちに、楽しくお酒を飲むことと仕事をすることが
結びついて、仕事そのものを楽しいものだと
思えるようになっていったそうです。
このように楽しいこと、好きなことと大変なこと、嫌なことを結びつけることで、嫌なことを好きなことと脳に思いこませていくのです。
勉強で言えば、
「好きなチョコレートを一粒食べたら、必ず机に向かい教科書を開く」
とか
「好きな音楽を聴きながら漢字練習をする」
といった、好きなことを勉強を始める時にすることで条件付けるのです。
但し、ここで気をつけなければならないのは、
「好きなこと」といっても余り長引くものは選ばないことです。
「テレビゲームが好き!」という人が
「勉強の前に必ずゲームをする」というように条件付けたら、
勉強開始までに時間がかかりすぎてしまいますから(^_^;
ちょっとしたことを勉強開始の時の「儀式」にしてしまうのです。
確かにすぐに「嫌い」→「好き」とはなりませんが、
少なくとも段々と「嫌い」という意識は減っていくはずです。
なかなか勉強をする気にならないなぁという時は試してみてください。
あ、「儀式」としてとっておきの方法を一つ、最後にお伝えしましょう。
勉強前に好きな子の写真を見ることです(^^)
私も学生時代にこの手を使って頑張った時があります。
好きな子を見ている時の頭の中の「気持ちいい」という感情は
強烈ですからね(笑)
行事の時に撮影係だったことがこれほどうれしかったときはないですね。
堂々と写真を撮りまくれますから(笑)
あ、くれぐれも眺めすぎて、
勉強が手につかないということにならないように気をつけてください。
劇薬は取り扱いに注意しないと(笑)