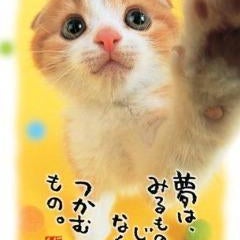室町無頼
ちょっとネタバレます。
1461年応仁の乱のちょっと前、大飢饉の為に民は税を払えず、高利貸しから借金をしても立ち行かない人たちで溢れ、借金のかたに女が連れて行かれ、更に疫病も流行り、路上は死者で溢れ、役人は生き残った民に死体を賀茂川に放り込ませ、川べりには八万人の死者が積まれていた。
しかし、当時の貴族の権力者は、飢えに苦しむ民を虫けらと呼び、自分たちの懐を肥やす事しか考えずに、増税すればいいという始末で、時の帝足利義政(中村蒼)は浮世離れしていて、何も考えてはいなかった。
そんな中、己の才覚と腕で色んな集落を訪ね、金貸しや貴族などの暴挙に対する助言を与え、明日をも知れぬ民に生きる力を与える自由人、蓮田兵衛(大泉洋)はこの世の中に秘かな不満を抱えていた。
強引な借金取りの僧兵集団に身を置く、天涯孤独の六尺棒使いの少年、才蔵(長尾謙杜)は僧兵達に暴力を振るわれ、何もかもに絶望していた。
300人の荒くれ者を抱える、洛中警護役の首領の骨皮道賢(堤真一)達に才蔵は捕まり、彼らのあじとにある木に縛られて、殺されそうになっていた。
昔馴染みの道賢に呼び出された兵衛は、とある村が一揆を企てているようなので、止めるように依頼を受ける。
兵衛は報酬の交渉の時に、道賢にそこのサル(才蔵)をやると言われ、縄に繋がれたまま連れて行く事にする。
反抗的な才蔵だったが、徐々に兵衛に懐き、縄もほどいての道中、二人は関所で通行税を払えずに、無理やり通ろうとする者が殺される場面に遭遇する。
兵衛は役人を斬って関所に火をつけ、そこにあった金を盗んで逃げてしまう。
道々才蔵に稽古を付けながら、道賢からの依頼のとある村に辿り着くと、才蔵が捕ったウサギを土産に、兵衛は借金を返せるだけの金を渡して、なんとか一揆を思い止まるよう諭して去る。
その後、兵衛は唐崎の老人(江本明)に才蔵を預け、六尺棒の修行を頼む。
すぐに過酷な修行を始める老人だが、才蔵は徐々に才覚を表し、2つの修行を成し遂げる。
すると老人は、新しい衣とを見事な六尺棒を渡し、最後の修行と言って、命がけの力比べを始める。
噂が広がり、食い詰めた武士まで挑んでくるが、才蔵は10日間挑む者を蹴散らしていき、ようやく老人に修行の終了を告げられる。
才蔵は兵衛を探し合流すると、才蔵に挑んだ3人の武者、赤間誠四郎(遠藤雄弥)、七尾ノ源三(前野朋哉)、馬切衛門太郎(阿見201)と再会して、才蔵と共に兵衛について行く。
兵衛は道賢から、大きな一揆を企てる者達を止める様依頼を受け、その集落に着くと、大勢の男たちが集まり一揆の相談をしていた。
旧知の中のような兵衛が皆の前に立ち、「皆の衆、待たせたな」と言い、貧困に喘ぐ民と一揆を起こす算段を始める。。。
めっちゃ面白かったです。
大泉洋史上一番カッコ良いい役かも。
そして才蔵役の長尾謙杜は、最初誰かわからないほどの汚い小僧で、老人の修行で腕が上がるごとに小ぎれいになっていく。
骨皮道賢役の堤真一は、洛中警護役に付いているものの、めっちゃ悪人顔で、有力大名の名和好臣役の北村一輝は気まぐれに村人を殺して、最後には兵衛に敵討ちに合う何ともな役です。
この蓮田兵衛なる人物は、初めましてだったので、ちょっと予習をしたのですが、史実に基づいてはいますが、民目線でかなりカッコよく描かれています。
応仁の乱(1467~1477)の少し前の飢餓がピークの頃、京都で発生した農民や民衆による大規模な一揆(寛正の土一揆)で、農民、武士などが参加し、次第に膨れ上がった群衆が、幕府の御所近くまで攻め込み、幕府は鎮圧に乗り出したが、混乱の中で多くの借金帳消しが実現したそうです。
映画では兵衛が、道賢との一騎打ちをしている間に、群衆が証文を燃やし、踊り狂う様を見て、ケガをした兵衛と才蔵はその場を去るが、このままでは収まらぬ道賢は兵衛を追い、もとより命を捨てる覚悟の兵衛が、才蔵の命を助ける様話し、河原で道賢が兵衛を打ち取る。
才蔵は兵衛の持っていたひょうたんを持って去って行き、道賢は横たわる兵衛の手から刀を外し、兵衛の髪に触れ涙を流す。
最後は皆がよくドラマにある旧知の武士の、どうにもできない一騎打ちって感じでしょうか。
でもこの頃って、時代的にホントかな~と思って観てました。
そしてテーマ曲が、ウエスタンと必殺仕置き人を足したような曲で、両方とも好きだったので、うわ~っと思いました。