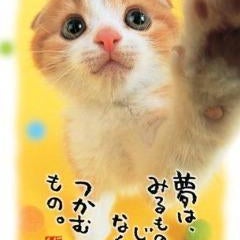以前冬至の記事に「いろは歌」について書くと言いました。
「いろはにほへと」は昔は数や音階等広く使われていました。
例えば、江戸の街を地区ごとに「いろは」の名をつけ、その地区の火消しに地区の名を使い、特に「め組の喧嘩」は有名で、歌舞伎の演目にも取り上げられた。
そして、明治時代に音階の「ドレミファソラシド」を「はにほへといろは」に置き換え使っていたが、母は戦時中に、敵性語なので「ドレミ」ではなく「はにほ」を強要されたと言っていました。
実は「ドレミ」はイタリア語で、第二次大戦でイタリアは同盟国で、敵性語ではなかったのですが、外国語っぽいものなら何でも“軽佻浮薄(けいちょうふはく)※”として一括りに敵性語としていた、なんともいい加減な訓示で、「いろは」になったそうです。
※考えや行動などが軽はずみで、浮ついているさま。
ちなみに「ハ長調」「イ短調」などは、「はにほ」の名残で今も使われています。
話を戻し、「いろはにほへと」は「いろは歌」と呼ばれ、47文字を全部使って七五調の意味のある歌にしたもので、作者、時代共にはっきりした事はわかっていません。
ただ、初めて文献に登場したのが1079年に仏典に登場したので、その辺りではないかと言われています。
いろはにほへと ちりぬるを
わかよたれそ つねならむ
うゐ(い)のおくやま けふこえて
あさきゆめみし ゑ(え)ひもせす
これを漢字に直すと
色は匂えど 散りぬるを
我が世誰ぞ 常ならむ
有為の奥山※ 今日越えて
浅き夢見じ 酔ひもせず
※有為とは、さまざまな因果関係・因縁によって、起こる現象を意味する仏教用語だそうで、この歌の場合、「無常の現世をどこまでも続く深い山」にたとえたものだそうです。
もう一つ「けふ」を「今日」と読むのは、旧仮名遣いだからで、たとえば「蝶々」は「てふてふ」と書きます。
歌の意味には色々な説があって、明確なものはないのですが、仏教の思想を歌にしたというのが一般的らしいです。
①香りも良く、美しく咲き誇っている花も やがては散ってしまう
②この世は誰にとっても 永遠ではない
③無情と言える現世の深い山を 今日超えれば
④はかない夢を見ることも 現世に酔いしれることもないだろうに
個人的にはちょっと説教臭い、ネガティブな感じがしました。
で、仏教用語で言うと、
①は「諸行無常(しょぎょうむじょう)」
この現実の世界のあらゆる事物(森羅万象)は、すべて本質も姿も作り出されたもので、 絶えず変化し続け、決して永遠のものではないということ。
②は「是生滅法(ぜしょうめっぽう)」
この世のすべてのものは、常にとどまることなく移り変わり、生きているものは必ず死ぬという考え方。
③は「消滅滅已(しょうめつめつい)」
生と死を超越して、煩悩が無くなった安らぎの境地である涅槃に入ること。
④は「寂滅為楽(じゃくめついらく)」
すべての苦しみ、悩みから離れた絶対に安静で、真の楽しみの境地であるということだそうです。
自分で調べてなんですが、何だかどうでも良くなってきた。。。
で、このいろは歌には暗号が隠されていると言われていて、古い文献では五七調ではなく、七文字ごと書かれているものがあり、
いろはにほへと
ちりぬるをわか
よたれそつねな
らむういのおく
やまけふこえて
あさきゆめみし
えひもせす
の一番最後の文字をつなぐと「とかなくてしす」、漢字に直すと「咎(とが)なくて死す」となり、「私は無実の罪で殺される」となります。
なので、これは冤罪にあった人が、殺される前に詠んだ歌で、遺恨が込められているので、いろは歌は呪いの歌とか、いろは歌の本当の意味は怖いと言われているそうです。
そんないわれもあったりするので、作者が菅原道真説や、小野篁説や、柿本人麻呂説、更にはキリスト説など、様々な不遇な時期を過ごした偉人の作と言われるのです。