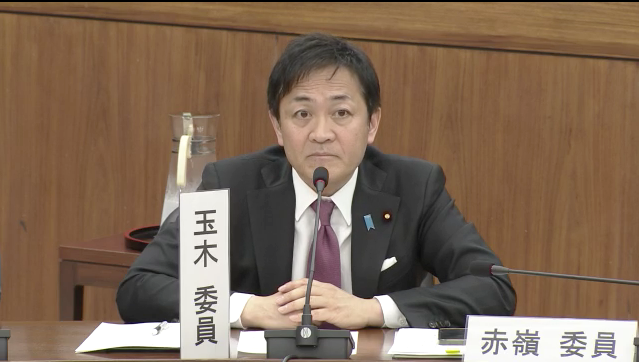全国の国民民主党の仲間の皆さんへ
連日、暑い日が続く中での活動に敬意を表します。今朝も街頭に立っている仲間もいることでしょう。熱中症など体調には十分に気をつけてください。
さて、国内外で政治的混乱が生じ、閉塞感と政治不信が漂う今こそ、国民民主党結党の原点の思いに立ち返ることを皆さんに呼びかけたいと思います。
私たちは、2020年、批判・反対に終始する政治から脱し、新しい日本を作るため、「つくろう新しい答え。」を旗印に、「対決より解決」を掲げて設立し、政策本位で各種課題に取り組んできました。この姿勢はこれからも変わりません。
昨年末に自民党の派閥の裏金問題が発覚し、自民党政治に対する不信感が極度に高まりました。これを容認することは私たちの掲げる「正直な政治」に反します。しかも、あれだけの事態を起こしておきながら、自民党が先の国会で成立させたのは抜け穴だらけのザル法でした。そして、一部の野党は、そんなザル法の成立に助け舟を出す始末でした。
他方、期待を担うべき野党第一党は、我が国を取り巻く安全保障環境が厳しさを増す中で、自衛隊を憲法違反だと主張する政党との繋がりを深めています。また、地政学的なリスクの高まりによるエネルギーの自給体制の強化や、AIの活用により電力消費量の増大への対応が求められる中で、原発ゼロ政策を依然として綱領に掲げています。
こうした政治状況の下、多くの良識的な国民は、どこにも持って行きようのないもどかしい思いを抱いているのではないでしょうか。
私たちは、そんな国民の思いを受け止めることができる存在でなければなりません。
「改革中道」
私たちの目指す「中道」とは、自分の考え方や価値観だけで物事を裁かないことを意味します。つまり、異なる意見も認めたうえで、熟議を尽くし、どのように結論を見い出すかという議論の作法です。中道とは民主主義そのものと言っても過言ではありません。
私たちのこの考えは、あたりまえ過ぎて面白みがないかもしれません。しかし、耳に聞こえの良い極論や二元論の中に課題を解決できる真の答えはありません。SNSの普及によって極論や陰謀論が蔓延しやすくなっているからこそ、この中道の理念が重要なのです。
データとファクト(事実)に基づき、国民のための現実的な政策を模索し実現を図る、そんな私たちの基本姿勢が今の日本に必要なのです。
かつて、日本は「政治は三流、経済は一流」と言われた時代がありました。しかし、政治がダメなら経済もダメになってしまうことを、この30年は証明したのではないでしょうか。
今、私たちが目撃しているものは自民党の危機ではなく、日本の危機です。
既存の政治の枠組みを変える「改革」の時が来ています。
そして、古い慣習、因習を変えていけるのは、極論ではなく、データとファクトに基づく冷静な議論です。
「新しいあたりまえ」
私たちは、非現実的な極論や、紋切り型の正論ではなく、冷静な議論で変えるべきものを変え、日本に「新しいあたりまえ」を作っていかなくてはなりません。そのためには、まさに、私たちの「偏らない現実的で正直な政治」が必要なのです。
大きな声をあげることはしないけれど、この国の未来に危機を感じている多くの良識的な日本人の声に応える政治を実現していきましょう。
そのために、私たちは強く大きくなる責任があります。
がんばりましょう。
この夏を、国民の思い受け止め、そして、私たちの思いを伝える夏にしていきましょう。