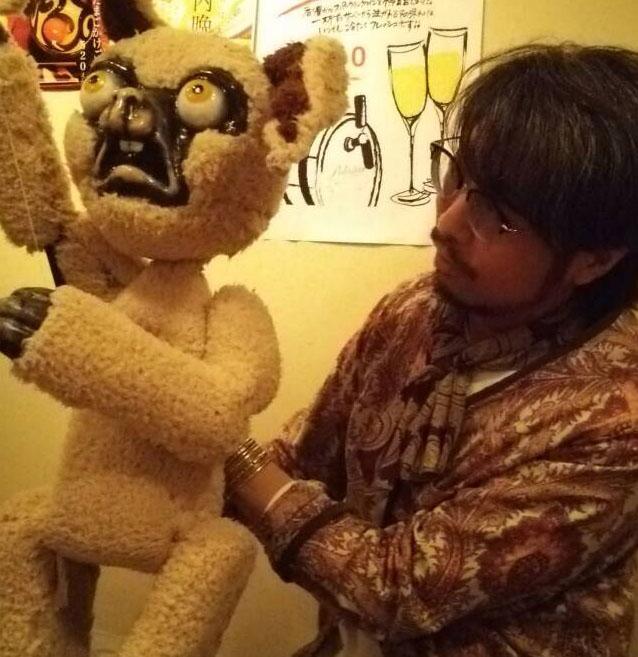「子」とは孔子のことである。
子はいった 「<仁>たる者だけが人を愛し、憎む術を知っている。」
一方で、
子はいった 「<仁>たる者は憎悪を捨てるものだ。」
匠は尋ねた 「先生のおっしゃることは矛盾しているようですが・・・
これは言葉の限界を意味しているのでしょうか。」
賢者A 「だから言葉なんて意味ねーつったんだよ。」
子はいった 「身振りと同様に、言語の正しい使用も、
効果的な行為を為すのに、必須の構成要素である。
正しい言語は単に便利な付属物ではなく、
儀式を執行する上での本質に関わる。」
匠は尋ねた 「子のおっしゃることはなんとなく分かります。
でも<儀式>とは何ですか。ちょっと不気味ですね。」
賢者A 「自分が楽しくなけりゃ意味ねーよ。
自分が「楽しい」と思う感覚を掴むことが大事なんだよ。」
子はいった 「目的成就のためにいかなる努力も計画も必要ない。
ただ儀式的動作を始めるだけでよい。」
匠はいった 「ますます不気味ですね。」
賢者A 「別に不気味でも何でもねーよ。
楽しめば奇跡が起き続けるんだよ。」
子はいった 「人間の生は全体としてひとつの広大で自然発生的な
聖なる儀式として現れる。
これこそが個人の生活よりも重要で、
唯一問題にすべきものなのである。」
匠は尋ねた 「個人の生活よりも重要なものがあるのですか。
まずは個人の生活からではないのですか。」
賢者A 「まったく、分かってねーな。おめえは。」
子はいった 「儀式とは<礼>の力である。
これが何よりもまず学ばねばならぬことだ。」
賢者A (何か言おうとするが・・・)
子はいった 「しかし、次の点には留意せねばなるまい。
儀式とは、人間の世俗的なものから遊離した霊を慰撫する
といった神秘的なものでは全くない。
霊はもはや儀式に支配された外的存在ではない。
儀式のうちで表現され、
儀式のうちで活性化されるものが霊なのである。」
匠 「なるほど・・・」
賢者A 「なかなかよく分かってるじゃん。このおっさん。」
子はいった 「<礼>とは道(タオ)の地図である。
道(タオ)を歩むことを出来ない者は、
錯綜したところを巡ってどこにもたどり着けず、
利や個人的な慰めの幻に惑わされて
当てどもなくさまようことになる。」
匠 (反省・・・)
賢者A 「その通り。結局は楽しいかどうかなんだよ。」
子はいった 「『どうしようか、どうしようか』
と常に問い続ける者でなければ、
私には手の施しようがない。」
*********************************
25年ほど前の文章です。
賢者A批判としても読んで下さい、と当時のボクの注釈が入っております。笑
『孔子 ―聖としての世俗者』H.フィンガレット(平凡社)
という本に感銘を受けてこれを書いています。
孔子のイメージがかなり変わりましたね。
(これは西洋における「自由」批判でもあって、
つまり、西洋というのは常に「選択」という迷いの中にいる。
西洋の路線は「選択の自由地獄」なわけですね。笑
西洋が陥る「思考の罠」と言えるのかもしれません。
その「自由からの脱却」を東洋ー孔子に求めた本だとボクは考えています。)
ここに出てくる『礼』というコトバは非常に魅力的な概念だと思います。
説明は難しいですが。
ボクは20代前半に当時「ニューエイジ」とか「精神世界」と呼ばれたジャンル?の老舗出版社で大学を中退して働いていた。当初バイトだったが、倉庫でそこの本を磨くだけで楽しかったのをよく覚えている。(出版社というのは返品された本を磨いてカバーをかけ直してまた書店に流通させるんですね)
当時「チャネリング」と呼ばれる宇宙イタコ(とボクは呼んでいた)が大流行しており、ボクはこの手の人達の、なんというんだろうか、「ポジティブの押し売り」のような感じが肌に合わなかった。(もちろんそうじゃない人もたくさんいましたよ)
といってUFO、超能力・・・などは大好きだったのであるが。。
この文章における賢者Aというのがいわゆる「ポジティブの押し売り」のような人です。笑
さて、それからボクに思考と感覚の大転換が訪れることになるのですが、
どういう経緯を辿ったかはこちらに。
あと、儀式についてはこれ(↓)も同じことについて語っています。
儀式化とは意識化と言ってもよく、言わば習慣化の逆ですね。
儀式が習慣に堕してしまえば元の木阿弥です。