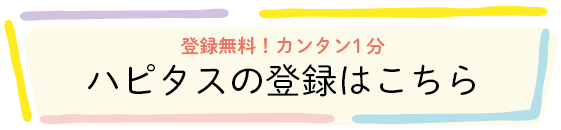”久留米を一望する高良大社(こうらたいしゃ)は、延命長寿や絶景で有名な筑後国一の宮。雨の中、初詣⛩”
おごめ~ん、大分のtakatch親方です(`・ω・´)ゞ
2024年(令和6年)の初詣、第3弾!過去2弾、宮崎県、大分県の神社を参拝。
<🐲2024年(令和6年) 初詣記事集>
- 📝宮崎県日向市「大御神社」初詣記事はこちら→https://ameblo.jp/takatch/entry-12834883755.html
- 📝大分市「賀来神社」初詣記事はこちら→https://ameblo.jp/takatch/entry-12835010335.html
今回は、福岡県久留米市の神社へ⛩
⛩「高良大社(こうらたいしゃ)」
山の中腹にある高良大社は、久留米市街地を一望できる絶景で有名✨
古代から「筑後国一の宮」として信仰を集めました。古代には朝廷から感謝されたり、江戸時代には藩主によって社殿を寄進されたり。
▽📝私は2016年秋に、友人と高良大社の夜景ドライブに行って以来、7年半ぶりの訪問。
今回は家族で初詣。日中の高良大社にお参りするは初。
▽雨と霧で参拝が難しい半面、荘厳な雰囲気が醸し出されて素晴らしい神社でした⛩
この記事では、「高良大社とはどんな神社?」「見どころはどこ?」などをご紹介。
- 最初に、高良神社の基本情報(ご利益や歴史、アクセスなど)をご紹介【第1章&第2章】
- 続いて、雨の初詣の写真とともに、境内のご紹介などで、あなたも一緒にエア参拝【第3勝】
<⛩今回の記事のみどころ3つ>
- 1600年以上もの歴史がある!朝廷や藩主からも愛される高良神社、必ず参ろう!
- 雨の参拝は、荘厳な雰囲気でエモい✨ただし、足元には気をつけましょう!
- 絶景や自然も必見!できれば、晴れた日の訪問がおすすめ☀
あなたも一緒に、高良大社をお参りしましょう(-人ー) 現地にご参拝される際のご参考お願いいたしますm(__)m
![]() 福岡県久留米市「高良大社」雨の初詣2024 ティザー映像はこちら→https://youtube.com/shorts/sBtHY4b7uu4
福岡県久留米市「高良大社」雨の初詣2024 ティザー映像はこちら→https://youtube.com/shorts/sBtHY4b7uu4
(1)高良大社はどんな神社?|「延命長寿」「絶景」で有名な筑後国一の宮
▽最初に高良大社のご利益や見どころ、歴史などを押さえましょう。これを知ってのご参拝がおすすめです!
⛩ご利益5つ|生活に関するものから、武運や芸能まであり。
- 厄除け
- 延命長寿
- 交通安全
- 武運長久
- 芸能の神
- 1~3は、生活全般にかかわるご利益として、古くから厚く信仰されました。
- 4は、蒙古襲来という日本の国難に打ち勝った際、天皇の勅使から「こうして無事に天下安泰になったのは、高良大社のおかげ」と告げられたことに由来です。
- 5は、高良大社が高良神楽という伝統芸能発祥の地にちなむものです。
⛩御祭神3柱
- 八幡大神(はちまんおおかみ)
- 高良玉垂命(こうらたまたれのみこと)
- 住吉大神(すみよしおおかみ)
▽拝殿、向かって右から、八幡大神、高良玉垂命、住吉大神を祀っております。
- 八幡大神は、応神天皇の化身と呼ばれます。弓矢の名人であることから、武運の神として信仰。
- 高良玉垂命は、朝廷から正一位(現在の総理大臣レベル)の称号をいただくも、その正体は現在でも論争になるほどの謎。江戸時代は、武内宿禰(たけしのうちのすくね)説が有力でした(Cf:武内宿禰といえば、福岡市の香椎宮、大分市の賀来神社にもゆかりあり)
- 住吉大神は、一般的には航海の神様。交通安全にも因みます(Cf:📝福岡市の住吉神社記事はこちら)
⛩歴史|1600年以上の歴史。筑後国一の宮として、江戸時代には藩主も篤く信仰。
- 鎮座は仁徳天皇時代(4世紀後半~5世紀前半)、創建は履中天皇時代(5世紀前半)。1600年以上の歴史あり。
- 古くは「高良玉垂命神社」と呼ばれました。延長5年(927年)にまとめられた神社の一覧表『延喜式神名帳』で、高良玉垂命神社が筑後国一の宮として記載されるほど、古代から信仰を集める神社です。
- 江戸時代には、久留米の藩主も篤く信仰。現在の社殿は、万治3年(1660年)に三代藩主の有馬頼利公が寄進されました。
- 明治時代には、近代社格制度にて「高良神社」として国幣中社に列格し、大正時代に国幣大社に昇格。
ご利益や歴史を踏まえたうえで、高良大社へ参拝しましょう⛩
- 第2章では、高良大社の住所や時間など基本情報をご紹介⛩
- 第3章では、2024年(令和6年)の初詣のスナップショットをご紹介📷
(2)高良大社の基本情報|住所や営業時間、地図など(2024年1月時点)
- HP→http://www.kourataisya.or.jp/
- 住所→福岡県久留米市御井町1
- 電話→0942-43-4893
- 時間→祈願の受付時間:午前9時~午後3時 ※正月の受付時間…大晦日:午後11時~翌午前2時、元日:午前6時~午後6時
- 交通→JR久大本線「久留米大学前駅」からタクシーで15分または徒歩約50分、西鉄バス(1・8)番利用「御井町」バス停から徒歩30分、九州自動車道「久留米IC」から車で約15分
- 駐車場→自家用車:約300台(無料)、バス:5台(無料)
▽地図
▽駐車場マップ(高良大社公式ホームページから拝借)
▽お正月三が日のみ、西鉄バスさんによる初詣臨時バスも運行(西鉄久留米~御井町~高良大社)。ご参考までに、時刻表と運賃表をご紹介(※現在は臨時バスの運行なし)
基本情報を踏まえたうえで、今回の雨の中の初詣風景を一緒にお楽しみください☔
(3)雨の中を参拝|雨と霧で、荘厳さもあり✨ ※足元に注意!
▽境内の写真。一緒にエア参拝しましょう(ー人ー)※各スポットの紹介は、高良大社ホームページから一部引用。
⛩三の鳥居・本坂(ほんざか)
131段の石段です。古くは、この石段より右奥(南側)にある「下向坂」が本参道であったかと思われますが、現在はこの石段が正面です(下向坂は後述)
石段がしんどいという方は、スロープカー(ロープウェイのように人を乗せて坂を乗り降りする乗り物)もございますので、ご活用ください🚙
⛩中門(ちゅうもん)・透塀(すきべい)
安永6年(1777)、七代藩主有馬頼憧公が寄進。鮮やかな朱色に魅了されます⛩
⛩本殿(ほんでん)、幣殿(へいでん)、拝殿(はいでん)【国指定重要文化財】
幅17m、高さ13m、奥行き12mの大きな本殿。神社建築としては、九州最大級の大きさ。
柿葺(こけらふき)、権現造(ごんげんづくり)の社殿は、江戸時代初期の特色をよくとどめています。
拝殿・幣殿の格天井絵(ごうてんじょうえ)は、狩野白信(かのうはくしん)が宝暦5年(1755)に描いたものです。
▽本殿の基礎部分に、三つ巴の紋が刻まれているのも趣あり⛩
▽雨と霧の本殿、荘厳な雰囲気をより一層感じます。
⛩境内社、摂社、末社
本殿以外にも、高良大社とゆかりのある神様が境内に多く祀られています。
境内の東側から西側(宝物殿方面)へ順番にご紹介⛩
⛩末社「真根子社」
- ご祭神は壱岐真根子命。武内宿禰の忠臣であるとされます。
- 昭和10年、五所八幡宮、日吉神社、風浪神社が合祀されています。
- 真根子社の社殿は、豊比咩神社の旧社殿と伝わります。
⛩摂社「高良御子社」
- 高良大社の御祭神:高良玉垂命の 御子神様たち9柱をお祀りしている摂社です。
- ご神徳→勝運の守護・厄除け・牛馬守護・安産病気平癒
- 例祭→11月13日 、月次祭→毎月13日
⛩末社「印鑰社(いんにゃくしゃ)」
- 明治6年、高良山麓の印鑰社をこの地に移してお祀りされました。
- ご祭神→武内宿禰
- ご神徳→延命長寿・厄除け・追難除け
- 例祭→11月13日
⛩境内社「市恵比須社」
- 夫婦の恵比須神像がお祀りされています。もとは筑後で最古の歴史を持つ府中(高良山麓、現在の御井町)の市の神として祀られていました。
- 九州経済圏全体の守護神とされている御神体の神像は「市指定文化財」です。
- えびす大祭→9月25日
⛩神輿殿
3柱の神々を表します。平成4年(1992)の、一六○○年御神期大祭時に修復されました。
境内は以上。次は、境内周辺の絶景や自然をご紹介!
⛰高良山の夜景
耳納連山(みのうれんざん)の最西端、標高312mの高台にある高良大社やその周辺では、久留米市街地を一望できます!
▽夜景(📝2016年秋に訪問時)
▽日中の様子…をお伝え予定も、今回は雨と霧のため、絶景を拝めず💦晴れた日にリベンジしよう!
▽晴れた日はこんな感じで、市街地や山々を一望できます⛰
▽展望台にはブランコあり。デートや家族ドライブにもいかが?
Cf: ![]() 「夜景✨」動画集→https://youtube.com/playlist?list=PLCP8H0iqHBwDGwrm6cbaKnsZ5nAIsxXyy
「夜景✨」動画集→https://youtube.com/playlist?list=PLCP8H0iqHBwDGwrm6cbaKnsZ5nAIsxXyy
🌳御神木|大きなクスノキ
▽※この画像は御神木ではございません。イメージ画像です(境内で撮影)
御神木である「高良大社の大樟」は、並立する二本の樟です。
樹齢数400年と推定され、樹高は1号・2号木ともに約23.5m。幹回りは1号木9mに対し、2号木は4.7mとスマートです。
Cf:![]() 「植物🌳」動画集→https://youtube.com/playlist?list=PLCP8H0iqHBwBL-w3qTVh9caUWhI-6o2Im
「植物🌳」動画集→https://youtube.com/playlist?list=PLCP8H0iqHBwBL-w3qTVh9caUWhI-6o2Im
🎍高良山のモウソウキンメイチク林【国指定天然記念物】
境内から帰り道、下向坂には、立派な竹林あり!
▽モウソウキンメイチク(孟宗金明竹)
金明竹(緑と淡い黄色が竹の節と節の間に交互に現われた竹)は全国にありますが、孟宗竹(もうそうちく)の変種とされる孟宗金明竹は、ここを含めて5ヵ所だけです(他には、福岡県岡垣町、宮崎県延岡市、大分県臼杵市、高知県日高村で観察。)

高良山でモウソウキンメイチクが発生したのは、昭和9年(1934)。その後、数が増えて約300本に。
▽高良山の孟宗金明竹は、地下茎(けい)から小枝に至るまで、一節ごとに左右交互に緑の縦縞があらわれます。
▽お日様に照らされた様子はまさに黄金の竹です✨(この日は雨でしたが☔)
雨の初詣写真は以上です。石段が滑りやすく危険でしたので、足元にはご注意ください。
一方で、雨と霧の神社は神々しい✨晴れた日中の高良大社にお邪魔したことがないため比較はできませんが、雨の高良大社も荘厳なり⛩
以上です(`・ω・´)ゞ最後までお付き合いいただきありがとうございましたm(__)m
![]() 「神社仏閣⛩」動画集→https://youtube.com/playlist?list=PLCP8H0iqHBwBN6zcqlWPYthJTkVIX3hsf
「神社仏閣⛩」動画集→https://youtube.com/playlist?list=PLCP8H0iqHBwBN6zcqlWPYthJTkVIX3hsf