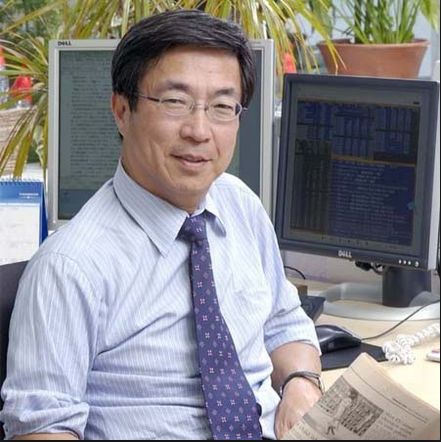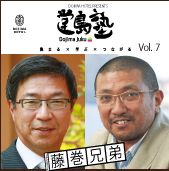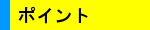一度信用されれば
横に広がっていく
廣瀬 恭久(ひろせ・やすひさ)氏
[エノテカ会長]

ワインビジネスは「契約書のない世界」と言われています。
だから大枚をはたけば誰でもおいしいワインを買い占め
られると思われがちですが、そうとは言い切れません。
この世界で何よりも大事にされるのは人間関係です。
だからこそ私のようなニューカマー(新参者)でも商売が
できた。そこに面白さがあります。
世界中にはおいしいワインがたくさんあり、それを日本にも
紹介したいという思いが高じて起業したようなものです。
とはいえ、当初は苦労しました。有力なワイナリー(ワイン
の醸造所)は日本の大手が囲い込んでしまっていて、
なかなか入り込めません。大半のワイナリーは家族経営で
横のつながりが強い。一度認めてもらえればそのコミュニ
ティーに入っていけますが、その最初のきっかけがつかめ
なかったのです。
当社はワインのインポーターであり、卸でもあり、そして自ら
リテール(小売り)まで手掛けてきました。
とりわけ「卸がショップをやるなんて言語道断だ」と周囲から
猛反対を受けました。でも、他人と違うことを恐れる必要は
ないのです。何か新しいことをやろうと思えば、必ず反発が
生じます。
店のデザインにもものすごく凝りましたよ。今でこそ似たような
業態の店はありますが、エノテカの個性は簡単にはまねでき
ません。苦しんで、苦しんでゼロから自分で作り上げたから
こその強みがあるし、その後に残るものがあると思っています。
日本人は味覚が敏感なのでワインを楽しむ素養があります。
今では老若男女がワインを楽しむようになりましたよね。
私は一人のワインラバー(愛好者)として、それが何よりも
うれしい。
当社は今年3月末にアサヒグループホールディングスの傘下に
入りました。
今後は後進を育てながら、毎日、うまいワインを飲んでいきたい
ですね。
(2015.06.15 号から)

「日経ビジネスDigital」 2015.06.15

キーワードは、 人間関係 です。
たとえ、企業間取引であっても、企業を構成しているのは
人間です。人間関係がスムーズでなければ、取引もうまく
回っていかないでしょう。
信頼関係は、契約書を取り交わすことで成り立つとは
限りません。契約に至るまでの相互信頼・相互信用が
根底になければ、契約はすぐに破棄されることになります。
人間関係の根底にあるべき、信頼・信用は、人種間や
民族間を問わず、成立するものだ、と信じています。
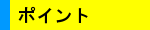
ポイントは、
世界中にはおいしいワインがたくさんあり、
それを日本にも紹介したいという思いが高じて
起業したようなものです
という心意気です。
最初から、儲けようという動機で起業したら、
上手くいかない、と思います。
廣瀬さんは起業の動機を次のように語っています。
「ワイン専門の輸入商社であるエノテカを創業したのは
1988年です。前年に父親が、経営していた半導体関係
の会社を売却。次は何をしようかと考えていたところ、
昔から好きだったワインに目が留まったのです。
ワインって1人でちびちび飲むというよりは、大勢で楽しく
飲むお酒です。ワインの周りには仲間がいて、ほほ笑み
があり、底抜けに楽しい。世界中にはおいしいワインが
たくさんあり、それを日本にも紹介したいという思いが
高じて起業したようなものです」
純粋な動機で起業した廣瀬さん(エノテカ)は、世の中に
認められたのだ、と考えています。
もちろん、起業後の廣瀬さんの頭からは採算性が一時も
離れることはなかっただろう、と推測しています。
せっかく起業し、東証2部銘柄にまで成長したエノテカが
倒産しては元も子もありませんから。ワイン愛好家にも
投資家にも多大な迷惑をかけることになります。
その後、本文にもあるように、アサヒグループホール
ディングスの傘下に入りました。
今後は、大きな後ろ盾を得て、財務面でも安心して事業を
継続していくことができるでしょう。
私はワインに限らず、アルコール類はほとんど口にしません
ので、詳しいことは分かりませんが、フランスワインのボルドー
やブルゴーニュはおいしいのでしょう。
もちろん、どんなものにもピンからキリまであるのは、
言うまでもありませんが。
カカオの含有量の多いチョコレート同様に、ワインには抗酸化
作用の強いポリフェノールが含まれていることは、知識として
理解しています。
ただし、ポリフェノールにも種類があるそうです。
チョコレートに関する記事が『日経ビジネス』(2015.06.15 号)
に掲載されていました。
(前掲誌 P.136)
カカオポリフェノールの主成分は、りんごに多く
含まれているポリフェノールと同じ「プロシアニジン類」
と呼ばれる物質である。プロシアニジン類は、
カテキンやアントシアニンなど、他のポリフェノールと
比較しても強い抗酸化作用を持つ。
ワインは飲んでいませんが、カカオの含有量70%の
チョコレートを定期的に食べています。
ちなみに、「エノテカ」とは、イタリア語で「ワインの箱、棚」
の意味だそうです。
藤巻隆(ふじまき・たかし)オフィシャルブログ-
人気のブログランキング
こちらのブログやサイトもご覧ください!
こんなランキング知りたくないですか?
中高年のためのパソコン入門講座(1)
藤巻隆のアーカイブ
本当に役に立つビジネス書