2006年に一般公開されてから4度目の東京公演だけど鑑賞するのは今回が初。
前回の2011年公演の時に初めて【魔法をすてたマジョリン】という作品を知ったんだけど、ニッセイ名作劇場での初演は1982年なんだってね。
初演から一般公開まで24年…(^-^;)
春休み期間中のマチネなので、お子ちゃまも沢山。
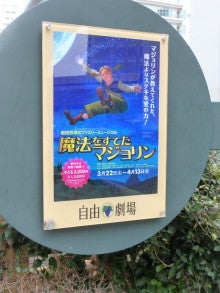
プログラムも購入。

キャストボード。

菅本さんや渡久山さんの名前を見ると、ファミミュ観に来たなぁって感じがします。
座席は二列ドセン。両脇が子連れではない大人で良かった(笑)
最前だと思ってたけど勘違いでした。
作品のあらすじは公式から。
この作品は、原作が無い完全な四季オリジナルなのかな?
四季オリジナルミュージカルにも、夢醒めやユタみたいに原作ありきの作品もあるからね。
先述の様に作品は今回が初見だし、作品の存在自体も知って間もないんだけど、昨年鑑賞した【劇団四季ソング・アンド・ダンス60 ようこそ劇場へ】でマジョリンの曲が歌われ、その曲を自分が大昔から知ってた事にびっくりしました。
ファミミュには作品毎にテーマ曲が必ず設定されているけど、マジョリンのテーマ曲『心から心へ』
♪きみの手とぼくの手を固くにぎり わけあおうぼくたちの心のぬくもりを~
音楽って不思議なもんで、幼稚園時代や小学校時代に教わって歌った曲って、大人になってもずっと覚えてるんですよね。
ソンダンでこの曲を聴いた時に、すぐに『この曲知ってる!懐かしい!』ってなって、そして初めてそれがマジョリンの曲だって知ると言う、なんだか不思議な出来事。
さて作品についてですが、ファミミュってどの作品も基本的に構成は同じなんですよね。
◇幕が開く前に登場人物が何人が出てきて緞帳の前で客席に挨拶して…
◇一幕でまずテーマ曲を作品の中心人物が歌う
◇同時に敵対相手にもテーマ曲がある事を教える
◇二幕に入ったらテーマ曲の歌詞が書かれたボードが吊り道具で出てきて、観客も一緒に練習(善悪対決シーンがある作品の場合)
◇悪者との対決シーンでは正義のテーマ曲と悪のテーマ曲を同時に歌ってぐちゃぐちゃにする(無い作品もあり)
◇悪者が改心するからと許しを乞うも正義はそれを許すまじとするけど、ここで主役が提案して結局許す事になる(ここにファミミュのテーマが隠されてる事が多い)
◇再び吊り道具でテーマ曲の歌詞が降りてきて、客席一同で合唱
◇ロビーでお待ちしてます!で出演者ロビーへ。
ファミミュの定番的流れってこんな感じですよね。全部同じだからこそわかりやすいんだろうけど。
またファミミュは、役者たちの台詞もかなりテンポが遅くまたハッキリと喋る上に、子供達に伝えたい部分(愛とか優しさとかそう言う、大人なら作品の流れから自力で汲みとる部分)を、わざわざ台詞に直して何度も何度も言うので、そう言った要素からファミミュってやっぱり子供向けだなって印象を受けるんだけど、悲しきかな、子供達はここまで感動的要素を台詞にして説明して貰っても結局理解出来ないんですよね。
そして、子供達に教えようとしてる部分が一緒に観てる大人の心を打っちゃって、結局大人だけが感動して泣いちゃう。
まさにこれぞ、ファミリーミュージカルのお約束(笑)
そんな子供達が素直に反応するのはやっぱり笑いの部分。
この作品に出てきた、悪の部分になる魔女達の名前の安直な事…(笑)


子供は素直に笑い、大人はあまりの安直さに苦笑…(笑)
中でもキモはやっぱりニラミンコですよねぇ。
魔女達の中で一番目立つんですが、男性が演じてるので必然的に『オカマ』と認識されてるキャラです。
オカマじゃなくて列記とした女性(キャラ)なんだけどね…(^-^;)
このニラミンコが、笑いのキモと申しますか、悪い人なのにイイ人感が凄く滲み出てると言うか、判りやすいズッコケキャラにこれでもか!と言う位徹してる。子供達はニラミンコの挙動に大笑い。
てか、子供達の大笑いって大人の大笑いと違って、無理に声を張り上げてるよね、自分が出る一番大きな笑い声を一生懸命出そうとしてる、と言うか。
これを演じたのが神保幸由さん、個人的にはファミミュの常連でありながらストプレも輸入ミュージカルもこなすベテラン俳優と言う印象ですが、何故かオネェを演じる神保さんって容易に想像出来ちゃうと言うか、面白いんだけどソツなくこなす印象…。
例えば同じニラミンコ役にキャスティングされてる牧野公昭さんみたいな、この人にこの役をやらせたらどんな演技をするのか想像しがたいオネェとか、夢から醒めた夢でデビルを演じる川原洋一郎さんみたいな完全にモノにしちゃってある意味一線を超えちゃってるオネェとかみたいな、観てみたい!と掻き立てられる気持ちに欠ける、と言うか…。
しかしまぁ、このニラミンコってキャラ、なんだかタイムボカンのボヤッキーみたいだなぁ、と思ったのはオレだけでしょうか?
キャラの中で一番目立つのはこのニラミンコだけど、個人的にはマジョリンの世話係ブツクサスも好きだなぁ。
オカシラスを前に、まるでお奉行様の元にひれ伏してる人みたいな言い回しでつらつらとマジョリンの許しを乞うシーンとか、魔女と言う西洋的な設定の中でやる時代劇的言い回しのギャップが面白いと思いました。
関心した舞台演出は、マジョリンが村に魔法をかけて村人を困らせるシーンなんだけど、まるでアニメを観てるかの様にスムーズな演出でした。まぁ…ポンピラパーン!と言う魔法の掛け声はどうかと思うけど(笑)
サクランボの木に魔法を掛けて、なってるサクランボが一斉にバタバタ落ちるシーン、村人の頭が一斉にハゲて、村人の服が一斉にボロになるシーン、建てたばかりの家が一気に崩れ落ちるシーン。
家が崩れ落ちるシーンは『人間になりたがった猫』でも妙にリアルだったよね。
服がボロになるシーンはどうやってボロに着替えたのかを見逃してしまったのが悔しい。リバーシブルか何か?
魔女なだけにフライングシーンもありますが、昔ながらの背中にピアノ線を付けるタイプのフライングでした。
その為か、マジョリンのフライングシーンが、大昔観たミュージカルピーターパンとダブって見えた。
リトマの様な最新式のフライング装置を使わない昔ながらの手法でもあんなに綺麗に飛べるのに、何故にユタと不思議な仲間たちのフライングシーンはあんなに不格好(衣装が装置に引っ張られてめくれあがってる)なんだろう?と毎度毎度フライングを観る度に思うわけです。
あと、マジョリンがダビットと共に薬草を取りに行くシーン…二人が並んで喋ってる後ろで、ブツクサスが二人の後ろ側を行ったり来たりしてるので何やってんのかなーと思ったら、二人の身体にピアノ線を取り付ける作業(笑)
ご丁寧に装着完了を、マジョリンの肩をパンパンと叩いてお知らせしてる。縁の下の力持ちですなぁブツクサス(笑)
魔女達と村人達の対決のシーン、左記の通り正義のテーマと悪魔のテーマのガチャガチャな合唱シーンなんですが、一旦は村人達は劣勢になって舞台下に降りるんだけど、そこで出しゃばって来るのがまたしてもニラミンコ…。
勝っちゃったのよーーーん!…とか、超いい人感滲み出てるじゃん(笑)
あと細かい点まで拘ってるな、思ったのがマジョリンや村人達が、愛とか友達とか親切とか、そう言う言葉を言う度に魔女達全員がいちいち反応してダメージ喰らって地味に苦しんでるんだよね(笑)
そんなお笑い要素が目立つ作品だったけど、感動を伝えると言う大目的の部分も良く出来てますね。
誰かの為に自分が何かをする、と言う人助けの大切さを訴える内容。
それは時には自分が犠牲を負う事になるかも知れない、それでもやる大切さを訴える内容。
感動しましたです、はい
しかしこの作品はファミミュの中でも特にテーマ曲を歌う回数が多かった印象。
そして、最後の決まり文句『ロビーでお待ちしてます!』が無かった。
お見送りの握手は…
ブツクサス…菅本烈子さん
プレッツェル婆さん…佐藤夏木さん
ダビット…渡久山慶さん
以上3人としてきました。
とにかく、若い役者さんよりも、オレの世代がマジョリンの曲に子供の頃から馴染みがある事を知ってる世代の役者さんとお話がしたかった。
自分より若い世代の役者さんに、懐かしい気分になったと言ってもわかってもらえないからね。
渡久山さんは多分自分より若いけど。
いい作品でした。
何に、と言うワケではなく、感動出来る作品でしたねぇ。
心温まりました。
この記事にポンピラパーン!