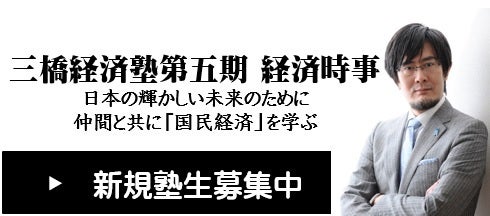
株式会社経世論研究所 講演・執筆依頼等、お仕事のご依頼はこちらから
三橋貴明のツイッター
はこちら
人気ブログランキング
に参加しています。
◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆
『お金の担保①』三橋貴明 AJER2016.9.20(7)
https://youtu.be/sjOa8Z-ezqA
◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆



◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆
明日は文化放送「おはよう寺ちゃん活動中」に出演します。
先日、9月17日の三橋経済塾第五期第九回講義で、柴山先生が、
「経済学者は『既に起きたこと』を学問化するだけで、目の前で起きている危機には対応できない」
という、まさに現在の日本は世界の経済問題を象徴するような「事実」についてお話下さいました。
学者が対応できず、誰がするかといえば、現場の経営者や政治家といった、「目の前の危機」に直面している人たちとのことです。
逆に言えば、「学者の言うこと」を聞き、目の前の経済危機に対処しようとしたとき、間違うケースが少なくないという話です。もはや今更感が強いですが、
「デフレは貨幣現象」
という「学者(岩田規久男教授など)」の主張に従い、いわゆるリフレ政策が行われた日本、厳密には日銀の金融緩和はやるものの、反対側で財務省主導の緊縮財政に屈した日本は、結局、三年半が経過したにも関わらず、未だにインフレ率がマイナスという惨状になってしまいました。
ちなみに、昨日のエントリー「内部留保とデフレーション 」において、「バブル膨張と崩壊、デフレ化のプロセス」を解説しましたが、あれは別にどこかの学者に教えてもらったわけではありません。
単に、80年以降の国家のバランスシート、GDPの動きから、バブル崩壊後の日本における、
「国民が借金してまで買った資産価格が暴落するという憂き目に会った。資産価格が下落しても、銀行から借りた借金の額は変わらない。我々国民は「合理的」に借金返済や銀行預金に走り、その分だけ消費や投資という「需要」が減り、そこに緊縮財政が追い打ちをかけ、総需要不足に陥った」
ことが分かるという、データの動きを語ったに過ぎないのです。三橋貴明の「解釈」とやらではありません。本当に、上記の通りにデータが動いていたのです。
興味深いことに、上記の類の「論理的なバブル膨張と崩壊、デフレ化のプロセス」について、経済学者が語ることはほとんどありません。逆に、
「いや、三橋は間違っている! バブルとバブル崩壊は~」
と、異なるプロセスを示され、反論されたこともありません。要は、沈黙されるのです。
なぜでしょうか。
推測ですが、データを見る限り、上記のプロセス通りにバブル崩壊、デフレ化が進んだのは間違いないのです。とはいえ、上記を認めてしまうと、デフレは「総需要の不足」という事実を受け入れざるを得ないためでしょう。
そうなれば、主流派経済学者たちが嫌悪する「ケインズ的な有効需要(GDPのこと)の創出」という政策が正しいという話になってしまいます。
さらに、経済学の大前提である予算制約説(政府で言えば財政均衡主義)を放棄せざるを得なくなり、財務省が推進する緊縮財政は不可能になります。
というわけで、日本のみならず、世界的に上記のバブル崩壊、経済のデフレ化のプロセスは共有されず、デフレ対策は金融政策任せ。反対側で、財政は緊縮、同時に構造改革という奇妙な(というか、間違えた)政策が推進されてきたのですが、ようやく「静かなる大恐慌
」(柴山桂太)ならぬ、静かなる方向転換が始まっています。
『「財政拡大」へ静かに方向転換する主要国
http://jp.wsj.com/articles/SB12260954658240904189704582315243126192380
世界は何年にもわたって、中央銀行が経済成長てこ入れに向けあらゆる政策手段を動員してくれるのを頼みとしてきた。ところがいまや中銀の手段は限界に達し、今度は政府が静かに存在感を増しつつある。リセッション(景気後退)終了以降で初めて、先進国は一斉に緊縮財政から積極財政へと軸足を移し始めた。
こうした動きは、「どれほど大きな価値を持つかがあまり理解されていない2016年経済動向ランキング第1位」かもしれない。財政出動の規模は金額としては少ないが、政治の流れが大きく変わったことを示唆している。(中略)
財政政策の転換は気づかれにくい。なぜなら、政府は少なくとも公約上は債務削減に尽力する姿勢を維持しているからだ。だが数字を見ると、実態は公約通りではないことが分かる。米国、日本、英国などの主要国では、2016年の財政赤字が前年比あるいは当初目標比で増える見通しだ。JPモルガンのエコノミストらは、今年は09年以来初めて財政政策が先進国の経済成長率の押し上げ要因になるとみている。(後略)』
後略部で、ピーターソン国際経済研究所のヤコブ・キルケゴール氏が、
「低成長が長期化すると、支出を拡大したいと考えるのが政治家の習性だ」
「その意味でわれわれは基本に立ち戻ったのだ」
と、述べていますが、現実に目の前で起きていることを理解すれば、基本に立ち戻らざるを得ないという話なのでしょう。
学説や理論、仮説、モデルといった経済学者たちが好むロジックではなく、目の前の危機に臨機応変に対応しなければならない時代が訪れたのです。世界で最も長期間、デフレーションに苦しみ、多くの人々が貧困化した我が国は、世界に率先して「学者理論」を捨て去らなければなりません。
さもなければ我が国のデフレは続き、10年後の日本は「取るに足らない弱小国」と化しているでしょう。
「学者理論を捨て、現実に対処しよう!」にご賛同下さる方は、↓このリンクをクリックを!
人気ブログランキングへ
◆本ブログへのリンクは以下のバナーをお使いください。

◆関連ブログ
◆三橋貴明関連情報
Klugにて「三橋貴明の『経済記事にはもうだまされない』」
連載中
新世紀のビッグブラザーへ ホームページ
はこちらです。
メルマガ「週刊三橋貴明~新世紀のビッグブラザーへ~」
は↓こちらです。

