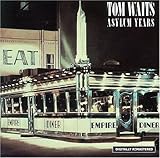フランス共和国首相、Francois Fillonの依頼を受けて社会分析局(Conseil d'analyse de la societe)が作成した、今回の金融危機の分析および対策レポートが数日前に出版された。(Luc Ferry, Face a la crise, Odile Jacob, 2009.)資本主義とグローバル化に対するヨーロッパの基本方針を知るうえで参考になると思うので、簡単にまとめる。
----------------------------------------------------
<現状分析>
市場経済のグローバル化が歴史から人間の意思を疎外する
市場経済のグローバル化により、全てのものが自由競争に飲み込まれるようになった。その結果、生き残るためには競争し続けなければならない、という事態が生じている。社会の流れは各成員間の自由競争のメカニックな結果でしかなくなり、歴史から人間の意思は疎外された。このような現代社会においては、政治がどれだけ力を持ちうるか、つまり歴史に人間の意思を介在させることができるかどうかが重要な問題となる。
我々は、他者への思いやりと関係性を基盤とする新しいユマニスムの時代に入った
資本主義は、集団から断絶した個人が匿名の存在として自由に収入を得ることを可能にした。その結果、個人は集団の拘束から解放され、独立した存在として生きられるようになった。このことは、神、国家、革命といった、集団を基盤とする伝統的「聖なるもの」が、個人の自己犠牲に見合うだけの価値を失ったということを意味する。独立と自由を手に入れた個人は、神、国家、革命といった抽象的な概念のためにみずからの命をかけることを拒否するのである。
伝統的「聖なるもの」が価値を失ったからといって、「聖なるもの」自体が消滅したわけではない。現代における「聖なるもの」、それはユマニテ(人間性)、つまり個々人の開花であり成熟である。人間には、それぞれが思い思いに花開く権利があり、またその権利は万人に対して保障されるべきである。かつて、神、国家、革命のために命をかけることが美徳とされたように、現在では全ての人のユマニテを守るべく戦うことが美徳とされる。我々は新しいユマニスム(人文主義)の時代に入った。我々は、「他者への思いやり(le sentiment)と関係性(le rapport)を基盤とする」ユマニスムの世紀にいる。このとき政治には、国民の一人ひとりが充実した私生活を送れるように尽力することが求められる。
<提案>
二つの優先課題 : 真に人間的な絆を結ぶ唯一の場所としての家庭への支援+失業対策のための企業支援
A. 家庭支援
政府は、国民が充実した私生活を送れるように尽力しなければならない。そのためにも、家庭への支援は不可欠である。まずは、第一子に対して月額70~80ユーロの給付金を与える、といった政策をするべきである。子供が一人生まれると家庭の購買力が10%ダウンすると言われる中で、この政策は出生率の低下防止にも寄与するだろう。また、家庭状況に関係なく全ての子供たちに平等に成功へのチャンスを与えるという意味で、各子供に対して2000~5000ユーロの給付金を与える、という案も考慮されて良い。この給付金の使い道を高等教育の費用のみに制限するか、あるいは完全に自由にするかでは、意見が分かれると思われる。
B. 企業支援
企業税制の簡素化を実現させることが急務である。
「公平さ」という課題 : どうすれば全ての市民が「同じ船」に乗っているように感じられるか
全ての経営者に該当するわけではないが、たしかに一部の経営者は法外な給与をもらっている。このような中で公平さを保つには、労資間の利益分配制度、パートタイマーの報酬アップ、若者や退職者など、今回の金融危機で最もダメージを受けた人への支援などを積極的に行わなければならない。
教育方針 : 市民教育、専門性、経済プログラム、哲学・文学教育での名作の位置づけについて再考する
市民教育の改革が急務である。文学、哲学、映画の名作を通して、市民として生きていくことの本質を教えなければならない。歴史的名作は生徒の興味を引きつけるし、また今日、集団として生きていくうえで必要となる倫理観について考えさせる教材としても最適である。
次に、経済教育を行っていくことも必要である。経済教育は、金融危機やグローバル化がもたらす拘束を理解させるうえで不可欠である。
さらに、文学的、哲学的名作や歴史に関する教育も充実させなければならない。消費社会の世界的広がりの中で、偉大な作品のみが現状に対する批判的距離をもたらしてくれる。
赤字削減という課題 : 世代間の連帯
今回の金融危機は、負債を国際へと転移し、我々の子供たちに多額の借金を負わせる可能性がある。このような事態を避けるためにも、国家の支出を減らし続ける必要がある。
グローバル化が進行する世界の中で、ヨーロッパに再び影響力を持たせる、という課題
ヨーロッパはグローバル化に脅威と憤りを感じている。しかし、ヨーロッパが世界の中で十分に政治的な力を発揮できていないのも事実である。このようななか、真に「文明的な政治(politique de civilisation)」を目指すフランスは、やはりヨーロッパというレベルを意識して政策を展開していかなければならない。
----------------------------------------------------
<感想>
議論が若干粗い。歴史を人間の意思によって導いていこうとするのは、いかにもヨーロッパ的。今年はじめのG20の対立も、独仏と英米の歴史観の違いが背景にあったのだろう。ユマニテを「聖なるもの」とするのは、今年の二月に出版されたドゥブレの『le Moment fraternite』の影響だろうか。(ドゥブレは、現代ヨーロッパの「聖なるもの」を人権としている。)個々人が充実した人生を送れるように政府が尽力すべき、という考え方には賛同できる。ただこれは、政府による市場への直接介入を即座に正当化するものではない。市場の流動性を確保しながらもそこからこぼれる人への保障は充実させる、労働市場に関して言えば、EUがスローガンとして掲げるFlexicurityという考え方が、やはりいちばん現実的ではないか。(関連リンク : Flexicurityについて
)