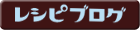きてくださってありがとうございます!
今回はまたプレモル工場見学に続きます、大人の遠足日記です。
先日サントリーさんとアイランドさん、かな姐さん、和美さん(たっきーママ)、サントリー山崎蒸溜所に行きました!
初めて降り立った山崎駅。
10分ほど歩くと見えてくる重厚で趣のある建物。
1923年にサントリーの創業者、鳥井信治郎が作った日本初のウイスキーの蒸溜所です。
緑の山に焦げ茶と白が映えてめちゃめちゃ綺麗。
山崎駅は京都やけど、山崎蒸溜所は島本町、大阪にあります。
(「山崎」という場所は大阪府と京都府に隣接した場所で、町名で言えば京都府乙訓大山崎町と大阪府島本町の両町付近を広範囲でさす場所らしい。知らんかった!京都かと思ってたわ)
島本町って私の高校の友達も何人か住んでるんですけど、とにかく水が美味しいことで有名で。行ったことなくても島本町=水がおいしいっていうのはみんな言うてたから、山崎蒸溜所があることに大いに納得しました。
ほんで今回、ここでウイスキーの勉強をしたことにより、帰って開発秘話とかいろいろ調べ始めたら楽しくて止まらんくなってしまって。
だいぶ長文になってしまいましたが、調べたりなんだり12時間以上かけて書いたんで(やる気出しすぎ)、お時間あるときに読んでもらえたら嬉しいです!
ーーーーーこの記事は約4分で読めます(※計った)ーーーーーーーーーー
まずウイスキーの歴史は…
から調べたら「蒸溜という技術は紀元前2000年頃のメソポタミアのバビロニア人が…」とかでてきたんで、さすがにメソポタミアってチグリス&ユーフラテス川ぐらいしか聞いたことないし手に追われへんわ!と思い
日本の歴史からでいきます!
最初にウイスキーが輸入されたのは1871年。(その前にペリーが沖縄に持ち込んではいる)
そのころ洋酒の消費は全然伸びず、日本の市場の1%にも満たなかったらしいです。
当時、本格的なウイスキーはスコットランドでしか作れないと信じられていたんですが、サントリーの創業者である鳥井信治郎は
ウイスキーの美味しさを知ってほしい。自分たちの手で、日本人の味覚に合った本格・本物のウイスキーをつくりたい!
という思いから、スコットランドでウイスキー製造技術を学んだ竹鶴政孝を迎え入れ、この山崎蒸溜所の建設に着手しました。(竹鶴さんはNHK連続テレビ小説「マッサン」で主人公のモデルとなった人です)
さっきより角度をつけてお送りしています。
何がすごいって、売れるかどうかもわからん(しかも既に外国産のウイスキーは全然受け入れられてない)、さらに製造から商品になるまで長い年月がかかるようなものを、莫大な予算と時間をかけて製造に踏み切るという勇気。
まさに無謀な挑戦。
「わしがウイスキーをつくるのは、日本の事業家が誰一人手を出そうとせんからや。日本でもウイスキーが作れることを実証したいんや」
彼は決然としてそう語ったという。(いやお前何を知ってんねん、て思われるかもしれんけど、サントリーさんのHPに載ってました)
無謀な挑戦をされた方↑
ただ音声が残ってるとか生前にご本人が原稿チェックしてるわけじゃないと思うし、もしかしたら「ええー!僕、そんな言い方してないんですけど!」てなる可能性もありますけどね。大阪の人って公の場でコテコテ関西弁を求められるから、こうあってほしい鳥井さんの理想像の台詞かもしれん。
で、その莫大な予算はどこから出したん?て話なんですけど
ウイスキーより前に鳥井信治郎が成功させたのが赤玉ポートワインで。
このポスターで有名なやつ。
「いいものを作ってもそれを知ってもらわないことには売れへんのや」
という信念のもと制作されたこのポスター、日本初のヌードポスターということで批判もすごかったらしいんですが、その反響はすさまじく。赤玉は驚異的な売り上げを記録し、ドイツで開かれた世界ポスター品評会でも1等に入選したそうです。
(モデルの女性はスタジオに6日間もカン詰めになり、1ポーズについて60枚もの写真を撮られ、最初は着物姿、次に肌着、最後は上半身裸というふうに、モデルの気持ちを自然に和らげムードを高めて撮られたそうです。後に親戚や家族に勘当されたとか)
ヌードにばっかり話題がいきがちやけど、モノクロ印刷の中でワインの赤色だけが浮かび上がる印刷技術開発もすごいところで。この手法は今でも矢沢永吉さんのプレモルのCMやポスターで使われてるやり方らしいです!オシャレですよね。
って話それたけど
ウイスキーを作ることに関して周囲は猛反対するなか 「自分の仕事が大きくなるか小さいままで終わるか、やってみんことにはわかりまへんやろ」と、鳥井さんはこの赤玉ポートワインの利益のほぼすべてを国産ウイスキー製造につぎ込みました。こわ!
こういった挑戦の数々がまさにサントリーの
の精神のもとになってるそうです。
そして長い年月をかけ、ついに初めての日本のウイスキーとして完成したのが1929年の「サントリーウ井スキー」、通称「白札」。
が、本場のスコッチの製法にもとづいて仕込まれた味や風味が「こげくさい」と悪評で売りあげは上がらず。翌年「赤札」も発売しますが、1931年には資金繰りの困難から仕込みを停止せざるを得なくなったそうです。
そこから諦めずに試行錯誤を重ね、1937年に日本人の味覚に合うまろやかな味のウイスキー、サントリーウイスキー「角瓶」を発売。
これが大成功を収めます!
蒸溜所の完成から10年以上経ち、原酒がさらに熟成されていたのも功を奏したそうです。まさに起死回生の救世主。
さらに1946年、敗戦直後の混乱期の中、「うまい、やすい」を謳った「トリスウイスキー」を発売。経済復興に拍車がかかる1950年代には逆に「出世してから飲む酒」の立ち位置で、格上の憧れのウイスキー「サントリーウイスキーオールド」を発売。
時代とニーズに合わせたウイスキーを次々と発売し、1984年に、初のシングルモルトウイスキー(=ひとつの蒸溜所で生まれたウイスキー原酒だけを組み合わせてつくるウイスキー)として「サントリーピュアモルトウイスキー山崎」を発売に至りました。
今ジャパニーズウイスキーが世界でどれだけ評価を受けているかはご存知の通りだと思います。
ちなみに最初に鳥井さんが竹鶴さんを呼び寄せた時はまだ「サントリー」じゃなく「寿(ことぶき)屋」っていう会社やったんですけど
ウイスキーに賭ける想いを引き継ぐという意味と、ジャパニーズシングルモルトウイスキーの門出を寿ぐ気持ちを込め、「山崎」の「崎」の右側
ここに、そっと「寿」を忍ばせているそうです。
漢字テストやったらアウト。(いや、めちゃくちゃ良い話で感動した)
こういうのって成功したから良いけど、挑戦した結果惨敗して、会社潰れて家族もバラバラになって路頭に迷って「やってみんかったら良かった…」って泣きながら膝をつくパターンもあるから恐ろしいですよね。
「やめときなはれ」(銅像立たんわ)
でもおそらく、鳥井さんとかウォルトディズニーみたいな人って(突然のウォルト)、そこで腐ることはなく「まだ何か手はあるはずだ…」みたいに諦めずもがいて最終的に成功に持っていくんやろうなと思う。
現に最初のウイスキーが全然売れんかった時点で、私やったら「世紀の大失敗や…ほんまゴメン」ってなって原酒全部流して工場閉めてたやろうし、そこで諦めてたら角瓶も生まれず、今のサントリーも無いわけで。
結局人生ってどんなにしんどいことがあっても、自分が終わりと決めるまで終わりじゃないし、成功した瞬間に、それまでの失敗は全部成功までのプロセスの1つになるんやろうな。さっきから何の話してるんこの人。まだ蒸溜所に足踏み入れてへん。
めちゃめちゃ長くなってしまったんで、ちょっと続かしてください!!
いつもありがとうございます!
----------------------------------------------
最後まで読んでくださってありがとうございます!
(気軽にコメントを頂けると嬉しいです。もしよければ「いいね」を最後に押して頂けるとめちゃくちゃ励みになります)
お手数ですが、最後に下のバナーをクリックして応援して頂けると嬉しいです。
------------------------------------
コメントは承認制ですが、無人の野菜売り場のような、個人個人の秩序で、ずっといい雰囲気を保って頂いてるので、読んで嫌な気持ちになるものじゃなければ完全公開です。質問の返信はコメント欄に書きます。気長にお待ちいただけると嬉しいです