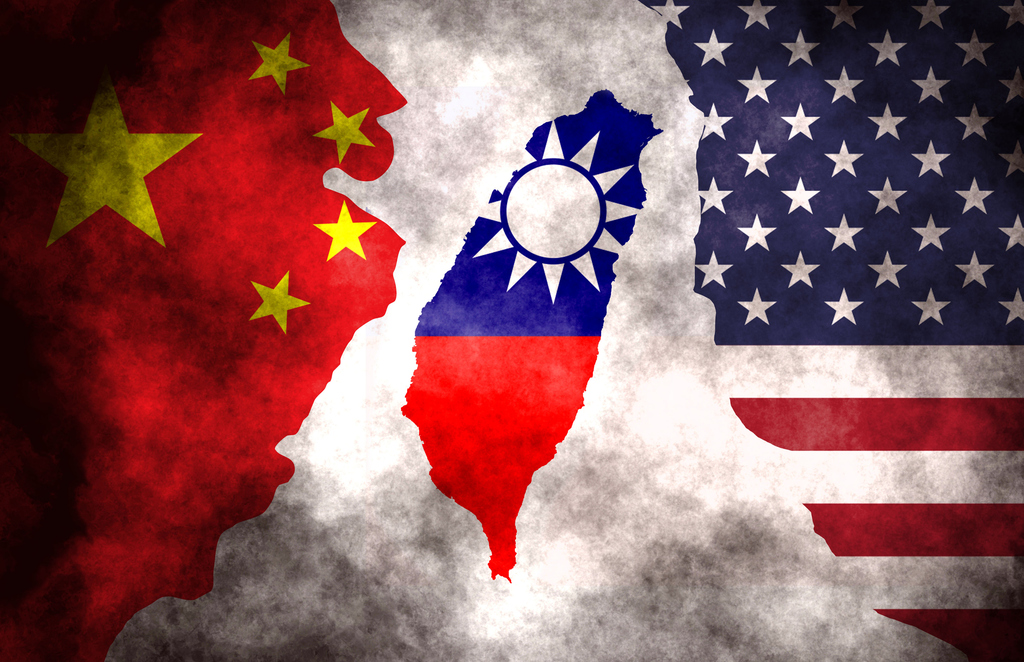◎台湾への武器供与を急ぐ米国 求められる台湾有事への備え
フィナンシャルタイムズ紙米中特派員のサヴァストプロが12月9日付け同紙解説記事で、台湾への武器供与のための100億ドルを含む今年の米国の国防権限法案を取り上げ、米国が台湾防衛への武器供与を迅速化しようとしていることを描写している。要旨は次の通り。
・米議会は、中国から台湾への圧力が強まる中、台湾への武器供与のための100億ドルを含む、8580億ドルの国防権限法案を可決した。
・米政府が台湾への武器に資金供与するのは初めてのことだ。これまでは、台湾は米政府の承認を待って米企業から武器を買っていた。
・北京は、台湾をめぐる緊張が高まる中、武器の供与に強く反対してきた。米中関係は、先月のバリ島でのG20サミットに際してのバイデンと習近平の初の直接会談にもかかわらず、緊張が続いている。
・北京が台湾への主張を強める中、台湾は米中間の最大の「フラッシュポイント(発火点あるいは引火点)」となった。中国軍は、台湾の防空識別圏により大量かつ頻繁に戦闘機を飛ばすようになっている。
・ナンシー・ペロシ下院議長の同職として25年ぶりとなる訪台に抗議して8月に中国が大規模軍事演習を実施し、初めて台湾上空にミサイルを飛ばすなどした後、緊張が急速に高まった。
・米議会は近年、新疆でのウイグル人弾圧から香港の民主化弾圧に至るあらゆる事項について、中国共産党に対し批判を強めている。
・共和党が下院の主導権を握る2023年には、中国に対し更に批判的な姿勢を取ると見られる。
・米政府は、同盟国、特に日豪との協力強化などによりインド太平洋地域での抑止力を高める一方、台湾への武器供給を遅らせる官僚的なハードルを下げようとしている。
・台湾への武器供給の過程の迅速化から、台湾が適切な後方支援を受けられるようにする必要性まで、台湾をめぐるあらゆる紛争の可能性に備えるべく米国がより迅速に行動することを求める声も高まっている。
・米海兵隊のデヴィッド・バーガー総司令官は、兵站の面で軍がより迅速に行動することを望んでいる、と述べた。
・同司令官は、米軍にはもっと速く動いてほしいとの希望を表明するとともに、
台湾に対する軍事行動は考えていたよりも難しいと中国に思わせるような態勢――兵站の準備を含め――を取らなければならない、としている。
米国の上下両院は、台湾への武器供与のための100億ドルを含む計8580億ドルに上る「国防権限法案」を可決した。サヴァストプロが指摘するように、米政府が台湾に対し、武器売却に変え、予算措置を講じて資金供与するのははじめてのことであり、画期的なことである。
振り返ってみれば、米国議会は台湾との外交断絶の4カ月後に、議会主導の下に、国内法「台湾関係法」(1979. 4.10)を制定した。その中で、「台湾の将来が平和的手段によって決定されることは、米国の重大関心事と考える」と述べた。そして、この「台湾関係法」は「防御的な性格の兵器を台湾に供与すること」を規定した。
「台湾関係法」は実質的に米国政府が米国議会に対して負う義務の形になっているが、台湾海峡の現状を維持する上で、決定的に重要な法的基盤となっている。上記解説記事も言うように、これまで、米国議会は、台湾政権側からの米国への武器購入の申し入れの希望を聞き、その希望に応じるか否かを決めてきた。
そのような旧来の対台湾への武器売却の方式を変えて、今回米国が100億ドル相当額の資金供与を行うこととなったのは、画期的変化ということが出来よう。まさに、これは中国からの圧力に抗する台湾を支援するための新たな試みと言える。
〇中国を抑止できる態勢構築は急務
中国にとっては、最近の習近平の発言にもあったように、台湾問題は「核心中の核心」の問題であり、「大きなレッドライン(超えてはならない一線)」である。今日、台湾海峡はインド太平洋において米中間の最大のフラッシュポイントであることは言うまでもない。習近平にとっては、台湾問題こそ自らの実績を国民に具体的に見せる上での一大優先課題となったと言っても間違いないだろう。
昨年8月にペロシ下院議長が訪台した際には、中国解放軍は台湾海峡において大規模軍事演習を行い、発射されたミサイルの内、5発は日本のEEZ(排他的経済水域)内に落下した。
米海兵隊のバーガー司令官は「米軍にはもっと早く動いてほしい。なぜなら、相手がいつ動くのか分からないからだ」と述べた。中国の対台湾軍事侵攻の可能性については依然として予断を許さないものがあり、米国の軍当局の内部でもその可能性の時期については一致していない。しかし、バーガーがいうように、「兵站などの面で米国軍が、より迅速に行動することを強く望んでいる。台湾への軍事侵攻は、実際は考えていたよりも難しいと中国に思わせるような抑止体制を早急にとらなければならない」という意見は傾聴に値しよう。
日本内部では、「台湾有事」の際にいかなる対応をとるか、米国のみならず、台湾当局とも種々の議論を重ねつつあるものと推測されるが、「台湾有事」は「日米同盟有事」であるとの観点から、遅きに失することのないような早急な対応が必要とされることは言うまでもないだろう。