モテキ (1) (イブニングKC)/久保 ミツロウ
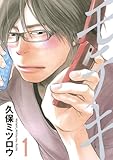
¥610
Amazon.co.jp
ほぼ日で話題に挙がっていた「モテキ」を一気読み。
自分がこれまで女の子と縁が無かった理由が少しだけわかった。
そして、だいぶ間違った方向に突き進んでしまったことも。
自分に魅力が無いから付き合えないのだと考えていたけど
魅力の定義を狭めすぎていた。
女の子を一般的というか、概念的に捉えていたかもしれない。
世の中で言われている仮説を鵜呑みにして、検証していなかった。
要は、考えていなかったということ。
それに、自信が無いから付き合えないなんて言っていたら始まらない。
他人を過大評価しすぎだし、さらに自分を過小評価しているのかもしれない。
まず俺が、小さな自分を受け入れてやらなければならない。
受け入れられなければ、思い切って飛ぶことだ。
女の子と向かいあった時、堂々としていられるようにと
何かしら実績を残したいと思っていた。
仕事とか、数学とか。
女の子と付き合うという目的に対しては、最適とはいえない手段ではあったけれども
自己完成という目的に対しては、悪くない手段だと思うので、数学はこれからも続ける。
ただ、女の子とは付き合いたいので
それだけではなくて、他のことも楽しむ余裕があってもいいかもしれない。
そして、自分を含めた人間を受け入れることだ。
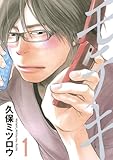
¥610
Amazon.co.jp
ほぼ日で話題に挙がっていた「モテキ」を一気読み。
自分がこれまで女の子と縁が無かった理由が少しだけわかった。
そして、だいぶ間違った方向に突き進んでしまったことも。
自分に魅力が無いから付き合えないのだと考えていたけど
魅力の定義を狭めすぎていた。
女の子を一般的というか、概念的に捉えていたかもしれない。
世の中で言われている仮説を鵜呑みにして、検証していなかった。
要は、考えていなかったということ。
それに、自信が無いから付き合えないなんて言っていたら始まらない。
他人を過大評価しすぎだし、さらに自分を過小評価しているのかもしれない。
まず俺が、小さな自分を受け入れてやらなければならない。
受け入れられなければ、思い切って飛ぶことだ。
女の子と向かいあった時、堂々としていられるようにと
何かしら実績を残したいと思っていた。
仕事とか、数学とか。
女の子と付き合うという目的に対しては、最適とはいえない手段ではあったけれども
自己完成という目的に対しては、悪くない手段だと思うので、数学はこれからも続ける。
ただ、女の子とは付き合いたいので
それだけではなくて、他のことも楽しむ余裕があってもいいかもしれない。
そして、自分を含めた人間を受け入れることだ。
だれかを犠牲にする経済は、もういらない/原 丈人

¥900
Amazon.co.jp
原丈人さんと金児昭さんの対談。
原さんについてはこちらにおもしろい記事があります。
原丈人さんと初対面
とんでもない原丈人さん第一部
とんでもない原丈人さん第二部
とんでもない原丈人さん第三部
とんでもない原丈人さん第四部 アフリカへ!
原さんの武勇伝が楽しみで買ったのですが
全体の趣旨も熱い!
こういうの好きです。
マネーゲームによりほんの一部の富める者と
そうでない者とに二極化してしまっている現状。
そんな世の中で人間は本当に幸せにはなれない。
では、どうすればいいのか?
という話です。
口先だけでなく、実際にバングラデシュで事業を行っているので
本気さが伝わってきます。
俺も人を幸せにしたいし、希望を与えられるような人間になりたい。
自分の能力を磨きつつも
幸せとか、不幸せということについて考えを深めておきたい。

¥900
Amazon.co.jp
原丈人さんと金児昭さんの対談。
原さんについてはこちらにおもしろい記事があります。
原丈人さんと初対面
とんでもない原丈人さん第一部
とんでもない原丈人さん第二部
とんでもない原丈人さん第三部
とんでもない原丈人さん第四部 アフリカへ!
原さんの武勇伝が楽しみで買ったのですが
全体の趣旨も熱い!
こういうの好きです。
マネーゲームによりほんの一部の富める者と
そうでない者とに二極化してしまっている現状。
そんな世の中で人間は本当に幸せにはなれない。
では、どうすればいいのか?
という話です。
口先だけでなく、実際にバングラデシュで事業を行っているので
本気さが伝わってきます。
俺も人を幸せにしたいし、希望を与えられるような人間になりたい。
自分の能力を磨きつつも
幸せとか、不幸せということについて考えを深めておきたい。
究極の鍛錬/ジョフ・コルヴァン

¥1,890
Amazon.co.jp
目次
第1章 世界的な業績を上げる人たちの謎
第2章 才能は過大評価されている
第3章 頭はよくなければならないのか
第4章 世界的な偉業を生み出す要因とは?
第5章 何が究極の鍛錬で何がそうではないのか
第6章 究極の鍛錬はどのように作用するのか
第7章 究極の鍛錬を日常に応用する
第8章 究極の鍛錬をビジネスに応用する
第9章 革命的なアイデアを生み出す
第10章 年齢と究極の鍛錬
第11章 情熱はどこからやってくるのか
現在読中。
・うまれつきの才能というものはないかもしれない。
・努力の積み重ねが大事
・努力の質が大事
といった仮説を様々な研究結果や逸話を挙げながら主張している。
今まで、プロになるには一万時間の訓練が必要だ、ということは読んだことがあったが
この本はそれ以上に深く掘り下げた説明がされている。
これを読んでいたら久々に、俺にもできるはずだって思えてきた。
読み終えたらまた報告します。
で。
読み終えました。
第1章 世界的な業績を上げる人たちの謎
偉大な業績を上げるには、単に経験を重ねるだけでは足りない。
しかし、だからといって、生まれつきの能力に差異があるわけではない。
第2章 才能は過大評価されている
音楽を学ぶ学生や、ジャックウェルチの例などから
特定の生まれつきの才能が果たす役割に対する
一般的な見方を再検討する必要がある、といえそうだ。
第3章 頭はよくなければならないのか
第1章の繰り返し
第4章 世界的な偉業を生み出す要因とは?
累計の練習量が多いほどより業績が上げられる。
達人は素人より多く、考え抜いた努力(究極の鍛錬)を行っている。
第5章 何が究極の鍛錬で何がそうではないのか
究極の鍛錬には以下の特徴がある。
(1)しばしば教師の手を借り、実績向上のため特別に考案されている。
(2)何度も繰り返すことができる。
(3)結果に関し継続的にフィードバックを受けることができる。
(4)チェスやビジネスのように純粋に知的な活動であるか、
スポーツのように主に肉体的な活動であるかにかかわらず、
精神的にはとてもつらい。
(5)あまりおもしろくない。
第6章 究極の鍛錬はどのように作用するのか
達人になるとより多くを認識できるようになる。
それは彼らが莫大な量の情報を
次々と長期記憶として覚えられる情報引き出し構造を手に入れているからだ。
つまり、専門分野の知識は達人の能力の中心的な要素といえる。
第7章 究極の鍛錬を日常に応用する
メンタルモデルをつくるべし。
メンタルモデルとは、これによって自分の専門分野がシステムとして
どのように機能しているのかイメージできるものだ。
第8章 究極の鍛錬をビジネスに応用する
省略
第9章 革命的なアイデアを生み出す
創造的活動で大成功をおさめる前に、長年にわたる徹底的準備期間が必要。
また高等教育は今日創造的問題解決にはなくてはならないものだ。
すべての達人とどうように必要とされる困難な仕事を進んで
取り組む気持ちがあるかどうかにかかっている。
第10章 年齢と究極の鍛錬
頭脳はかなり高齢になっても外部環境が求めるかぎり
新しいニューロンを増やすことができ
年齢とともに脳の可塑性も停止しない。
第11章 情熱はどこからやってくるのか
内的動機が重要。
そのためには取り組む課題の難易度に注意。
また、情熱自体、生まれつきなものではなく、
むしろ高い水準の技能と同じで、努力して身につけていくものだ。
原理としては、ある分野で偶然起こったちょっとした優位性が
一連の出来事を生み出し、それがのちにはるかに大きな
優位性につながっていく、というものだ。
さらに、偉大な業績を上げたひとはみな
その過程で大変な困難に遭遇している。
そのことに例外はない。
もし正しい訓練を行えば問題は克服できると信じているなら
少なくともこれまでにないほど素晴らしい能力を手に入れることができるだろう。
キモは第5章だけど、タイガーウッズ、ライス、
音楽専攻の学生たちの例によってわかりやすくなっている。
要は、考えて努力しろ、と。
適切な課題の設定、課題克服手段の考案に時間とエネルギーをかけるのが大事なのだろう。
考えるという行為の質が重要になってきそうだ。

¥1,890
Amazon.co.jp
目次
第1章 世界的な業績を上げる人たちの謎
第2章 才能は過大評価されている
第3章 頭はよくなければならないのか
第4章 世界的な偉業を生み出す要因とは?
第5章 何が究極の鍛錬で何がそうではないのか
第6章 究極の鍛錬はどのように作用するのか
第7章 究極の鍛錬を日常に応用する
第8章 究極の鍛錬をビジネスに応用する
第9章 革命的なアイデアを生み出す
第10章 年齢と究極の鍛錬
第11章 情熱はどこからやってくるのか
現在読中。
・うまれつきの才能というものはないかもしれない。
・努力の積み重ねが大事
・努力の質が大事
といった仮説を様々な研究結果や逸話を挙げながら主張している。
今まで、プロになるには一万時間の訓練が必要だ、ということは読んだことがあったが
この本はそれ以上に深く掘り下げた説明がされている。
これを読んでいたら久々に、俺にもできるはずだって思えてきた。
読み終えたらまた報告します。
で。
読み終えました。
第1章 世界的な業績を上げる人たちの謎
偉大な業績を上げるには、単に経験を重ねるだけでは足りない。
しかし、だからといって、生まれつきの能力に差異があるわけではない。
第2章 才能は過大評価されている
音楽を学ぶ学生や、ジャックウェルチの例などから
特定の生まれつきの才能が果たす役割に対する
一般的な見方を再検討する必要がある、といえそうだ。
第3章 頭はよくなければならないのか
第1章の繰り返し
第4章 世界的な偉業を生み出す要因とは?
累計の練習量が多いほどより業績が上げられる。
達人は素人より多く、考え抜いた努力(究極の鍛錬)を行っている。
第5章 何が究極の鍛錬で何がそうではないのか
究極の鍛錬には以下の特徴がある。
(1)しばしば教師の手を借り、実績向上のため特別に考案されている。
(2)何度も繰り返すことができる。
(3)結果に関し継続的にフィードバックを受けることができる。
(4)チェスやビジネスのように純粋に知的な活動であるか、
スポーツのように主に肉体的な活動であるかにかかわらず、
精神的にはとてもつらい。
(5)あまりおもしろくない。
第6章 究極の鍛錬はどのように作用するのか
達人になるとより多くを認識できるようになる。
それは彼らが莫大な量の情報を
次々と長期記憶として覚えられる情報引き出し構造を手に入れているからだ。
つまり、専門分野の知識は達人の能力の中心的な要素といえる。
第7章 究極の鍛錬を日常に応用する
メンタルモデルをつくるべし。
メンタルモデルとは、これによって自分の専門分野がシステムとして
どのように機能しているのかイメージできるものだ。
第8章 究極の鍛錬をビジネスに応用する
省略
第9章 革命的なアイデアを生み出す
創造的活動で大成功をおさめる前に、長年にわたる徹底的準備期間が必要。
また高等教育は今日創造的問題解決にはなくてはならないものだ。
すべての達人とどうように必要とされる困難な仕事を進んで
取り組む気持ちがあるかどうかにかかっている。
第10章 年齢と究極の鍛錬
頭脳はかなり高齢になっても外部環境が求めるかぎり
新しいニューロンを増やすことができ
年齢とともに脳の可塑性も停止しない。
第11章 情熱はどこからやってくるのか
内的動機が重要。
そのためには取り組む課題の難易度に注意。
また、情熱自体、生まれつきなものではなく、
むしろ高い水準の技能と同じで、努力して身につけていくものだ。
原理としては、ある分野で偶然起こったちょっとした優位性が
一連の出来事を生み出し、それがのちにはるかに大きな
優位性につながっていく、というものだ。
さらに、偉大な業績を上げたひとはみな
その過程で大変な困難に遭遇している。
そのことに例外はない。
もし正しい訓練を行えば問題は克服できると信じているなら
少なくともこれまでにないほど素晴らしい能力を手に入れることができるだろう。
キモは第5章だけど、タイガーウッズ、ライス、
音楽専攻の学生たちの例によってわかりやすくなっている。
要は、考えて努力しろ、と。
適切な課題の設定、課題克服手段の考案に時間とエネルギーをかけるのが大事なのだろう。
考えるという行為の質が重要になってきそうだ。
中3の時のクラスのメンバーで同窓会。
成人式以来5年ぶり。
今回は、大学院受験しまっせーと宣言してきた。
これで落ちたらチョーカッコ悪い。
絶対合格する!という気持ちが強まればいいのだけれども。
今、一番強いのは、今の状況を何としてでも変えたいという気持ち。
でもそれだけなら、数学である必要はない。
なぜ数学かといえば、一つは数学自体の魅力。
美しさと、直感とは異なる結果が導かれたときの面白さ。
だから研究をしてみたい気持ちはある。
なぜ数学か、の二つ目の答えは、ツールとしての強さ。
構造物の強度の評価、新薬の効果と副作用についての検証、鉄道ネットワークの最適化、
化学プラントの設計、資産運用のリスクマネジメント・・・
いろいろなところで数学は使われている。
で、俺はどちらかというと、ツールとしての数学に惹かれている。
ただ、数学というツールを手に入れて何をしたいか、というのは特にない。
というか、いろいろしたい。
数学コンサルタントとして、いろいろなところに携わりたい。
気持ちの再確認終了。
勉強はじめまーす。
成人式以来5年ぶり。
今回は、大学院受験しまっせーと宣言してきた。
これで落ちたらチョーカッコ悪い。
絶対合格する!という気持ちが強まればいいのだけれども。
今、一番強いのは、今の状況を何としてでも変えたいという気持ち。
でもそれだけなら、数学である必要はない。
なぜ数学かといえば、一つは数学自体の魅力。
美しさと、直感とは異なる結果が導かれたときの面白さ。
だから研究をしてみたい気持ちはある。
なぜ数学か、の二つ目の答えは、ツールとしての強さ。
構造物の強度の評価、新薬の効果と副作用についての検証、鉄道ネットワークの最適化、
化学プラントの設計、資産運用のリスクマネジメント・・・
いろいろなところで数学は使われている。
で、俺はどちらかというと、ツールとしての数学に惹かれている。
ただ、数学というツールを手に入れて何をしたいか、というのは特にない。
というか、いろいろしたい。
数学コンサルタントとして、いろいろなところに携わりたい。
気持ちの再確認終了。
勉強はじめまーす。
読んできた本を振り返るような歳でもないが
ちょっとしたことで読書にハマるもんだよなーと思ったので
俺の読書歴において重要な影響を与えた本を紹介。
必ずしもおすすめする本ではないので
ご容赦されたし。
まず読書にハマる最初の重要な経験は高校3年の時。
日本人なのに、有名な日本の小説を知らないことに焦りを感じていた頃。
そんな中でたまたま選んだのがこれ。
坊っちゃん (集英社文庫)/夏目 漱石

¥270
Amazon.co.jp
サクサク話が進んでいきおもしろい、と感じた。
これで、本っておもしろいのね、ということを覚えた。
「東大に入る」ということ「東大を出る」ということ/中島 敏

¥1,575
Amazon.co.jp
次の重要な読書体験は高校卒業直後。
購入動機は、ただ単純に気になったから。
東大、どうよ?って。
東大に入るということも出るということも
特になんでもない、普通の体験だと感じた以上に重要だったのは
こんなに熱く生きている人がいるということを知ったこと。
確実に世界が広がったし、それ以来、自分の人生を真摯にとらえるようになった。
霧の旗 (新潮文庫)/松本 清張

¥580
Amazon.co.jp
大学に入ってミステリーにハマった。
ミステリーはたいがいおもしろかったが
特に松本清張は、単なるミステリーではないというのがよかった。
本はおもしろいもの、というイメージが完全に定着した。
推理小説 (河出文庫)/秦 建日子
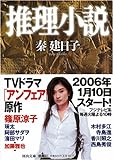
¥620
Amazon.co.jp
ミステリーを読んでいるうちに出会った本のうちの一冊。
この本で初めて小説で自分の考えを主張してもよいことを知った。
それ以来、主張のある小説を好んで読むようになった。
僕のなかの壊れていない部分 (光文社文庫)/白石 一文

¥650
Amazon.co.jp
たとえば、これ。
「どうして僕は自殺しないのだろう?」という帯が
強く印象に残っている。
白石さんの著作は、どれも考えさせられる。
そして、白石さんの人生に対する真摯な姿勢が好きだ。
オーデュボンの祈り (新潮文庫)/伊坂 幸太郎

¥660
Amazon.co.jp
これも主張がある本。
でも一貫して強い主張を発するのではなくて
さりげない主張がいくつもある。
そして、伊坂さんの作品は、おもしろい。
ばかばかしくておもしろいのだ。
このタイプのおもしろさをおもしろいという人は、あまりいないように思うが
俺はこういうおもしろさが好きだ。
主張もして、おもしろくもできる。
こんなことができるのか、という発見だった。
人間の土地 (新潮文庫)/サン=テグジュペリ

¥580
Amazon.co.jp
伊坂さんの「砂漠」でたびたび引用されているので気になった。
こんな本を書ける人になりたい。
話としては、めちゃくちゃおもしろいということはないが
豊かな経験を感じさせる。
なんといっても名言が多い。
「最大の贅沢は人間関係の贅沢だ」とか。
こうしてみると、小説が重要な影響を与えていたことがわかる。
読んだ本は確実に自己啓発系の本の方が多いのに。
話の筋がおもしろい、ということも重要だが
発見がある、というのが最高の体験であるように思う。
発見することがおもしろかったのだ。
そして最高の体験である発見を求めているから読書をやめられないのだ。
ちょっとしたことで読書にハマるもんだよなーと思ったので
俺の読書歴において重要な影響を与えた本を紹介。
必ずしもおすすめする本ではないので
ご容赦されたし。
まず読書にハマる最初の重要な経験は高校3年の時。
日本人なのに、有名な日本の小説を知らないことに焦りを感じていた頃。
そんな中でたまたま選んだのがこれ。
坊っちゃん (集英社文庫)/夏目 漱石

¥270
Amazon.co.jp
サクサク話が進んでいきおもしろい、と感じた。
これで、本っておもしろいのね、ということを覚えた。
「東大に入る」ということ「東大を出る」ということ/中島 敏

¥1,575
Amazon.co.jp
次の重要な読書体験は高校卒業直後。
購入動機は、ただ単純に気になったから。
東大、どうよ?って。
東大に入るということも出るということも
特になんでもない、普通の体験だと感じた以上に重要だったのは
こんなに熱く生きている人がいるということを知ったこと。
確実に世界が広がったし、それ以来、自分の人生を真摯にとらえるようになった。
霧の旗 (新潮文庫)/松本 清張

¥580
Amazon.co.jp
大学に入ってミステリーにハマった。
ミステリーはたいがいおもしろかったが
特に松本清張は、単なるミステリーではないというのがよかった。
本はおもしろいもの、というイメージが完全に定着した。
推理小説 (河出文庫)/秦 建日子
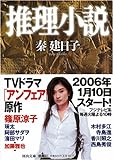
¥620
Amazon.co.jp
ミステリーを読んでいるうちに出会った本のうちの一冊。
この本で初めて小説で自分の考えを主張してもよいことを知った。
それ以来、主張のある小説を好んで読むようになった。
僕のなかの壊れていない部分 (光文社文庫)/白石 一文

¥650
Amazon.co.jp
たとえば、これ。
「どうして僕は自殺しないのだろう?」という帯が
強く印象に残っている。
白石さんの著作は、どれも考えさせられる。
そして、白石さんの人生に対する真摯な姿勢が好きだ。
オーデュボンの祈り (新潮文庫)/伊坂 幸太郎

¥660
Amazon.co.jp
これも主張がある本。
でも一貫して強い主張を発するのではなくて
さりげない主張がいくつもある。
そして、伊坂さんの作品は、おもしろい。
ばかばかしくておもしろいのだ。
このタイプのおもしろさをおもしろいという人は、あまりいないように思うが
俺はこういうおもしろさが好きだ。
主張もして、おもしろくもできる。
こんなことができるのか、という発見だった。
人間の土地 (新潮文庫)/サン=テグジュペリ

¥580
Amazon.co.jp
伊坂さんの「砂漠」でたびたび引用されているので気になった。
こんな本を書ける人になりたい。
話としては、めちゃくちゃおもしろいということはないが
豊かな経験を感じさせる。
なんといっても名言が多い。
「最大の贅沢は人間関係の贅沢だ」とか。
こうしてみると、小説が重要な影響を与えていたことがわかる。
読んだ本は確実に自己啓発系の本の方が多いのに。
話の筋がおもしろい、ということも重要だが
発見がある、というのが最高の体験であるように思う。
発見することがおもしろかったのだ。
そして最高の体験である発見を求めているから読書をやめられないのだ。
まずは元本を作る。
そこから利子を生み出し日々の生活にあて、投資を行う。
これが順序。
生産性を高めたければ投資として行うべきであって
元本には含まれない。
ということで、ライフハック、脳科学だのは置いておいて
まずは数学を。
そこから利子を生み出し日々の生活にあて、投資を行う。
これが順序。
生産性を高めたければ投資として行うべきであって
元本には含まれない。
ということで、ライフハック、脳科学だのは置いておいて
まずは数学を。