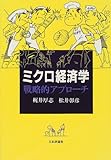12月23日・24日・25日は、アルバイト先のホテルに住み込みで働いていた。
働いては飯を食らい、そして寝る。
起きたら飯を食らい、そして働く。
そんなことの繰り返しである。
人がSEXしてるときに、私どもは皿を洗うのだ。
恐らく、あの日、2000人くらいが一つの場所でSEXに興じていたことだろう。
どうやら私の現時点の体力では、
立ちっぱなし、動きっぱなし、休憩なしだと、連続13時間の労働が可能だということが分かった。
13時間を超えると、脳のブレーカーが自動的に落ちる。
3日間で何時間働いたのか覚えてません。
「愛・覚えてますか?」
40時間くらいまでは記憶があります。
しかし、コックさん達は不眠不休で48時間労働をしていた。
不眠不休で48時間労働をすると人間はどうなるのか?
笑うのである。
笑うしかないのである。
下半身から込み上げてくる笑いを抑えることができないのだ。
そこで、1つの仮説が立てられる。
「笑いを抑制する一つの要因は理性である」
理性がなくなると笑いと性衝動と食欲が残るのではないか?
だからこそ、酒やマリファナは、人間を笑いに誘うのではないのだろうか?
この仮説を実験で検証することは倫理上困難である。
しかし、この仮説が証明されれば、私はベルクソンを超えられるだろう。
だいたい、ベルクソンの『笑い』に引用されてる例が古すぎて笑えない
という矛盾をクリアしない限り、『笑い』を証明したことにはならないでしょうが。
すべての仕事が終わった後、洗い場と調理場の間に何かしらの友情が生まれたことは事実である。
いつもいがみ合っていても、今回だけは笑いを通して解りあえた気がする。
みんなで飯を食いに行き、26日の早朝に家に帰還した後で、
私は立花隆ばりに「戦士の休息だな」と呟いてから布団に入った。
私はベルクソンを超え、立花隆を凌駕できたのではないかと勘違いしてしまった。
そんな極限を超えた私に待ってるものは、超回復以外にありえないだろう。
[今回の参考文献]
- 笑い/アンリ・ベルクソン

- ¥630
- Amazon.co.jp
- 耳をすませば
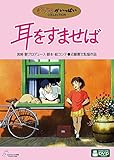
- ¥3,860
- Amazon.co.jp
- 超時空要塞マクロス 愛・おぼえていますか

- ¥7,020