「仁義なき戦い」は、第一作の制作前にシリーズ化が決定されていましたが、予想以上の大ヒットとなり配給収入は当時、邦画の中で年間第2位となったのでした。
めまいを覚えるような荒々しい手持ちカメラによる映像が、ドキュメンタリーを見ているかのような生々しさで迫ります。
聞き慣れない広島弁のリアリティと、古典的ともいえる主題曲の単調な繰り返しが、独特のリズムとバイブレーションを生んで中枢神経を揺さぶる、画期的な暴力映画とも評されたといいます。
その主題曲がこちら:
深作欣二監督は、「広島弁」について、こう振り返っています。
「"仁義なき戦い"に一番興味を感じたのは焼け跡であり、それがしかも地方都市、広島、呉だったということ」
「それと前に『ジャコ萬と鉄』で少しありましたけど、地方弁を本格的な形で使ったのは初めてだったんですよ」
「京都で映画を撮ったこともないから、地方弁を使いたくてしょうがなかった。自分の中に地方人としての意識があったんでしょうね」
助監督をつとめた土橋亨は、インタビューで以下の点を指摘しています。
『仁義なき戦い』の成功の理由は、深作欣二のダイナミックな演出、斬新なカメラワーク、絶頂期に向かう役者たちの演技、実録ならではのリアリティ。
さらに、終戦直後の広島や呉という舞台設定の妙、] 戦国時代の"国盗り物語的なスリルなど、多くの複合要因から成り立ち、それらの幸福な出会いともいえる。
だが やはり原作にはない膨大な資料を掻き集めてシナリオにまとめた笠原和夫の巧みな脚本が秀逸だった。
"脳天唐竹割りな広島弁の応酬"、広島弁のシェークスピア とも"血風ヤクザオペラ" とも称された広島弁の珠玉の名セリフの数々によるところが大きい。
「仁義なき戦い」シリーズなど多くのヒット作を手がけた東映京都撮影所のプロデューサーの日下部五郎氏が今年2月に亡くなりました。85歳でした。
彼は、こう述懐しています。
「脚本を書いた笠原さんが『仁義なき戦い』シリーズで残した最も大きな功績は、広島の方言、やくざ言葉を巧みに拾い上げて、映画の名ゼリフと言われるまでにしたことでしょう」
では、「仁義なき戦い」での代表的なセリフを、見てみましょう:
・広能昌三(菅原文太)

- 馬の小便、いうなら、ホンマもんの小便飲ましたろうか
- 呼んでええですか?呼んでええですか?呼びますよ!
- あとがないんじゃ、あとが
- サツにチンコロしたんはおどれらか
- 狙われるモンより、狙うモンのほうが強いんじゃ
- そがな考えしとるとスキができるぞ
- 山守さん、弾はまだ残っとるがよぉ
・山守義雄(金子信雄)
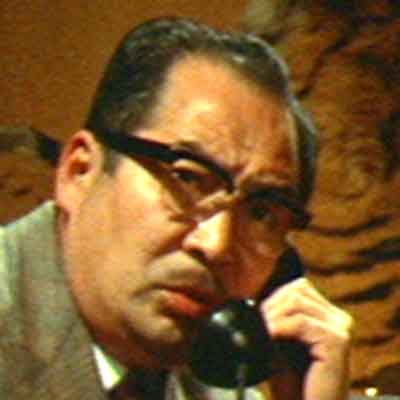
- 調子に乗りゃがって、ええ加減にせえよ、ゼニになりもせんことしやがって
- 頼む、ワシを男にしてくれ
- お前が帰ってきたら、ワシの全財産をくれちゃる
- そがな昔の事、誰が知るかい
・坂井鉄也(松方弘樹)

- ワシゃ、旅うってくるけん
- あんたぁ最初からワシらが担いどる神輿じゃないの
- 神輿が勝手に歩ける言うんなら歩いてみないや、おぉ
- ワシらどこで道間違えたんかのう
- 目え開いてよぉ、ワシに力貸せぇや
TBSの演出家だった鴨下信一は「『仁義なき戦い』は、
「仁義なき戦いは、日本映画のマイルストーンになった。
出演者は各々のベスト・パフォーマンスを見せているが、これらの誰よりも大スターがいて、その魅力が全編を支えている。
それは広島弁である」
と論じています。
『仁義なき戦い』で重要な演出効果となるのが、何といっても広島弁なのです。
現役の関西系の組関係者が不気味でドスが利いていると評価する言葉です。
播磨弁では汚くて、博多弁では可愛らしくて、鹿児島弁では意味不明というところで堂々の極道方言ベストワンとも評されるのです。
広島弁は、この映画をきっかけに良くも悪くも全国に広まりました。
公開当時は聞き慣れない広島弁のオンパレードに戸惑った映画ファンも多かったようですが、何度となく鑑賞する度にどこかの英語教材のように精通していき、"仁義ファン"はみな広島弁のバイリンガルとなったとの評価もあります。
さらに、この映画のヒットの背景には、法された時代の社会事情も大いに関係があったと分析されています。
1960年代後半から1970年代初期にかけて、日本はひとつの転換点を迎えていました。
高度経済成長政策が行き詰まりをみせ、各種公害の発生や大学紛争の波及にみられるように、これまで抑え込まれていた政治社会の歪みが至るところで噴き出し始めていたからです。
それは経済至上主義できた戦後の路線に対し、深い内省を迫る社会の動向があったといいます。
「仁義なき戦いシリーズ」は、こうした世相の中で登場してきたのです。
第一部は終戦直後、第二部は昭和27年頃、第三部と第四部は昭和30年代後期、第五部は昭和40年代を舞台にしています。
戦後史を別の角度から見つめ直すという意味では、この連作はまさに時代の産物であったのです。
映画は今まで隠蔽されてきた野卑で猥雑なものに視線を向け、これを白日のもとに晒そうとします。
ここに提示されているのは、戦後日本の裏面史です。
令和の時代になった最近も、景気が良いと言われても庶民には給料のアップがないのに、物価だけがじわじわ上がってきて、社会に閉塞感があります。
そこに、突然新型コロナウィルスという流行り病が起こり、世界を席巻している今日、今後の生活に大きな不安が沸き起こっています。
「仁義なき戦い」の令和バージョンが生まれてくるような気がしているのは、私だけでしょうか。
