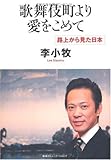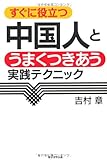★★★★★(星5)
<My Opinion>
表紙とタイトルはいかにも薄っぺらなハウツー本を想起させるが、内容に極めて説得力がある。本書を読んだことで、私が1年半中国にいて感じてきた中国人に対する疑問が全て整理された。中国にこれから滞在する人は本書を読んで「中国人」について予習したほうが生活がスムーズに進むと思うし、赴任してある程度時間が経ったが、典型的な中国人像を掴みかねているような人にとっても必ず役に立つだろう。本書の中に、中国人は本来的に「会社」というコミュニティに防衛機能を期待していないとの件があったが、もっと言えば「国家」に対しても防御機能を期待していないのだと思う。なぜなら私の取引先の経営者のほとんどはカナダやニュージーランドの永住権を取得していることからである。いざとなったらいつでも国外脱出する心の準備が出来ているのである。著者は相当数の中国人と接してきており、地に足がついた内容かつ実践的なので星5つ。
あまりに実践的で抜書きが相当な量になった。
<My Opinion>
●4つのフィルター
中国人を理解する時は「地域差」「世代差」「業界・職業差」「学歴・経歴差」の4つのフィルター重ね合わせて理解する。(P3)
●3つの「没有(メイヨウ)」に気をつけろ
中国人が良く口にする「没有問題」(問題ありません)という言葉は「わかりました」という挨拶程度の意味に受け取っておいたほうが無難である。この場合「まったく問題がないはずはない」と考えたほうが賢明。「没有問題」の次が「没有関係」。これが中国人の口から出てくるようになるとその「問題」はかなり深刻に陥っていると理解するのが良い。そして、最後に出てくる言葉が「没有弁法」(仕方ありません)という表現。これが出てきたときはもうあきらめるしかないと心得ておくのが良い(P15)
●「贈り物」として贈ってはいけない品物
①時計:中国語で時計を意味する「鐘(Zhong)」は「終(Zhong)」と発音が同じであり、時計を送るということは「終了」「おしまい」を連想させるので厳禁。又、「時計を贈る」というのは中国語で「送鐘」と書き、「送終」(死に水を取る、死に目にあう)という意味になる。
②傘&扇子:中国語ではそれぞれ「雨傘(Yu san)」「扇子(Shan zi)」と発音し、中国語の「分散(fen san)」(散らばる)「離散(li san)」(散り散りになる)という言葉を連想させるのでこれも良くない。
③詰め合わせのお菓子:中国では基本的に「贈り物」は個人が個人にプレゼントするもの。例えば、取引先の社員を代表して陳さんが空港に出迎えに来てくれた場合、陳さんに対して「社員みなさんでどうぞ」と詰め合わせのお菓子を渡すのは失礼。もしそうするのであれば、陳さん用に1つ、社員用に1つ用意するべき。原則はあくまで1人1つ。(P52)
●中国人の独特な「タマゴ型コミュニティ」とは
中国人は家族を中心とした独特なコミュニティ感覚を持っている。著者はこれをタマゴ型コミュニティと命名。タマゴの黄身部分には①自己(自分)と②自家人(家族)がいて、白身の部分には③自己人(身内)がいる。そして殻の外に④熟人(友人・知人)もっとその外に⑤外人(他人)がいる。中国人を理解する上で一番大事なのがこの卵の中と外の区別、つまり③と④の違いである。自己人というのは日本語で言う親友や仲間よりもより固い絆で結ばれた、絶対的な信頼関係の上に成り立っている関係の人を指す。(P62)
※著者ですら、殻の中に入ることができた(=その人の自己人になれた)と実感できる関係は、10人に満たないということから考えても、この自己人の意味合いの重さが分かる。
●同心円状に広がる中国人の「花びら型シェルター」
タマゴ型コミュニティのタマゴの殻は実は一つではなく自己を中心に花びらのようにいくつものタマゴを抱えている。本業のコミュニティ、旅行仲間のコミュニティetc…というようにいくつものシェルターが花びらのように広がっている。注意すべきは、中国人は日本人と違い、「会社」というコミュニティにシェルター機能を期待していない、「j会社」をシェルターと見なすことは一般的にしない。(P71)
●業務の「引継ぎ」は行われない
日本では業務の「引継ぎ」が行われるのは当たり前であるが、中国では担当者が変わった場合、新しい担当者が決まるまでプロジェクトがストップする、担当者が具体的な仕事内容を把握していないといったケースがよくある。担当者が交代したり、辞めたりするときは、「業務の引継ぎは行われない」という心の準備をしておく必要がある。(P124)
●中国人とのビジネスは「個人対個人」が基本
日本人はビジネスの基本は「会社対会社」と考える。しかし、中国では「会社対会社」の関係よりも「個人対個人」の関係を重視する傾向にある。担当者個人の力がない場合にはビジネスがそこでストップしてしまう場合もある。(P145)
●「結果の平等」よりも「機会の平等」を重視する中国人
日本企業は組織やチームを重視するので、「みんなで頑張った成果は平等に分配する」という考えがなじみやすい。しかし、中国では「成果」に対する「報酬」に格差をつけるほうが一般的。個人の実績と貢献度に合わせて結果に格差が出ることは当たり前と考える。(P181)
●「契約は努力目標にすぎない」と考える中国人
中国人にとって「契約」とは、その「契約」を交わす時点で最良の方法だと思われることを、「契約」を交わす時点で文書に書き記したもの。つまり、「契約」を交わした後で状況が変化していけば、「よりよい方向」へ見直しを行っていくことは当然であると考える。(P239)
●「割り勘」にしない中国の食事会
若い世代の間では「割り勘」は一般的になっているが、伝統的な考え方はそうではない。中国人にとって「平等に負担すること」は貸し借りの関係をなくしてしまうことであり、それは「人間関係の清算」という意味に通じる。関係を続けていくためには貸しと借りを大切につないでいく(食事はおごり合っていく)というのが中国人の伝統的な考え方。(P270)
●「郷に入らば郷に従え」とは違う異文化理解アプローチ
異文化理解においては第一に「気づき」、第二に「自己認識」、第三に「接点探し」が重要。まず、自国文化との違いに「気づき」、そしてそれに対して、自国文化と対比してどうなのかと「自己認識」してみて、お互いの違いをはっきり確認した上でその「接点」がどこにあるのか探してみるというプロセスが大切。譲れる部分、譲れない部分等、円滑なコミュニケーションを進める上での選択肢がはっきり見えてくる。(P304)
- すぐに役立つ 中国人とうまくつきあう実践テクニック/吉村 章
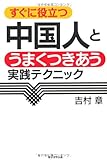
- ¥1,365
- Amazon.co.jp