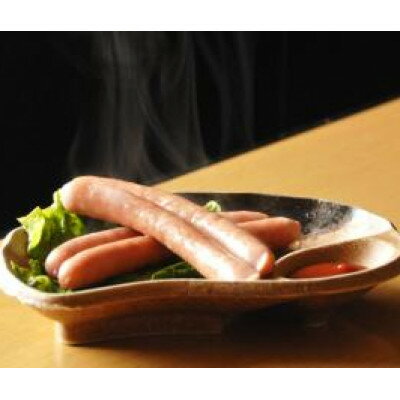毎度、当ブログへお越しいただき、ありがとうございます。
先日、長野県飯田市にある飯田古墳群を訪ねたのですが、飯田市内には他にも国指定文化財が多くあります。
飯田市のある伊那盆地は、中央アルプスとも称される木曽山脈と、南アルプスとも呼ばれる赤石山脈に挟まれた盆地です。この両山脈は2,000~3,000m級の山々が連なり、“日本の屋根”とも呼ばれます。
盆地の中央には諏訪湖に源を発する天竜川が流れ、その両岸には隆起と天竜川の浸食によって形成された河岸段丘が発達しています。
盆地から眺める両山脈は急峻な峰々が連なって、壮大な風景を見せてくれます。
飯田古墳群は天竜川の右岸段丘上に形成された古墳群ですが、その対岸、赤石山脈側の山際には文永寺という古刹があります。
今回は、この文永寺に残る「石室五輪塔」を訪ねました。
文化財に指定されているものは、何かしら指定される理由があります。特に、現行法の「文化財保護法」以前の「国宝保存法」時代に指定されたものはたいてい、古くから「美麗なことで有名」か、「変わっている、珍奇なことで有名」か、いずれかなものが多いです。
ここ文永寺に残る「石室五輪塔」も昭和の初め頃(昭和5年)の指定と、昔から有名な石塔だったようです。なんせ、石室が設けられて守られている五輪塔なんて、あまり聞いたことがありません。
普通は覆屋で、しかも保存のために近代以降に設けられた建屋で守られている、というものならいくらでも見たことがありますが。
その石室も込みで文化財に指定された五輪塔、マニアとしては是非見ておきたいものです。
と書きましたが、私は若い頃に既に見たことがあります。改めてもう一度、見てみたいと訪ねました。
文永寺のある飯田市上久堅、下久堅は総称して「知久平」と呼ばれていて、中世をとおして、神之峯城に拠った地頭・知久氏に支配されていました。
文永寺は今でこそ小さなお寺ですが、「文永寺」の「文永」とは鎌倉時代の年号(1264~1275)です。元寇の「文永の役」で有名なあの文永です。
年号を寺号に持つお寺はだいたい「勅額寺」といわれる、かつて朝廷から賜った宸筆の勅額を掲げていた格式のあるお寺です。文永寺も朝廷とのつながりがあったと伝えられています。知久氏の嫡流、知久信貞を開基とし、京都・醍醐寺理性院の龍亮が開山です(隆毫とも)。
そんな古刹なのですが、今はひっそりとした山村に佇む、観光寺院ではないので人影もまばらな静かなお寺です。
重要文化財の五輪塔は現在の境内の西側、住宅や田んぼに囲まれた一画にあります。
もともとはここも境内でした。しかし長い歴史の中で境内は縮小されてしまい、今は境外となっています。
五輪塔の位置は造立以来、変わっていないそうです。昭和61年7月~12月にかけて行われた修理工事の際の調査で明らかになりました。
五輪塔は花崗岩製です。外側には、やはり花崗岩の板石を組み合わせて造られた石室が築かれています。
この石室があるおかげで、五輪塔はほとんど風化も欠失もなく、造立当初の形態が残されています。しかも石室の天井には造立時の年代や造立者、石工の名前が刻まれて残っているんです。
石室が設けられていること、そのおかげで石塔が劣化せずに保存されたこと、石室と五輪塔の造立時期が明確にわかることが特に貴重とされたようです。
地、水、火、風、空の各輪に刻まれた梵字もくっきりと残っています。
鎌倉時代の五輪塔は各輪の幅や高さが揃っていて、バランスがいいのでカッコいいなと思います。奈良・西大寺の叡尊塔や鎌倉・極楽寺の忍性塔がいい例です。
石室の方も観察してみましょう。
複雑に切られた平石を、絶妙に組み合わせているところがおもしろいですね。
しかも屋根は切妻造りで棟まで設けられていて、木造の建物を意識しているのがわかります。
石室というより、石で祠を造ったんじゃないでしょうか。いずれにしても珍しいですけどね。
天井の銘文を撮影してみようと試みましたが、柵の外から撮影するのは一苦労でした。一脚を伸ばして、何とかそれらしいものを撮影したのが下の写真です。
文永寺にある国指定文化財はこの石室五輪塔だけですが、他にも長野県宝に指定された梵鐘や貴重な古文書類が残されていました。
現地で見られるのは梵鐘だけなので、ここで紹介します。
なぜ国指定にならないのかは、おそらく銘文がないせいでしょう。銘文がないと鋳造された年代がわからないので、鋳造年代の基準史料にならないからだと思われます。
しかし、形態の特徴からは明らかに鎌倉時代を下らない、古鐘だと思われます。だって胴部がやや膨らむ形状は後代の鐘のそれではありません。
あと、乳ノ間と池の間、下帯の幅のバランスの良さはこの鐘の古さを物語っています。
飯田市の山奥にひっそりと佇む古刹、文永寺。
観光寺院ではないため、訪れる人もまばらなお寺ですが静かな雰囲気を満喫するにはとてもいいところでした。
--------
文永寺 石室五輪塔 (昭和5年5月 重要文化財、長野県飯田市下久堅南原)
文永寺は飯田市の南東、竜東地区の一角である下久堅に所在します。天竜川が形成した河岸段丘の左岸台地上にあります。開創は地元の地頭である知久信貞、開山は隆毫あるいは京都・醍醐寺理性院の龍亮ともいわれています。勅願寺として隆盛を誇り、室町中期の文明年間には塔頭12坊を抱えて隆盛を極めました。
旧境内の西側、民家へ続く道のわきに花崗岩製の石室に収まった五輪塔があります。この五輪塔は石室天井にある銘文
弘安六年
癸未十二 左衛門尉
月二十九日 神敦幸
神敦幸造 生年六
南都石工 十二歳
藤原行長
とあり、造立年月と奉納者、石工の名前が明らかになっています。造立時期の基準となる保存状態の良い石造物(五輪塔)として、重要文化財に指定されました。
銘文中にある「神敦幸」とは開創の知久信貞の息子、敦幸と見られ、知久氏はもともと神氏を名乗っていたとみられています。
参考文献:『重要文化財文永寺石室・五輪塔修理工事報告書』、財団法人 文化財建造物保存技術協会・編、重要文化財文永寺石室・五輪塔保存修理委員会(1987)