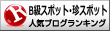毎度ご覧いただき、ありがとうございます。

暖かい季節になってまいりました。
今年は冬が去るのが早かったのか、早くから暖かい日々が続きました。おかげで全国的に花の開花が早まっているようです。サクラなどはそのよい例で。
季節ものの文化財を見に行きたいと思案していたところ、やや見頃は過ぎたものの、まだまだ綺麗に咲いているという花がありました。
それがサクラソウでした。埼玉県には全国でも唯一、特別天然記念物に指定されたサクラソウの自生地があります。今回はその自生地を訪ねました。
目指すはさいたま市内の荒川河川敷です。なおこの情報は令和5年4月8日現在です。ご覧いただいている方はご注意ください。
指定名称は「田島ヶ原サクラソウ自生地」といい、埼玉県内にある3件の特別天然記念物の一つです(他は「牛島のフジ」、「御岳の鏡岩」)。
また、大正9(1920)年当時、史跡名勝天然記念物法の施行による最初の天然記念物指定のうちの一件でもあります(特別天然記念物に指定されたのは文化財保護法施行後の昭和27年)。
最寄り駅はJR武蔵野線 西浦和駅になります。徒歩20分ほどです。
あるいはJR浦和駅西口から志木駅東口行バスにて「さくら草公園入口」下車、すぐ下の河川敷が目指す自生地です。
訪ねてみればわかりますが、すぐそばまで住宅地開発や河川整備が進んでいて、都市化の波にさらされていることがわかります。
本来、荒川流域には多くのサクラソウ自生地がありました。サクラソウは本来、山地の低湿な土地を好む植物です。荒川が「荒ぶる川」だったため、大雨が降るたびに氾濫し、それによって上流から河川敷に新たなサクラソウの株と肥沃な土が運ばれてきたのです。
ところが戦後の混乱期に多くの場所は開墾され、そのうえ洪水を防ぐための河川改修が進んでしまい、荒川はおとなしい川になってしまったのです。そのため、河川敷は土の更新が行われず、乾燥化も進んでしまいました。
人々の平穏な生活を守るためには仕方がないことなのですが、サクラソウにとっては過酷な環境となってしまいました。
そのような理由から、自生するサクラソウが見られるのは田島ヶ原のみとなってしまったのです。
田島ヶ原も例外ではなく、乾燥化が進んでいて自然の営みに任せていてはサクラソウが生育しない状況だそうです。
水もスプリンクラーのようなもので散水しているのだとか。
私、実は20~30年ほど前に一度この場所を訪ねているのですが、サクラソウの株はだいぶ減ったように感じました。
ところで、サクラソウが特別天然記念物になったのは希少性が理由ではありません。
ひとつはサクラソウの生育と植物同士の競争、共存の様子や生態の移り変わり(遷移)を観察できる格好の場所であること。
もうひとつ、サクラソウは自然に変異しやすい特性を持ち、遺伝研究の良いサンプルになるから。
これらが大きな理由となっています。
江戸時代にはその可憐さから愛でられて栽培されるようになりましたが、変異が発生しやすいので自生地から特徴の違う株を持ち帰り、新しい園芸品種をつくることが流行った時期もあったそうです。
現地で見た、いろんな形態のサクラソウの花を見ていただきましょう。
また、田島ヶ原は河川敷に特有な植物が多く、絶滅危惧種が多数みられることでも有名です。天然記念物指定地の利得ですね。
その一部をご覧ください。
ノウルシは田島ヶ原でサクラソウが終わった後に見頃となるので人気の植物です。ただ、ノウルシは河川敷でも乾燥した場所を好むそうなので、乾燥化が進んでいることを表わすあまり歓迎されない植物でもあります。
あと、ススキがだいぶ侵入していました。これも乾燥した場所を好むそうなので、あまり歓迎されていません。
環境の変化にさらされながら、それでもまだまだ元気に花をつけている可憐なサクラソウたちにエールを送りながら、田島ヶ原を後にしました。
ところで、荒川沿いにはかつて多くのサクラソウ自生地があったとお話ししましたが、再びサクラソウの名所にしようと試みている場所が何か所かあります。東京都北区の浮間ノ原などが話題となっています(浮間ノ原は復活を目指しているのとは少し違うのですが)。
埼玉県内にもあります。今回、同じさいたま市内の西区にある錦乃原サクラソウ自生地を訪ねました。
ここは田島ヶ原より上流の荒川河川敷にあり、戦後の混乱期に開墾されて全滅するまで国の天然記念物に指定されていました(指定名称は「馬宮村サクラソウ自生地」、現在は解除されています)。
文化財保護なんて気にしていられない時代、失われてしまったのは仕方のないことです。しかし近隣の人がここから株を持ち出して栽培していたため、20年ほど前からその株を河川敷へ戻し、自生地の復元を試みているそうです。
どうなっているのか気になったので、田島ヶ原を訪ねたあと行ってみました。
ここへはJR大宮駅西口から「二ツ宮」行バス終点下車、徒歩約10分または「所沢駅」「馬宮団地」「ららぽーと富士見」行「運動場前」下車、徒歩5分ほどです。
治水橋という橋の下の河川敷に広がっています。田島ヶ原とよく似た環境です。
今は「錦乃原桜草園」として地元の保存会の方が保護管理しており、サクラソウは順調に定着していました。
地元の小中学生が保護育成に携わっていて、毎年現地に株を移植して増殖させているとのこと。
この位置が旧治水橋の築堤の陰になっていて、強い風が吹き込まないせいか、一番生育がいいそうです。
田島ヶ原のような多様な形状の花は見られませんが、安定して生育している様子を見て安心しました。
最盛期には田島ヶ原より広い面積に生育していたという錦乃原の自生地をよみがえらせたいという地元の熱意が実ることを祈って現地を後にしました。
なお、この日は地元のサクラソウイベントが行われていて大勢の人が現地を訪れていました。イベントの一環としてサクラソウの苗を配布していて、私も在来種のサクラソウを育ててみようと思い、いただいてきました。
帰宅して早速植えてみました。順調に成長してくれるように祈ります(かつてムジナモの栽培に失敗した実績がありますので…)。
-----------
田島ヶ原サクラソウ自生地 (昭和27年3月・特別天然記念物 埼玉県さいたま市桜区田島)
田島ヶ原サクラソウ自生地は荒川河川敷にたくさんあったサクラソウ原野が明治時代以降、河川改修や開発の波にさらされて失われていくのを憂いた、当時植物学の権威だった三好学博士が保護・保存のために働きかけて国指定天然記念物となった場所です。我が国初の天然記念物指定の場所でもあります。
現在は都市化の波にさらされ、河川改修も進んだため環境の変化が著しく、サクラソウの絶滅が心配されています。
江戸時代には多く見られたサクラソウ原野の保存、保護に加えて、サクラソウ原野の生態遷移の観察場所として、またサクラソウの形態変異の観察場所として貴重なため、特別天然記念物に指定されています。
参考文献:
『日本の天然記念物』 講談社(1995)
ブログが気に入ったらクリックをお願いします