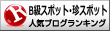実は昨年、4ヶ月ほど「武甲山石灰岩地特殊植物群落」の植物を追っていました。
埼玉県秩父市と横瀬町に跨って聳える独立峰、武甲山。
埼玉県の秩父地方出身なら心に刻まれている、故郷の峰。
武甲山を見れば、「秩父に帰ってきたなぁ…」と思わないことはないという、埼玉県秩父地方を代表する山です。
日本三大曳山祭りに数えられる「秩父夜祭」で知られる秩父ですが、夜祭で祀られる神様はこの“武甲山”の神様とされています。
この山は巨大な石灰岩の塊です。そのため明治時代から石灰岩の採掘が始められ、近代の発展に合わせて山肌は削られていきました。
そして採掘された石灰岩はセメントやコンクリートになり、関東大震災や太平洋戦争で大きな惨禍に見舞われた東京の復興を助けました。
そのような功績もありながら、しかし秩父の心の支えともいえる武甲山は今や消滅が危惧されるほど削られ、山容が大きく変わりました。
ところでこの山には、石灰岩地を好む特有な植物が多数繁茂しているのです。その中にはここで採取された標本が基準となっているもの(基準標本種)や武甲山固有とされるものが多数含まれています。
そのような植物が特に多く見られる区域は「武甲山石灰岩地特殊植物群落」の名称で国指定天然記念物となっています。
ところが、時代の流れでしょうか、産業が優先されて植物群落は今やほんのわずかな広さのエリアしか保護されていません。
しかも石灰岩採掘場のど真ん中に位置しているため、一般者の立ち入りは固く禁じられています。
採掘を行っている企業側は、武甲山の自然を維持する努力を声高に喧伝していますが、特殊植物群落は今や風前の灯火です。あるいは既に消滅したともいわれています
そんな天然記念物指定地に繁殖している植物を、昨年は追いかけてみました。
そのレポートになります。
先にも書いたように、武甲山石灰岩地特殊植物群落は現地へ立ち入ることができません。そのため現地から、特に貴重な武甲山の固有種や武甲山で採取されたものが基準標本とされる植物が移植されている場所がありました。
それが秩父郡横瀬町にある横瀬町歴史民俗資料館の玄関前に設けられた前庭と、秩父市内の羊山公園内にある武甲山資料館の前庭です。
武甲山資料館では、武甲山で採掘事業を行っている企業が行っている保護事業で栽培された鉢植えの植物を借用して時々展示されることもありました。
まず春先に、小さく可憐な花をつけるブコウマメザクラの開花を見に行きました。
横瀬町歴史民俗資料館前には主に木本の植物が十種類ほど植えられています。
その中にブコウマメザクラもありました。
ブコウマメザクラはその名の通り、武甲山で発見された標本が基準となっている桜の品種です。
開花時期はソメイヨシノよりやや遅い頃でした。
マメザクラの名の通り、街中で見られるソメイヨシノより小さい花が一本の木にポツリポツリと咲いていました。
いっぺんにパッと咲く桜ではないので、華やかさは全くありません。
むしろ慎ましく可愛らしいサクラの花でした。
萼(がく)が筒形をしていて紫がかった赤い色をしているのが特徴なのだそう。
武甲山だけでなく、秩父を中心とした関東西部の石灰岩地帯で見ることができます。
ちょうど同じころ、イヌコリヤナギやチョウセンナニワズ、チチブヤナギなどの花も見られました。イヌコリヤナギは普通に見られる植物だそうですが、チョウセンナニワズとチチブヤナギは関東の石灰岩地でしか見られない木で、武甲山が基準標本採取地だとか。
現地は石灰岩地帯だというのに、要は土壌がアルカリ性が強いはずですよね。
そのような環境を再現している努力に脱帽です。
そして4月中~下旬には武甲山資料館でチチブイワザクラの展示がありました。
私が武甲山石灰岩地特殊植物群落を追っているのは、ある意味この花が見たかったから、というのもあります。
武甲山石灰岩地特殊植物群落の指定域でしか見られない固有種なんだそうです。
武甲山で操業している企業が増殖事業で育てている株を借りて展示しているものだとか。
鉢植えにされていますが、簡単には増殖させられない植物の一つです。
サクラソウの一種で、本邦のサクラソウはその仲間自体が環境の変化に弱いというのに石灰岩地帯に特化した植物なんだとか。
可憐な花ですが、サクラソウらしい儚さを感じます。
同時に展示されていたのが、ウメウツギ。
こちらは武甲山でよく見られるアジサイ科の基準標本種です。
思いもかけず別の植物が見られたのでラッキーでした。
そして梅雨の最中の7月には武甲山資料館でミヤマスカシユリの展示がありました。
この花は武甲山以外でも見られるそうですが、岩手や茨城のごく限定された場所でしか見られず、ほぼ武甲山でしか見られない植物のようです。
これも武甲山で操業している企業が増殖事業で増やしているものを拝借して展示していました。
やはり増殖が難しい植物のようで、鉢植えでよく繁殖させられたなと考えてしまいました。
このあと、本当はチチブヒョウタンボクの実がなる10月頃に横瀬町立歴史民俗資料館をもう一度訪問するつもりでしたが、仕事や他の博物館での特別展を見に行くのに忙しかったりして失念してしまい、行けませんでした。
今年もまた花の季節がやってきますので、行けたら行ってみようと考えています。その時はまた報告します。
-----------
武甲山石灰岩地特殊植物群落 (昭和26年6月・国指定天然記念物 埼玉県秩父郡横瀬町生川)
武甲山石灰岩地特殊植物群落は、埼玉県の秩父地方を代表する独立峰・武甲山(標高1,304m)の北面、標高約990m、高さ約60m、幅約120mの通称「三ツ岩」「幕岩」と呼ばれる地域とその下部、標高594m~755mに位置する地域の範囲が指定されています。武甲山はその半分がおよそ石灰岩でできており、明治以降多くの植物学者によって新種や分布上貴重な植物が多く発見されています。
特記すべき植物としてはブコウマメザクラ、ブコウカスミザクラ、チチブヤナギ、チョウセンナニワズ、イワツクバネウツギ、チチブヒョウタンボク、チチブイワザクラ、イワシモツケ、ミヤマスカシユリなどがあります。
現地はセメントやコンクリートの原料として石灰岩の採掘が4つの企業によって現在も進められ、現地の自治体との協定によって武甲山の植生復元に取り組むことが約束されています。天然記念物指定地も採掘場の中にあって一般の立ち入りは禁止され、近づくことができません。本文でも書きましたが指定地自体がすでに消滅したともいわれています。
そのような経緯から武甲山石灰岩採掘企業が協同で出資し、武甲山の採掘事業の事業内容紹介と自然保護の取り組みについて解説を行う施設として秩父市の羊山公園内に設立した施設が武甲山資料館です。そのため、ときどき武甲山の固有種である植物の展示を期間限定で行なっています。
また秩父郡横瀬町にある、横瀬町歴史民俗資料館の前庭にも武甲山石灰岩地特殊植物群落から移植された貴重な植物が植えられ、近づくことのできない特殊植物群落の一端を我々に教えてくれます。
参考文献:
『日本の天然記念物』 講談社(1995)
『写真集 武甲山植物群』 武甲山植物群保護対策推進協議会・編、武甲山植物群保護対策推進協議会(2001)
参考HP: 武甲山資料館 http://www.bukohzan.jp/index.html
ブログが気に入ったらクリックをお願いします