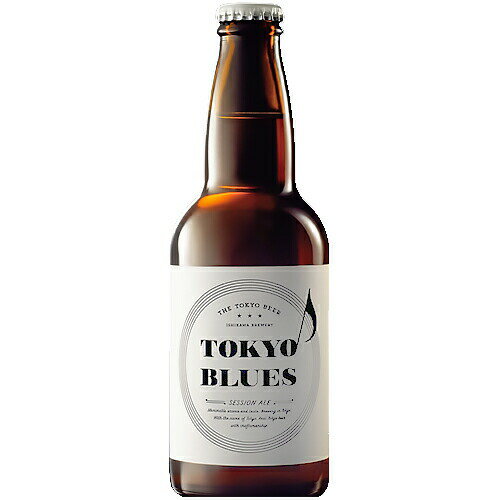日本で一番飲まれているアルコール飲料は、ダントツでビールです。
税法上、スピリッツ扱いですが、第三のビールなどを含め、ビール系が半分以上を占めます。
それだけ売れるということは、新商品もどんどん発表され、CMも盛んに作られることになります。
日本に住んでいる外国人は、日本のお酒のCMの多さに、驚かされるといいます。
欧米では、規制されているので、飲酒をすすめるようなものは、公共の場では流せないからだそうです。
日本にもそれなりの規制はあるのですが、かなりゆる~いので、お酒CM天国になっているわけです。
規制がゆるいということは、お酒を過剰に飲んで、社会不安を起こすような人が少ないということと、
民族性や国民性の違いということなのかもしれませんが、
まァ、田舎の酒好きジジイが偉そうなことをいったところで、何も始まらないし、終わりもしませんが。
ビールのCMで、最近流されるようになったのは、大手メーカーのクラフトビールで、
見るにつけ、やはりクラフトビールのブームがきているのかと感じられます。
明治期にも、当時はクラフトビールという言葉はなかったので、地ビールのブームがあったそうです。
NHKBSの『コウケンテツの日本の100年ゴハン紀行』という番組で訪ねた福生の老舗酒蔵には、
明治20年にビールを造っていた時の麦汁の煮釜が、蔵の一隅に残っていました。
18代目となる当主が語ってくれたところによると、
銘水として知られる福生の水を使って、現在の1億円近い資金をかけてビール造りを始めたそうです。
ところが、わずか3年で撤退してしまったといいます。
当時は王冠を締める技術が十分でなく、運搬中に、次々と吹き出してしまったからだそうです。
準備に1年、醸造したのが1年、後かたずけに1年、足掛け3年で、
1億円はビールの泡とともに、消えてしまいました。
屋敷内には井戸が6つあり、銘水は今も豊富に流れています。
この銘水を使って再びビールを造る、明治の雪辱を晴らそうという意思が働いたのかどうかはわかりませんが、
明治復刻ビールのキャッチコピーで、クラフトビールを造りました。
こだわりは3つ。
・ろ過をしない
・火入れをしない
・ホップをきかせる
醸造責任者は、365日、自ら糖度をチェック、
手作りだからできる繊細な味と香りにこだわったビール造りをしているといいます。
*・゜゚・*:.。..。.:*・゜*・゜゚・*:.。..。.:*・゜*・゜゚・*:.。..。.:*・゜
ポケットマルシェ(ポケマル)という、会員が50万人以上、日本最大級の産直者直送サイトがあります。
生産者直送で、普段なかなか手に入らないような珍しい食材、流通には乗りにくい訳あり商品ほか、いろいろラインナップがあります。
【フードロス】や【フードレスキュー】などの社会問題の解決にもつながるサイトです。
ポケットマルシェは、『全国の隠れたうまいに出会えるサイト』で紹介してます。
★おすすめ商品★
泥付き下仁田ねぎ

《生産の言葉》
年5回行う養蚕の時期に、桑を食べたお蚕さまが出すフンを下仁田ねぎの畑に入れて、土づくりを行っています。お蚕さまのフンとても栄養価の高い肥料になります。この下仁田ねぎはお蚕さまの力を借りて大きくなりました。