監督 スジョイ・ゴーシュ 出演 ビディヤ・バラン、パラムブラト・チャテルジー
脚本が巧みにできている。妊婦が事件解決に取り組むというのはコーエン兄弟の「ファーゴ」のよう。妊婦はふつうの女性より動きにハンディがある。男に比べて、もちろんハンディがある。そこにどうしても目がいってしまう。意識が集中してしまう。これを巧みに利用している。
疾走した夫が宿泊していたから、という理由で安ホテルに泊まる。事件を追うだけなら、別に泊まる必要はない。調べるだけ調べたらちゃんとしたホテルに泊まって体調をととのえながら調べればいいはずなのだが、そうしない。
汚いホテルだからせっせと掃除をする。そういうことはホテルの従業員にまかせておけばいいのだが、「家でもそうしていたから」と気にしない。「ほこりに弱い」のだと言う。それならなおさら高級ホテルに移るべきなのだが……。
で、これが最後に、実は「指紋を消していた」ということにつながる。女はただの妊婦ではない。ただ疾走した夫を探しに来たのではない。ある事件を捜査し、その犯人の殺害を目的に動いていたのだ。犯人を殺害した後、女が殺したということがわかる。その女は誰なのだ。指紋を採取しろ、ということになったら困るので、毎日せっせと指紋を拭き取っていたのだ。こういうことをするためには、高級ホテルでは駄目。まずホテルが汚れていない。さらにルームサービスがしっかりしていて、客が自分で掃除をするなどということはありえない。だから、部屋の掃除などしていたら、この女はおかしい。何か隠している、と観客に気づかれてしまう。
安ホテルでも掃除をしていれば変だと思われるが、妊婦が自分の体調、さらに生まれてくる子供への影響を考えて掃除をしていると言われれば、どうしたって信じてしまう。そこにはまだいない「子供」の存在が、あらゆる想像力を「正しい」と思わせるのである。いやあ、すごいねえ。この観客を誘導する巧みさ。
「不在」を利用する。不在の方が想像力を刺戟し、信じさせる力がある。「存在」しているものは、「存在感」が必要だが、「不在」のものにはせ「存在感」が必要ではない。一般的に「存在感」は「役者」が表現するものだが、「不在」の「存在感」は観客がかってに作り上げてしまう。
で、この「不在/存在」の交錯は、映画全体のテーマともなっている。「夫」はほんとうにいるのか。「夫と顔の似た男」はほんとうにいるのか。もしかすると二人は「同一人物」なのではないのか。舞台となっているコルカタでは人は「二つの名前」をもっている。そうであるなら「夫」が二つの名前をもっていて、その一方だけを妊婦につたえていたということもありうる。(妊婦/妻はコルカタに暮らしているのではなく、イギリスから夫を探しにきた、という設定である。)
で、最後の最後。その「不在/存在」のテーマは、あっと驚くことをやってのける。妊婦と思っていたら、妊婦ではなかった。「胎児」は、そのときはいなかった。女には妊娠の経験はあるが、コルカタで捜査をしているときは妊娠していなかった。変装していたのである。まわりの人間を騙す/信用させるためである。「妊婦」を前面にだすことで、女自身の任務を不在にさせていた。隠していた。
あ、やられたね。
唯一の「疵」を言えば、女が「夫」を探すふりをしているときの写真。夫の職場を訪ね、たった一枚の写真を職場の人事担当にみせる。その写真をそこに忘れていく。人事担当はその写真をあらためて見直して、「あの男だろうか」と思い出す。この「思い出し」そのものは変ではないのだが、女がたった一枚の写真を忘れていったのに、そのことを気にしていない。それが、あれっと思わせる。夫が映っている大事な写真。コルカタで夫の「存在」をひとにつたえるたった一枚の証拠。それを忘れていって、なぜ平気? 人事担当が忘れていった写真を取り上げ、ふと過去を思い出した瞬間、私は一瞬、あれっと思ったのだが、この人事担当はすぐに殺されてしまうので、その瞬間に疑問も忘れてしまった。
「不在/存在」の交錯、という点で、この映画は「シックスセンス」のテーマを引き継いでいるかもしれない。インド人の「想像力」には「不在/存在」の関係が強く影響しているのかもしれない、とも思った。
(KBCシネマ1、2015年05月08日)
*
「映画館に行こう」にご参加下さい。
映画館で見た映画(いま映画館で見ることのできる映画)に限定したレビューのサイトです。
https://www.facebook.com/groups/1512173462358822/
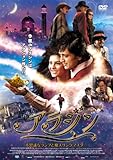 | アラジン 不思議なランプと魔人リングマスター [DVD] |
| クリエーター情報なし | |
| ファインフィルムズ |