
スウェーデン版「フォレスト・ガンプ」と書いてしまうと、もうそれでおしまいのような気がするが。
ミソは主人公が波瀾万丈の人生を生きるというよりも、 100歳になって、こんな気ままな生き方ができるのは波瀾万丈の人生を生きてきたから、波瀾万丈のなかで何が起きても生きて行けるという「実感」をつかみ取ったから、ということかな。
いろいろおかしいシーンがあるのだが、私が最初に大笑いしたのは主人公がバスの切符を買うシーン。北欧だからシニア割引がある。(けっこうルーズで、私はノルウェー・ベルゲンのケーブルカーに乗ったとき65歳と言ったら半額で乗れた。)で、係員が「65歳以上?」と聞くのだ。 100歳なのだから、どう見たって65歳以上。もちろん答えをきかずに、「そうだよね」というようなことを自問自答して切符を売る。
私は自分の経験もあって、大声を出して笑ったのだが、まわりが誰一人笑わない。
あ、こうなると映画がおもしろくなくなる。かつて大阪のロフトで「フランキー・フランク」を見たとき、私が笑うたびに間を置いてふたつ席を離れたおじさんが笑う。ほかは誰も笑わない。私が笑う、おじさんが笑う。掛け合い漫才のように、少しずれて。私とおじさんの間の女性は映画を見るというよりもひっきりなしにノートに何ごとかを書いている。うーん、だんだん笑いにくくなる。大阪人って、変。
同じように福岡の人も変かも。
コメディーなのに12歳未満は見られない制限つきの映画。笑いには皮肉(人間批評)がいっぱいだし、映像もかなりえげつない(ただし血は思いの外飛び散らない)。こういう映画って、声を出して笑わないと、体の中に変なものが溜まってしまう。
私は最初の私の笑い声があまりにも響いたので(ほかに誰も笑わなかったからね)、あとは抑え気味に笑うようにしたのだが。
次に笑いをこらえることができなかったのが、やっぱりバスの切符売り場の男が出てくるシーン。男はお爺さんを見張っていなかった(?)という理由で、お爺さんに大金が入った鞄をあずけた若者に暴行される。それで警察に被害届を出しにゆく。そのときの「供述」がまだるっこしい。それで、ついてきた妻がかわりに話のポイントを整理して警官に言う。この間合いが、あ、夫婦だねえ、こういう夫婦いるねえ……と笑わせる。
100歳の主人公と、たまたま出会った老人が、鞄を追いかけてきた若者を冷凍死させてしまったあとのエピソードもおかしい。死体を捨てにいく途中、サッカーを教えている男(高齢者)に目撃される。その目撃したことを警官に聞かれ、説明するとき、「いっしょにいた若者はあいさつもしない」と苦言をつけくわえる。死んでいるからあいさつなんかできないのだけれど、そうか、老人は若者があいさつをしないことに不満を持っているのか、ということがわかる。そこに若者に対する批判もあれば、老人の人生観へのめくばりもある。
どのシーンも、こういう感じ。
いかげんな感じのストーリーなのだけれど(映画だからいいかげんでいいのだけれど)、その細部がいいかげんではない。きちんと人間を見ている。瞬間瞬間にあらわれる、そこに生きている人間の「本質」のようなものがちらりちらりとのぞく。そのちらりちらりがいい。
波瀾万丈なのだけれど、そこに「こういう人いるなあ」と感じさせるものがある。こんなことでよく生きてこれたなあ。こんな感じだから生きて行けるんだろうなあ、とも言える。で、見終わったあと、こんな感じで生きていきたいなあ、と思う。人間なんて、いずれは死ぬのだから、好き勝手をした方が勝ちなのだ。
あ、もっと大声で笑いつづければよかった。そうしたらもっと楽しくなれた。もっと笑えば、誰かがつられて笑い出したかも。観客が笑ったからといって映画そのものが変わるわけではないが、いっしょに笑うとみんなで見ている、これが映画だって気持ちになれるからね。
(2014年11月12日、KBCシネマ1)
*
「映画館に行こう」にご参加下さい。
映画館で見た映画(いま映画館で見ることのできる映画)に限定したレビューのサイトです。
https://www.facebook.com/groups/1512173462358822/
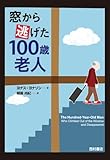 | 窓から逃げた100歳老人 |
| クリエーター情報なし | |
| 西村書店 |