八柳李花「sanctuary18 」は、想像力をむりやり駆り立てる。
行きずりの眩しさに冴え、
駅舎の灰の屋根をたどる
平らかな驟雨に濡れ。
頬を伝わる水滴の酸い汚穢を
舌先でなつかしみながら。
喉をしめらせる過度の慰みを
一身に受け路傍をさまよっている、
夏に廃されたプラットフォームの
白い廃墟に声をからし。
文字と音声のはざまを震撼する
鉄路の響きのうわずみを
かさかさとめくりあげ。
作品の冒頭の部分である。句点「。」が何回か出てくるが、読点の一般的な使い方と違っていて、ことばはそこでは完結していない。「驟雨に濡れ、○○した。」がない。「結末(?)」を省略したまま、ことばが進んでゆくのである。
この「中断の継続」を読み進むとき、私は、省略された何か、「○○した。」を追い求めるようにして、先へ進むのである。
この不思議な中断が、想像力を駆り立てる「仕組み」である。
想像力が、いま読んだことばではなく、書かれていないことばを追いかけるので、かかれたことばの奇妙さが気にならなくなる。
(と、書きながら、私はその奇妙だけれど気にならない部分の「奇妙」について書こうとしているのだから、私の書いていることは「矛盾」なのだが……。)
たとえば、「眩しさに冴え」とはどういうことだろう。冷える・澄む・あざやか。何か、うまく、ことばが結びつかない。ふと出会った光景が「眩しく」感じられる。その「眩しさ」によって、意識のよごれ(?)が払拭され、瞬間的に透明に澄む。その結果、世界があざやかに見える。そうして、意識はまっさらな、冷え冷えとしてような感じになる--ということかもしれないが……。
なにか、そこには「わからないもの」がある。
そして、その「わからないもの」がある、という感じが、いっそう想像力を誘うのである。「わからないもの」がある。それは、中断されたことばが、進んでゆく先にあるという印象を強めるのである。
ただ、そのことばが進んでゆくのは、いま書かれた「ことばの外部」ではなく、「ことばの内部」である。
と、ここでも、私は「矛盾」を書く。
中断しながら進むことばを追いかける、と私は書いたが、「進む」というときは一般的に、「いま/ここ」という一点から、外へ向かって進むものである。--しかし、八柳のことばを読むとき、私には、そういう感じがしないのである。
八柳のことばは先へ進む。しかし、その進む先は、「内部」である。それは別なことばで言えば、「逆戻り」である。
1行目の「行きずりの眩しさに冴え、」を、私は正確に読むことができない。なんと書いてあるか「わからない」。その「わからない」の内部へとことばが進んでいく、と感じるのだ。1行のなかに、矛盾がある。先へ進むはずのことばが、先へではなく「内部」に向かう。
--その矛盾のために、ことばは「中断する」。
「中断」が、ことばの進む方向が「内部」である、と印象づけるのである。
で、その「内部」なのだが--これが、また何とも不思議。
古くさい。古くさくないのかもしれないけれど、古くさいという印象を呼び起こす。
たとえば「駅舎の灰色の屋根」。
「駅舎」って何? いま、そんなことばつかう? 「駅」としかいわないのでは? いまでは、建物を強調するときにしか「駅舎」とはいわないだろう。それに、建物を強調するときにだって、普通は「駅ビル」だろう。「駅舎」なんて、せいぜいが、明治にたてられた様式風の木造駅舎という具合につかうくらいだろう。
この古くさい感じが、より「ことばの内部」を印象づける。八柳のことばはいま流通していることばではない時代のもの--八柳のことばは、すでにつかわれなくなったことばなのである。「いま」が封印していることばなのである。
「内部=過去」へもぐりこみながら、そこから、ことばをあらたに拾い上げている。
たとえば「平らかな驟雨」の「平らかな」。「驟雨」は古くさいだけだが、「平らかな」は違う。「古くささ」によごれていない。それは、つまり「平らかな驟雨」ということばの結びつきが、「過去」にはなくて(あるかもしれないが、無知な私は知らない)、八柳の「内部」(八柳の「肉体」)にのみ存在するからである。
句点「。」でことばを中断させながら、八柳は、八柳の「内部(肉体)」に隠れていることばを引っぱりだし、動かす。その動きは、そうして、さらに「内部」へ「内部」へと運動を誘う。
鉄路の響きのうわずみを
の「鉄路」など、「駅舎」そっくりで、時代後れの新聞の見出しぐらいにしかつかわれないことばだが、そのあとの「響きのうわずみ」の「うわずみ」がとてもいい。「響き」と「うわずみ」を結合させたところがとてもいい。
「うわずみ」までことばを追ってきて、1行目の「眩しさ」「冴え」が、あ、これなんだ、と「わかる」。(「わかる」というのは、私はそういう風に「誤読」する、ということである。八柳は別の「意味」で書いたかもしれないが、私はそう理解し、納得する。美しいなあ、と思う、ということである。
何か書きたいことがある。その書きたいことというのは「肉体の内部」にある。八柳自身のなかにある。外にではない。その「内部」へ「内部」へととこばを逆戻りさせるようにして進んでいくと、「内部の内部」に「うわずみ」がある。
これは、もちろん「矛盾」である。「うわずみ」は上の方にある。「内部(下部)」には存在しない。--けれど、詩のことばの運動では、そういう矛盾を突き破って、そういうことが起きるのである。
断定せず、中断し、中断しながら継続するという、八柳のことばは、そういうことを引き起こすのである。
残念なのは、詩の最後である。
信号機は太古に振りおろされていた、
やわらかな軋轢に包まれ。
まるくなる、胎児のように
眼を閉ざしたまま。
私たちは閉ざされたまま。
「内部」であるから「とざされたまま」というのは矛盾ではない。
矛盾ではないことを書くことで、最後の最後で、八柳は何かを「間違えている」。「矛盾」で終わらなければ、詩ではない。「内部」へ逆戻りしながら進むことばは、「内部」に閉じ込められてしまってはいけない。「内部」を突き破って、「内部」でも「外部」でもない、「名付けようもない場」を見つけ出さないといけないのだ。
「閉ざされている」から「聖域」、なのではなく、「名付けようもない」から、「ことばのなかにしかない」(名付けようもないと、ことばのなかにしかない、というのは「矛盾」だが……)から、「聖域」なのではないかと、私は八柳のことばを追いなから思ったのだ。
--でも、まあ、私がここで書いているのは連作の1篇に対する感想に過ぎない。連作全体で、もっといろいろな動きを書きながら、ことばは別の世界をつかむかもしれない。
*
文月悠光「今日の渇き」は、とても具体的である。八柳のことばとちがって、あくまで「私」から「外」へ向かってことばが動く。「私」の「外」、つまりそこにあるものを描写する。だから、とてもわかりやすい。(わかった気持ちになれる。)
日めくり暦を留めていた画鋲を
壁からそっと抜き取ってみる。
日々の重みを一途に受け止めてきたのか、
それは思いの外大きく、壁に穴を拡げていた。
こういうときに「一途に」ということばが出てくるのは、文月が「一途」な正直さを生きているからだろう。
具体的に、「外」の世界の「細部」をていねいに描くことが、ここでの文月の「一途」である。
「一途」に先だつ「そっと」が「一途」をいっそう引き立てているが、これは文月の「狙い」か、それとも「地」か。あいまいなことろが魅力的である。
と、思いながら読みはじめたのだが……。
穴に額を寄せると、
その細い闇が
ひめやかに胸の芯へと忍び入る。
あ、この「転調」。いいなあ。「外」を具体的に(そっと)ていねいに一途に描写していると、「外」と「私」のあいだに不思議なつなぎ目(通路)ができる。その通路がきちんとできるまで、文月はことばをていねいに動かす。中断させたり、飛躍させたりしない。
文月は、とこばを動かさずに「肉体」を動かす。「穴に額をよせると、」という具合に。そして、肉体を動かしてから、ことばを動かすのである。
これは、ほんの「ひと呼吸」の問題なのだが、この「肉体」を動かしてから「ことば」を動かすというタイミングが、とてもいい。
で、動きはじめたことばが、加速する。
ひめやかに胸の芯へと忍び入る。
「ひめやかに」など、なんともうさんくさいことばだと思うのだが、文月のことばがていねいに一途に動いているので、はっと驚くほど美しい。
ことばは、どんどんことばになっていく。--つまり、ことばが、「いま/ここ」をととのえてゆく。
画鋲の穴がまたたき、星々を成す。
かぼそい闇を抱きながら
壁は星空へ転身していく。
ことばが世界を描写するのではなく、世界がことばへむかって整っていく。
 | Beady‐fingers.―八柳李花詩集 |
| 八柳 李花 | |
| ふらんす堂 |
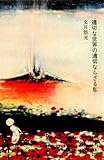 | 適切な世界の適切ならざる私 |
| 文月 悠光 | |
| 思潮社 |