なんともフランスっぽい。といっても、私が知っているフランスというのは限られているけれど。
どこがフランスっぽいかというと「個人」主義。この映画には「組織」が欠如している。「組織」はないけれど、個人と個人の人間関係がある。フランスの「組織」というのは、結局、アベック(古いことばだねえ)、2人が基本だ。1人を超えれば「組織」。まあ、これが面白いといえば面白いね。笑えるね。
「売春組織」も「海賊版組織」も「警察」も、ぜんぜん広がりを感じさせないでしょ? 警察署長に刑事が2人、売春組織の殺し屋2人、海賊版組織も2人、郵便配達の少年(青年?)を助ける少女と中年男が2人、そして主役の郵便配達の少年とディーバがまた2人。単純で、美しい。
で、このとき「組織」というのは「組織」というより「直接関係」と言い直した方が、フランス人の考え方の面白い部分が見えてくる。何かをするとき、それは、その「対象」と「私」の問題。「他人」は関係ない。「他人(複数)」がいないから「組織」もない。「組織」というのは「複数の他人」を取りまとめる方法だからね。
そして、この「個人」の問題を、「芸術(音楽)」に重ね合わせたのが、この映画。
オペラは「集団芸術」だけれど、ここでは一人の歌姫(ディーバ)に焦点が当てられる。「音楽」は「レコード」という媒体(組織が作り上げた、組織の金儲けの手段)を通しては伝わらない。ディーバが歌うその場へ人が出かけ、そこで聞く。会場には不特定多数の聴衆がいるが、「音楽」に触れるのは、あくまで「個人」。「個人」として、音楽を聞くのである。そのとき、ディーバと「一人の聴衆(少年)」の恋愛が成立する。そこに「音楽」の至福がある。
フランスでは、あらゆることが「恋愛」、つまり、「2人」の関係。
ディーバの歌う「アリア」も、ディーバにとっては「楽曲」と「歌手」という「2人」の関係。
「恋愛」だけがフランス人にとって受け入れることができる「組織」というか「団体活動」なんだねえ。
何が言いたいかというと・・・。
この映画に登場する「組織(組織の末端)」が「2人」にこだわっているのは、ディーバと少年の「2人」の関係を浮き彫りにするためである。
だから、といっていいいのかな、ディーバと少年がほんとうに「2人きり」になるシーン、夜のデートのシーンが美しいなあ。少年が傘をさし、ディーバが悠然と、気ままに、街をさまよう。どこかのテラスで休む。最初は2人は離れているが、少年が少しずつ近づいて行き、ディーバの肩に触れる。その「接触」(直接的なふれあい)をディーバは受け入れる。いいねえ。この静かな感じ。恋愛の至福。
この、夜の散歩と同じくらい気に入っているのが、東洋かぶれの男とベトナム人少女の恋愛の「場」。少年と同じように、「ロフト」に住んでいるのだが、装飾品に「止まらない波」のオブジェがある。その波の色が美しい。その波の底で中年男は「孤独」を生きる。その「孤独」からときどき浮上して、少女と恋愛をする――ここに、中年男の「夢」がある。いつでも「個人」でいたい。「組織」に属さず一人でいたい。けれど、さびしくなったら(?)、「恋愛」をして生きていることを確かめる。女は(少女は)、そういう男のわがままを受け入れる。
フランス人は恋愛を重視する、恋する女が「不名誉」な状態にならないように配慮する――といわれるけれど、違うんじゃないかな? ほんとうは、女にわがままを受け入れられたい思いの男で満ち溢れているんじゃないのかな? 無理に気取っているんじゃないのかな?
男がしでかした「結末」を受け入れるのはディーバ(女)であり、女刑事(これがあるから、刑事はやめられない、と最後に言う)だもんねえ。
――という、ジャン=ジャック・ベネックスの映画の奥に眠っている「夢」を分析してみました。
多くの映画は、2度目に見るときは、どうしても視線が「斜」になるなあ。1回目を見るときのように、まっすぐにのめりこめないいなあ、と「午前十時の映画祭」の作品を見ながら思うこのごろ。
*
天神東宝の音響は相変わらずひどい。途中で必ず入る「びりびりぶおぉぉぉん」という音はどうにかならないのか。
(2011年08月20日天神東宝3、「午前十時の映画祭」青シリーズ29本目)
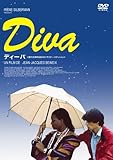 | ディーバ [DVD] |
| クリエーター情報なし | |
| Happinet(SB)(D) |