私はこの映画はあまり好きではない。ことばが多すぎる。また、長すぎる。
いちばん好きなシーンは、ノミのサーカスのシーンである。実際のサーカスでやってうけるかどうかはわからないが、映画では楽しい。ノミを追うチャプリンの目の演技がはっきりわかるからだ。私だけの印象かもしれないけれど、私には、チャプリンの目は、ノミを見ていない。もともといないのだから見えるはずはないのだが、それでも見えていると思い演技をするのが、ふつうの俳優の演技だと思う。チャプリンは、そうではない。最初から目を見せるために演技をしている。ノミを見せるための演技ではなく、目を見せるためにノミの存在を利用している。他の動きもそうである。ノミがいるから、そんなふうに動くのではない。チャプリンが演じている動きそのものを見せるために、架空のノミがひっぱりだされている。そんなふうに見える。
「役」を見せたいのではない。チャプリンという「肉体」を見せたいのだ。こういう姿勢は、私は嫌いではない。役者らしくていいなあ、芸人らしくていいなあ、と思う。「役」そのものは、「役」でしかない。
ラストシーンも、わりと気に入っている。チャプリンが死ぬ。舞台の上では、クレア・ブルームが踊りつづけている。チャプリンが死ぬ(死んだ)ということを、クレア・ブルームは知っている。知っているけれど踊ることをやめない。その芸人魂、芸人根性のようなものが、なんだか気持ちがいい。チャプリンが芸人に伝えたいのは、そういうことだろうと思う。何があっても動いてしまう「肉体」、「肉体」を見せつづけるという姿勢。「肉体」を見せたい、というのが役者の(芸人の)欲望である。その欲望を貫くこと--それが美しい。観客が見ている「肉体」を演じつづけるのではなく、自分の「肉体」をさらしつづけるのだ。
観客というのは単純である。クレア・ブルームが踊るのをやめ、死んでいくチャプリンに駆け寄るのを見れば、その瞬間に、クレア・ブルームの演じている「役」など忘れ、現実に起きている「物語」の方へ一気にのめりこむ。架空の芝居よりも現実の方がはるかに好奇心を刺激するからである。そのとき、観客は役者の「肉体」など見ない。そこで実際に起きている「こと」を見てしまう。役者の「肉体」は消えてしまうのだ。
これでは役者の意味(存在価値)がなくなる。
だから、クレア・ブルームは、死んでゆくチャプリンに駆け寄りなどはしないのである。そんなことをしないのが役者(芸人、パフォーマー)であることを学んだからだ。
別な視点から言いなおそう。
チャプリンがドラムの上に落ちて動けなくなる。そのままでは死ぬだけだとわかっていても、舞台に出て何か言う。それは芸人として観客に対して責任を持つという見方もあると思うが(そういう見方の方が多いと思うが)、私はそうではなく、芸人というのは死につつある(動けない)という「肉体」さえ、見せたいのだと思う。
こういう「本能」のようなものが噴出する瞬間が、私は好きである。こういう「本能」が噴出する瞬間というのは「本物」という感じがする。この「本能」は私のもっている「本能」とは無縁である。私などは、痛いときは痛いと騒ぎまくる本能しかもっていない。だからこそ、私を超越する「本能」を生きているひとを見ると引きつけられる。好きになる。すごいものだと思う。
考えてみれば、役者というのは変な存在である。それはチャプリンも実感していたのだと思う。だからこそ、映画のなかに、とても強いことばが出てくる。「血は嫌いだが、血は私の肉体のなかを流れている」。それが生きている、ということなのだ。
あ、なんだか、映画の感想という感じがしないね。書きながら、そう思う。こういう感想しか書けないのは、この映画が心底好きではない、という証拠である。などと、もってまわった言い方になったが、実際、私はこの映画がなぜ「名作」といわれるのかさっぱりわからないのだ。「キッド」の方がはるかにおもしろいのに……。でも「キッド」は「午前十時の映画祭」のなかには入っていない。
*
少し補足(?)すると……。
この映画でのチャプリンの目はなんだかすごい。私は「人間」を感じない。「役者」を感じる。入っていけない。多くの人間がもっている「感情の交流」というか、やわらかみ、弱みをもっていない。完璧に「自立」している。
「こころの一部」というより「肉体の一部」。
チャプリンは「こころ」を見せるのではなく、「肉体」を見せる。それは「目」においても同じ。その強靱さが、私は怖いのである。
(「午前十時の映画祭」27本目)
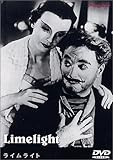 | ライムライト [DVD] パイオニアLDC このアイテムの詳細を見る |