題材は非常におもしろいし、「ニセ札」づくりが「軍国主義批判」にかわるのも楽しいのだが……。
一つ一つの映像が長すぎる。編集し直せばおそらく半分とはいわなくても5分の3程度の長さにはなりそう。一つ一つの映像が長いと、見ていて緊張感がなくなる。
たとえば、倍償美津子が世話をしている知恵遅れの青年が、軍隊あがりの青年が仲間を銃殺するのを目撃するシーン。ぱっと見て、ぱっと逃げる。思わず亀を落としてしまう、と2秒もかからないシーンなのに、役者に演技をさせてしまう。そうすると、よほど演技力がないと、スクリーンの緊張感が保てない。間の抜けた、というか、むりやり演技している顔がスクリーンに残ってしまう。
人だけではなく、風景のショットも少しずつ長い。風景に演技をさせるというのはとてもいいことだと思うけれど、長くなると、風景に必然性がなくなり、安手の観光案内のように見えてしまう。
いちばん問題が多いのは、倍償美津子の法廷での証言シーンである。そこでは、この映画の重要なテーマ「軍国主義批判」が展開されるのだが、それは「ことば」だけであり、あ、こんなことばを伝えたいのなら、映画ではなくて「小説」の方がいいだろう、と思ってしまう。映画はまず映像でなくてはならないという基本が最後で完全に踏み外されている。その証言のあとに、法廷に1000円札が飛び交うという美しくなるはずのシーンも、ことばの説明のための紙芝居的映像になってしまう。
また、倍償美津子が証言で語るもう一つの事実、「やっているうちに楽しくなった」が、やはりことばだけなのも大失敗である。「ニセ札」づくりで倍償美津子や他の登場人物が楽しくてやめられなくなった、という印象は、とても感じられない。紙漉き職人が白すかし、黒すかしの違いをとくとくと語るシーン、軍隊あがりの青年が「ニセ札」の原盤の写真撮影の露光時間をめぐって写真屋と対立するシーンなど、ちょっとマニアックな歓びの瞬間もあるのだけれど、それが増幅していかない。
この原因のひとつは、「ニセ札」づくりの集団と村人との関係にある。
倍償美津子は、村人から「ニセ札」づくりのための資金を調達するという重要な役割である。そこに村人と犯罪集団の「親和関係」のようなものが発生し、それが犯罪をささえ、歓びをもりあげる(深める)はずなのに、その「親和関係」、あるいは一種の「共犯関係」、うさんくささがもつおもしろさがうまれるはずなのに、それがない。提供資金に小銭が混ざっていたり、金がないので子山羊を金の代わりに提供したりという細部も描かれるは描かれるのだが、いまひとつ、しっくりこない。描写にていねいさがない。ストーリーの紹介に終わっているせいである。
小さな村のことである。そんな村では何かを隠れてやるということは不可能である。そんなところで何かをやれば、それがたとえ犯罪であっても、それは一種のお祭りに変わるはずである。その犯罪からお祭りへの加速度的なふくらみ、それを伝える映像がこの映画にはなかった。
だから、倍償美津子がいくら法廷で「楽しかった」といっても、そんなことを言われてもねえ……とため息が出てきてしまう。
映画は一種のカーニバルである、ということは監督の木村祐一には分かってるはずである。カーニバルであると分かってるからこそ、最後を、1000円札の紙飛行機が飛び交う法廷シーンにしたかったのだと思う。その狙いが分かるだけに、実際に、映像がそうなっていないのを見るのは、とても無残である。
意図だけがあって、形がない。意あまって血から足りず、という映画であった。
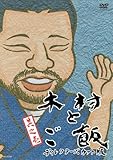 | 木村とご飯 Vol.1 [DVD] R and C Ltd. このアイテムの詳細を見る |