監督 ユー・リクウァイ 出演 オダギリジョー、アンソニー・ウォン、チェン・チャオロン
驚くほど鮮やかな緑。しかも圧倒的な自然というよりは(圧倒的ではあるのだが)、人間になじんだ緑である。暮らしのなかで見える緑、暮らしの手垢で磨かれた(?)緑なのである。つまり、暮らしが緑に侵食している。日本に(アジアに?)ひきつけて言えば、山の田んぼ、そのあぜ道から始まる山の緑という感じなのである。ブラジルでは、田んぼ(農村)ではなく都市である。本来、融合するはずのないものが、この映画では融合し、その融合によって、緑が鮮やかになる。補色が隣り合わせ緑なのである。実際、緑なのに赤を意識してしまう緑である。(これは最後に重要な意味を持つ。)
なぜ、こんなことが起きるのか。監督が、あのジャ・ジャンクー監督「長江哀歌」のカメラマンであるせいなのか。それも確かにある。アジア人の見た緑である。だが、同時に、この映画がアジア的人間関係を描いているせいもある。ストーリーにぴったり合致しているのだ。アジア的生活をすれば、目もアジア的になり、緑もアジア的に見えてくるのだ。それがたとえカメラを通したものであっても。
父と子、親分と子分、一種の「家族」感覚というのはどの民族にもあるものだけれど、民族によって何かが微妙に違う。アジアの場合、「個人主義」が弱い。そして儒教的なものが強い。「孝」の匂いがする。人間と緑の関係も、どこかに「孝」のようなものを含んでいて、それが「暮らし」(暮らし方)を感じさせる。「ひととひとのつながり」を優先するように、自然とも、対立ではなく、共存を大切にする。そのまなざしが、街の風景をとらえるとき、暮らしが滲んだ風景になる。(「長江哀歌」に通じる。)そして、「共存」、共存するための丁寧な関係の積み上げという暮らしを通じて、自然の緑と、街の暮らしが通い合う。
ここに、「共存」をよしとしない人間が割り込んできて、この映画の暮らしが崩れていく。その破壊のメカニズムは、ちょっと断片的すぎて分かりにくいが、それはその崩壊をあくまで主人公父子の関係を描くことで描ききろうとするからである。破壊する側の動きは最小限しか描かない、父子から見えるものしか描かないからである。闇社会の裏の動きを、実はこんな動きがあります、と説明しないからである。
説明の省略という「野心」を含んだ、あくまで映像にこだわった、映画のための映画なのである。
この映画の最後は、森へ、緑へ帰っていく。
その場所は、かつての生活の場であった。そこでの生活は金掘り、ゴールドラッシュにかけた人間の生活である。争いがあり、殺しもある。血が流された歴史がある。暮らしには、そういう暗部もある。いま、父としていきている男は、実は息子の本当の父を殺しているのだ。そのことを子は突然、フラッシュバックのように思い出す。その記憶、血の赤さが補色として、ふいによみがえる。偽りの父子の血の流れをたたき切って、本当の血が結びつく。噴出する。ギリシャ悲劇のように。
そのとき、緑が一変する。補色に向き合う鮮やかな緑を通り越して、ぶきみに深い深い緑になる。その瞬間がすごい。
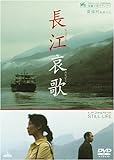 | 長江哀歌 (ちょうこうエレジー) [DVD] バンダイビジュアル このアイテムの詳細を見る |