この映画はバージン・クウィーンといわれたエリザベスの誕生秘話である。エリザベスというとどうしてもケイト・ウィンスレットの「エリザベス」を思い出してしまうのだが、そのエリザベスが、この映画のナタリー・ポートマンから生まれたのか、と思うと、なるほどなあ、と納得してしまう。
歴史と映画がごっちゃになってしまう感想だが、ケイト・ウィンスレットの演じた気性の強靱な女性像--それは、この映画でナタリー・ポートマンが演じたアンという女性、気が強くて頭の回転が速くて、美人の血を引き継いでいる。そのことが、くっきりと伝わってくる。変な話だが、アン-エリザベスという人間像のなかに、血がつながっているという、非常に説得力があるのだ。「変な」というのは、「エリザベス」の方が古い映画なのだから、「エリザベス」の人間像はナタリー・ポートマンの演じたアンに影響されるはずがないのだから……。頭では理解していても、映画を見終わったとき、ほんとうにそう思ってしまうのだ。
ナタリー・ポートマンの演技が、それだけ人間の、剥き出しの強さを具現化していたということかもしれない。歴史と映画をごちゃまぜにしてしまうような、人間の力そのものに触れていたということかもしれない。ほしいものはなんでも手に入れる。そのためにはなんでもする。黒い目の、強い輝きと、白い肌の対比--その強靱な矛盾(?)を感じさせる力が、とてもいい。スカーレット・ヨハンスンに比べると、実にいやな女性になるのだが、そのいやな女性の感じを突き破って目が誘っている。いやな女とわかっていても、その目に誘われる。それが「エリザベス」につながる、と書くと、ケイト・ウィンスレットに叱られそうだが、どうしてもそう感じてしまう。スカーレット・ヨハンスンが演じたメアリーからはエリザベスは産まれようがない。
歴史と映画がごちゃまぜになる感覚を味わうためにも、この映画は見るべきものだ。
この映画のもう一つの特質は、風景のきれいさにある。21世紀に撮影されているのだが、草が太陽の光の中で金色に輝く、その輝きの透明さは現代というよりも、まだ自然が剥き出しのまま生きていた時代のものである。同じように、空が、雲が、光の中でそれぞれに輝いている。剥き出しの命が祝福されている感じだ。この自然の剥き出しの美しさがあればこそ、ナタリー・ポートマンの感情の剥き出しも、命の美しさとしてスクリーンからあふれてくる。
この映画には、ひとつ付録(?)がついている。「みつばちのささやき」のアナ・トレントがヘンリー 8世の正妻(王妃)として出てくる。あ、この目はどこかで見た目だ、と思っていたらアナ・トレントだ。「みつばちのささやき」のときは10歳以下である。そのときから目はかわっていない。ここよりも、はるか遠くを見てしまう不思議な目。ここにとらわれず、永遠を見てしまう目--その力が発揮されるシーン、ナタリー・ポートマンの目、目の前の現実だけを見つめ、現実を変形させてしまう目との対立の一瞬は、見物である。
*
「ブーリン家の姉妹」のとは、ぜひ、この1本をみましょう。
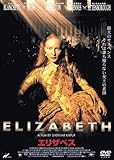 | エリザベス ソニー・ピクチャーズエンタテインメント このアイテムの詳細を見る |
時間があれば、この1本も。
 | レオン 完全版 アドバンスト・コレクターズ・エディション パラマウント ホーム エンタテインメント ジャパン このアイテムの詳細を見る |