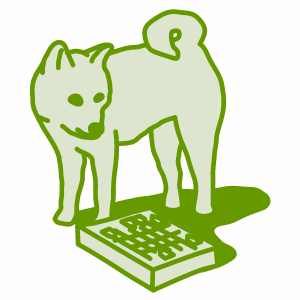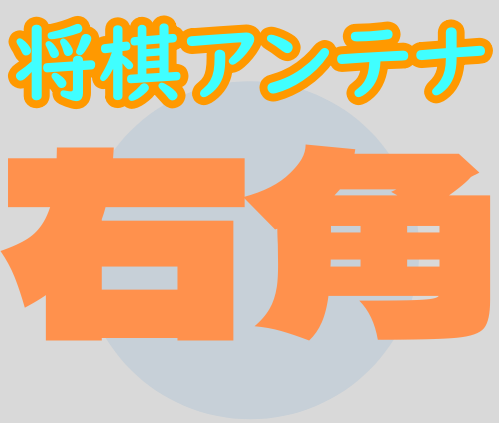読者の皆様こんにちは。雁木師でございます。今日は将棋ポエムの作品を発表します。早速作品を披露したいと思います。
「一門の系譜」
僕は棋士だ
師匠がいる
師匠がいなければ
僕は棋士になれなかった
それは師匠も同じ
大師匠がいなければ
棋士にはなれなかった
将棋の世界を
守るために
僕は弟子を
取ることにした
この子はきっと
プロになれる
そう信じて
時に厳しく
時に優しく
僕が師匠に
教えてくださったように
この一門を
受け継ぐ身として
そして一人の
棋士として
将棋に
恩返ししたい
未来に受け継ぐ
棋士を育てて
解説:今回の作品はいかがだったでしょうか。ここからは、作品と将棋用語の解説に入ります。
今回は、将棋界の根幹となる「師弟」と「一門」にフォーカスを当てた作品です。弟子をとることにしたプロ棋士を想像して作品を作ってみました。プロ棋士になるには師匠がいないとなれません。女流棋士の場合は、日本将棋連盟に所属する場合は師匠が必要になりますが、LPSA(日本女子プロ将棋協会)では師匠の有無は不問とされています。ただ、実際は師匠がいる女流棋士がほとんどです。
(日本将棋連盟所属女流棋士になる場合について)
(LPSA所属女流棋士になる場合について)
さて、今回の作品では弟子を取った棋士の心情を読み解きながら書きました。将棋に限らず、弟子を取るということは並々ならぬ覚悟が必要です。今では藤井聡太竜王名人の師匠としておなじみの杉本昌隆八段は、藤井竜王名人が四段昇段を果たせなかった時は棋士を引退する覚悟だったととある本で知りました。
将棋界には「弟子を取ることが恩返し」という言葉があると聞きます。こうしていくことで、将棋の歴史を受け継いだ側面があります。こうしてできた師弟関係の系譜を一門と言います。作品の終盤に出てくる
「この一門を
受け継ぐ身として」
という文章は、一門の系譜を守るという意味合いもあります。後世に続く棋士を輩出することも、将棋界への恩返しという意味を込めて最後の文章を書きました。
今回の作品では、特に用いた表現技法はありません。口語自由詩に分類されます。
※今回の参考文献はこちら
ここからは、将棋初心者の方でも楽しめる将棋界の「師弟」についてより深くお話ししたいと思います。将棋のプロになるには師匠が必要であることは前述しましたが、現在の師弟関係から、一門の勢力図が見えてきます。
近年は藤井竜王名人の影響か、中京圏出身の棋士・女流棋士が相次ぎ誕生。有名なのは杉本昌隆八段門下ですが、藤井竜王名人の他には、齋藤裕也四段もいます。女流棋士では室田伊緒女流二段、中澤沙耶女流二段、今井絢女流初段がいます。全員愛知県の出身で、杉本八段の師匠である故・板谷進九段から続いた東海地方での普及活動が現在に実を結ぶ形になりました。
中京圏では、岐阜県出身の高田明浩四段と三重県出身の澤田真吾七段、石川優太五段は森信雄七段門下。森信雄七段門下は現役棋士をたくさん輩出している一門で、棋士だけでも12人、女流棋士も4人現役で活躍されています。森信雄七段門下は東海から関西、中国地方までに出身棋士が分散。最も多いのは広島県で4人(山崎隆之八段、糸谷哲郎八段、片上大輔七段、竹内雄悟五段)です。最近では、森信雄七段にとって「孫弟子」と呼ばれる棋士も誕生しました。
さて、関西圏に目を転じますと近年実力派棋士を多く輩出しているのが井上慶太九段門下です。井上九段は兵庫県のご出身ですが、現在は「棋士の町」と呼ばれる加古川市で普及活動をされています。その影響もあって、お弟子さん現役で8人のうち5人(稲葉陽八段、船江恒平六段、出口若武六段、横山友紀四段、上野裕寿四段)は兵庫県の出身です。残りの3人は岡山県に2人(菅井竜也八段、狩山幹生四段)、香川県に1人(藤本渚四段)という構図で、西日本の有力な一門の1つと言えます。
関西圏では、小林健二九段門下も近年若手棋士を多く輩出しています。2017年の古森悠太五段からほぼ毎年プロ棋士を輩出している状況で活気があふれる一門と言えます。現役棋士は8人、女流棋士は3人活躍されていますがそのほとんどが関西圏出身です。実は小林健二九段は、杉本昌隆八段と同じ故・板谷進九段門下。板谷一門の未来は明るいと言えるでしょう。
九州圏に移してみますと、有名なのは深浦康市九段と佐々木大地七段師弟、中田功八段と佐藤天彦九段師弟ですが、九州は関東所属の棋士が開拓した、もしくは開拓しているという影響が強く師匠が九州出身ながら弟子が関東出身というパターンやその逆というパターンもあります。前者は森下卓九段(福岡)と増田康宏七段(東京)師弟、後者は島朗九段(東京)と水町みゆ女流初段(福岡)師弟があります。かつて修業時代に地元九州を離れて、将棋会館に近い関東圏に移り住んで研鑽を重ねた過去を持つ棋士もいること、九州出身の棋士(現役・引退ともに)が少なく、関東圏の棋士に師匠をお願いするケースがあるということが考えられます。また、九州研修会の開設が2016年と歴史が浅いことも影響しているとみられます。近年は、インターネットの普及やAIの進化などもあり、将棋の地域における実力格差はなくなったと言われています。今後、九州出身の棋士はどの師匠から誕生するかも楽しみです。
ここまで中京圏から西側の地域の一門勢力を見てきました。ここからは関東圏の一門勢力図を見ていきます。関東圏で実力派棋士が多い一門は所司和晴七段門下が筆頭に挙げられます。有名なのは渡辺明九段ですが、他にも松尾歩八段、近藤誠也七段、石井健太郎六段など実力派が勢ぞろい。出身地別では関東圏に4人、北海道に1人(石田直裕五段)、愛知県に1人(松尾八段)、和歌山県に1人(大橋貴洸七段)という構図です。
弟子の数の多さで言えば、故・米長邦雄永世棋聖門下も現役で6人の棋士が活躍中です。出身地別では、東北に2人(先崎学九段、中川大輔八段)、関東に3人(中村太地八段、長岡裕也六段、杉本和陽五段)、九州に1人(高崎一生七段)という構図です。かつては、米長永世棋聖の自宅に住まわせて「内弟子」の期間を過ごしたという米長一門の棋士もいます。現在では「内弟子」という制度をとっている棋士は聞きません。師弟の関係も時代とともに変化しているということなんですね。
安恵照剛八段門下は個性派揃いの一門です。現役で活躍する棋士は5人。北海道に1人(日浦市郎八段)、関東に3人(永瀬拓矢九段、佐藤紳哉七段、瀬川晶司六段)、東海に1人(青嶋未来六段)という構図です。それぞれの棋士に癖が強く、永瀬九段や青嶋六段のような強い棋士もいます。また加藤桃子女流四段も安恵八段門下の女流棋士です。
個性派と言えば石田和雄九段門下も有名な一門の1つ。弟子5人はすべて関東圏出身の棋士です。「教授」の愛称で親しまれ、文章の上手さでも有名な勝又清和七段。伝説の「連勝ストッパー」として語り継がれ、今期は順位戦をA級で戦っている佐々木勇気八段。初代叡王として知られ、「野生の観る将」の愛称でファンも多い高見泰地七段などが一門を代表する棋士です。
関東圏で近年注目とされるのが、宮田利男八段門下です。今期竜王と棋王に挑戦の伊藤匠七段。棋王戦挑戦経験のある本田奎六段。アグレッシブな将棋で注目を集める斎藤明日斗五段と才気あふれる棋士ばかりです。去年は一門で初めての女流棋士となる伊藤真央女流2級も誕生。今後の宮田一門の活躍にも期待が高まります。
とここまで、関東圏の一門について見てきました。では、それより北の東北・北海道圏内はどうかというところですが、北海道研修会は2020年。東北研修会は2021年に開設されました。棋士個人ではプロ棋士を輩出している県もありますが、師弟の結びつきに関しては、これからというところでしょうか。関東圏の棋士のもとに弟子入りした北日本出身の棋士が、地元の北海道・東北に戻って普及活動を始めたばかりということもあって時間がかかるかもしれません。
前述したように、地域間での棋力格差がなくなったといえる現代将棋界。どの地方の棋士がどの師匠から誕生するかは更なる注目を集めそうです。
以上で作品と将棋界の師弟に関する解説を終わります。今回の作品に関して、ご意見やご感想、リクエストなどあればぜひコメントをお寄せください。今後の作品に役立てたいと思います。次回の将棋ポエムもどうぞお楽しみに。
近況:北陸の描く将として
元日を襲った能登半島地震から2週間が経ちます。私は富山県の東部入善町に在住ですが、入善町でも実は大きく報道されてないだけで、住宅の被害があったそうです。幸い私が住んでいる自宅(実家)と家族は無事で、現在は震災前と同じく生活ができています。
富山では県西部の被害がひどく、能登半島に近い氷見市では現在も断水の続いている地域もあります。また様々なメディアで、北陸出身のスポーツ選手の方々もご実家が被害に遭われたなどのニュースを見聞きしています。石川県の能登地方の被害はかなりひどいという報道は何度も見ています。改めて被災された方々の一日も早い平穏が戻ることをお祈りしております。
私のできることと言えば募金しかできませんが、微力ながら今後も復興の支えになればと思います。
さて、今回の地震は北陸在住の「描く将」の私に多かれ少なかれ影響を与えました。幸いなことに、色鉛筆などの道具や過去の作品の原画など地震によるイラスト関連の物損の被害はありませんでした。
しかし、今回の地震で私の心と意識は変わりました。これまでは純粋に好きなテーマや棋士・女流棋士、ひいては将棋めしなどを描いてきました。おかげさまで「あつまれ!描く将」に応募してこれまで30枚以上将棋世界に掲載されてきました。優秀賞は取ったことがありませんが、これが「描く将」を続ける原動力と言ってもいいくらい、イラストを描き続けました。もちろん、棋士へのリスペクトを欠かすことも忘れてはいません。
しかしあの地震以降、イラストを描く原動力が変わったのです。地震後、初めて描いた棋士のイラストはこちらです。
私は本来、将棋世界に送ったイラストは掲載されてから当ブログなどで公表することをスタンスとしてきました。しかし今回は、送る前に先駆けて公表したいと思います。富山県出身の野原未蘭女流初段と石川県出身の田中沙紀女流1級です。共通項は、同じ北陸出身でアマ時代に鈴木英春さんに師事したこと。
作品の質は相変わらず我ながら低いレベルだなと感じます。描いたときは質は考えず、ただ一心にこのお二人の活躍を祈願して、北陸に思いを込めて描きました。こうして描くことで北陸ゆかりの棋士を、そして北陸にエールを送る。これが今の「描く将」のテーマにしようと決意しました。北陸出身の棋士はそんなに多くはいません。なのでいずれネタが尽きるのは覚悟の上です。ネタが続く限りは描き続けたいと思います。
「がんばろう北陸」の文字を加えるか否かは迷いました。しかし、XやInstagramなどのハッシュタグにもすでにあること。なにより、地元棋士の活躍や元気な姿が北陸の将棋ファンの希望であることと解釈してこの文字を入れました。たとえ下手くそでも、1人の北陸在住の絵描きとしてこの思いを絵に込めたかったのです。
思いはきっと伝わる。そう信じてイラストを描き続ける。「がんばろう北陸」という思いを込めて文字を入れる。今年は富山、そして北陸に思いを寄せる年になる。それが「描く将」の私ならではの被災地へのエールとして、自問自答はしながらですが気持ちはすでに次のイラストの構想を練っています。
さて、長々と話してきましたが、今日はここまでとさせていただきます。本日も長文となりましたが最後までお読みいただきありがとうございました。